多面的・多角的な見方・考え方を育む「聞くこと・話すこと」の指導法【学ぶ意欲と力を育てる 学習指導の極意⑦】

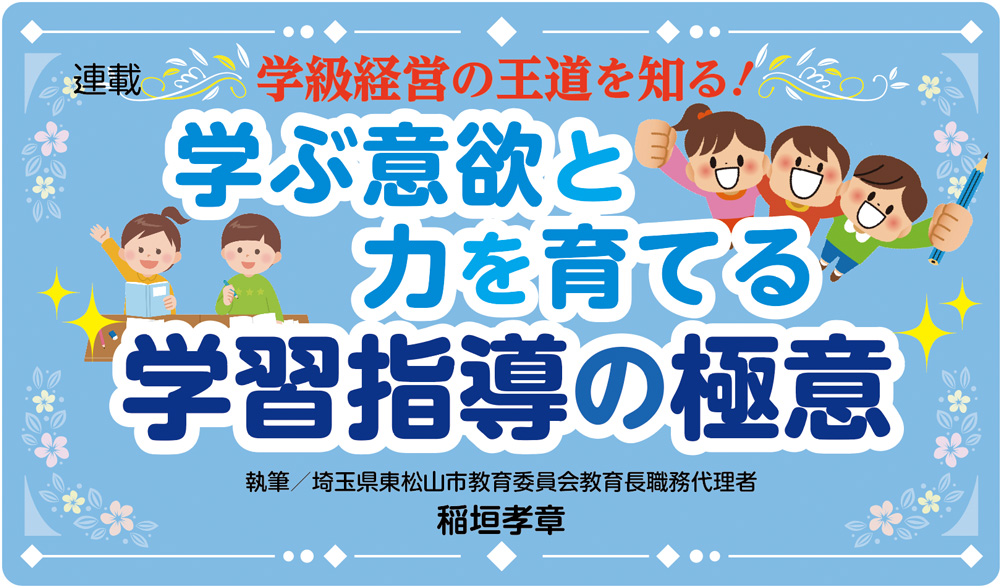
子供たちの学ぶ意欲と力を育てるためには、教師はどのような指導をしていけばよいのでしょうか。学級経営を長年、研究・実践してきた稲垣孝章先生が、全15回のテーマ別に学級経営の本流を踏まえて、学習指導の基礎基本を解説します。第7回は、「聞くこと・話すこと」について解説します。
執筆/埼玉県東松山市教育委員会教育長職務代理者
城西国際大学兼任講師
日本女子大学非常勤講師・稲垣孝章
「聞くこと・話すこと」は、学級経営上の基盤と言っても過言ではありません。特に、聞くことは、話すことを促すことにもつながる大切な指導事項です。相手が心を込めて聞いてくれることにより、話すほうも話しやすくなります。
この「聞くこと・話すこと」の定着は、学習効果を向上させるとともに、子供相互のよりよい人間関係を構築する端緒となります。そこで、「聞くこと・話すこと」を指導するにあたって、次の3つのキーワード「学習を支える『聞くこと』」「学習を広げる『話すこと』」「学習を深める『相互交流』」でチェックしてみましょう。
目次
CHECK① 学習を支える「聞くこと」
相手が自分の話に対して心を込めて聞いてくれると、話し手は心地よく話すことができます。心を込めて聞くことは、単に体を向けて聞くことや頷きながら聞くという形式的なことだけでは身に付きにくいものです。例えば「友達の話をしっかり聞きましょう。それが自分のためになります」といったフレーズで指導することも効果的です。
また、次のような「聞くこと」に関する技能等についても指導していきましょう。
聞くことの技能を踏まえて指導していきます
相手の話を「聞き取る技能」の指導とその定着が求められます。次のような視点をもって聞き取ることが考えられます。
①理由付けをしながら
②答えを類推しながら
➂問題の解決を図りながら
「聞き分ける技能」については、次のような視点が考えられます。
①肯定・賛成の視点で
②否定・反対の視点で
➂補足・修正の視点で
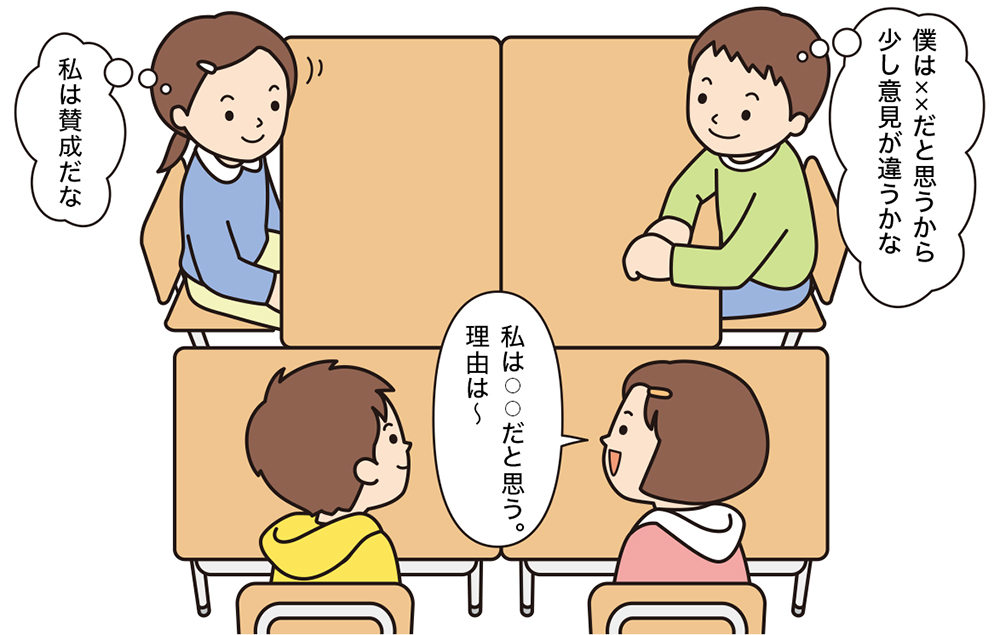
「聞き入る技能」については、次のような視点が考えられます。
①意図を理解して
②類推しながら
➂批判しながら
④理解・納得しながら
CHECK② 学習を広げる「話すこと」
「話すこと」は、自分の考えを整理し、自分なりの言葉で表現することで学びを深めることに直結します。個々の子供が自らの考えを話すことにより、互いに他の考えを知ることができ、学習の幅を広げることにつながります。例えば、「自分の考えを友達に伝えましょう。それがみんなのためになります」といったフレーズで指導することも効果的です。子供たちが進んで話すことができるような学級としての支持的な風土を醸成していきましょう。
話すことの技能を踏まえて指導します
「話し手としての基本的な技能や態度」の指導とその定着が求められます。次のような視点をもって話すことが考えられます。
①要件を落とすことなく
②要点や中心点を明確に
➂計画性をもって
④適切な音量と速度で
⑤平静に落ち着いて
⑥聞き手のことを尊重して
⑦目的に沿った話に
⑧正しい発音で
⑨適切な敬語を使って
また、共通語や方言を場に応じて使い分けていくことも、指導の視点の1つとして配慮しましょう。

