よくわかる教育委員会〜指導主事の仕事を中心に|第8回 指導助言の基本
各学校の研究推進が活発になる5月〜11 月の間は、教育委員会に学校からの指導助言の要請が舞い込みます。まさに「指導主事」としての力が問われる機会です。日頃の研鑽の成果を発揮して地域の学校教育に貢献できれば、これ以上ないやりがいと喜びを感じることができるでしょう。今回は、指導助言にあたって、学校のニーズにしっかりと応えるための準備や方法についてお話しします。
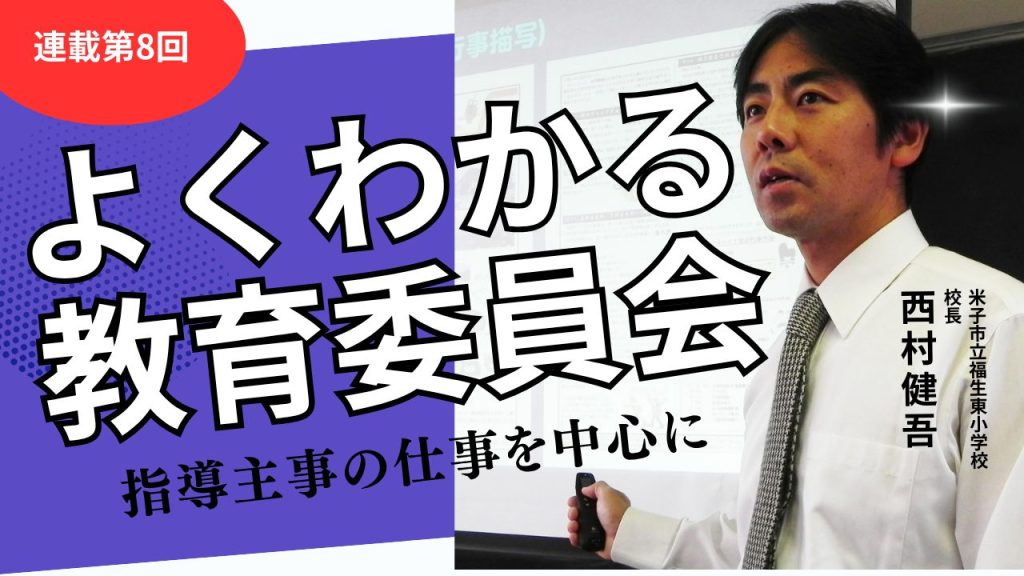

西村健吾(にしむら・けんご)
1973年鳥取県生まれ。東京学芸大学教育学部卒業後、鳥取県の公立小学校および教育委員会で勤務。「マメで、四角く、やわらかく、面白い…豆腐のような教師になろう!」を生涯のテーマにしている。学校教育に関わる書籍を多数執筆。近著は『学校リーダーの人材育成術』(明治図書)。現在、米子市立福生東小学校長。本コラムは、10年間の教育委員会事務局勤務の経験を元に執筆している。
目次
指導助言のポイント
「森」を見ながら「木」を見る
みなさんは、過去、指導助言に来た指導主事の言葉に、「うちの学校が指導してほしい話とズレていたな…」「うちの学校にはうちの学校の、これまでの研究の流れがあるのに…」などと不満に思ったことはないでしょうか。これは、指導主事が学校のニーズを十分捉えていないことから起こる現象です。
そうならないようにするために、指導主事には、国や自治体が示している教育の大枠を外さない範囲の中で、学校のニーズに的確に応えていく指導助言が求められます。要するに、指導主事には『「授業」のみを見るのではなく、その学校の「研究推進計画」を踏まえながら「授業」を見る』ことが求められるのです。
授業の善し悪しを見る視点は、それこそ星の数ほどあります。計画訪問における授業参観では、一般的な視点で見て単に気がついたことを言えばよいのですが、研究推進の一環としての授業研を見る場合、必ずその学校の当年度、あるいは経年の研究推進の営みを俯瞰した上で見る(診る・看る)視点が必要です。
もちろん、指導助言の大半も研究の方向性に沿ったものが求められます。できれば本時の授業だけでなく、研究の方向性までも示唆するような指導助言ができれば最高です。一般的な視点から見たその他の事項については、研究会終了後の校長室で授業者本人に個別に伝えればよいわけです。
「持久力」と「瞬発力」の両面で
指導助言には、「持久力」と「瞬発力」が必要です。ここで言う「持久力」とは、指導案や研究構想を踏まえた上で事前に準備した指導助言、「瞬発力」とは、当日の授業参観を受けての指導助言のことを指します。「持久力」だけの指導助言では授業に即したリアルな指導にならず、かといって「瞬発力」だけではバックボーンや深みに欠けます。
優れた指導助言は必ずこの両立がなされています。資料も用意しながら事前にしゃべることをしっかり準備しつつ、当日の授業内容に即したしゃべりも瞬時に行えるようにしたいものです。
認めることで信頼を獲得
人は「最もがんばったところ」をずばり認めたりほめたりしてもらったときに、報われたと感じます。そしてその人を信頼するものです。言い換えれば、授業者の「最もがんばったところ」を見抜き、認めたりほめたりすることを「できる・できない」が、指導助言者への評価の分かれ目になると言っても過言ではありません。指導助言者は、授業者を評価しているようでありながら、同時に授業者から評価される存在でもあるのです。
指導助言のポイント
指導助言を受ける授業者は、誰しも緊張するものです。まず、その点を考慮して「もし自分が指導助言をもらう立場だとしたら、どんな言葉をもらいたいか」を考えるようにします。そのためには、次のようなポイントに気をつけるとよいでしょう。
- 助言の冒頭では、まず学校や教員の努力をねぎらう
- 授業の成果や工夫を具体的な言葉にして認める
- 改善点は否定や批判ではなく、「こうすると良かったかもしれません」など、提案型で伝える
- 助言は、指導理論や一般論だけでなく「子どもの反応」を根拠にして行う
- 専門用語はできるだけ抑え、分かりやすい言葉で伝える
- 「次はこんな視点で研究を深められそうですね」と未来に向けた視点を示す
記録と情報発信
指導助言ノートの活用
同一学校から複数回、指導助言を依頼される場合があります。ただでさえ忙しい上に仕事がさらに増えるわけですから、指導主事の中には、できれば引き受けたくないと感じる方がいるかもしれません。しかし、これは1回目の指導助言が学校から評価された証左でもあります。まさに指導主事冥利に尽きることと言えるでしょう。ただ、2回目、3回目となると、指導助言の難易度は増すことを肝に銘じなければなりません。
そんなときに備え、以下に紹介するような指導助言ノートを作成しておくことをお勧めします。自分が実施した指導助言を、「持久力(=当日までの準備)」と「瞬発力(=当日の授業を見て話したこと)」の両面から記録として残しておきます。以前の指導助言内容を振り返り、確認することができます。そして、「以前に話したこと(資料)なので話さなくてもよいこと」「以前に話したが繰り返し話した方がよいこと」「新たな視点を加えて話すこと」などが明確になり、指導助言を組み立てる際に大いに役立ちます。
以下に指導助言ノートの実例をしめします。

