地域社会の主体的な担い手を育む『学びのコミュニティ』としての学校へ【福島県大熊町「学び舎 ゆめの森」の挑戦#2】
前回の記事で、文部科学省の田村学主任視学官がその取組に注目してほしいと語った福島県双葉郡大熊町立「学び舎ゆめの森」(以下、「ゆめの森」)。2023年春に避難先からふるさとへの学校帰還を果たして新たなスタートを切ったこの学園は、どのような学び舎で、どのような取組みが行われ、そこには教育者のどんな思いが込められているのか。同校を訪ね、学校帰還時からの校長であり、元「福島県立ふたば未来学園」の副校長でもある南郷市兵校長にお話を伺った。
合わせて読みたい:田村学氏インタビュー「福島県の探究を全国の先生に知ってほしい」【福島県大熊町「学び舎 ゆめの森」の挑戦#1】
目次
本の森を囲む教室で主体的に学ぶ子供たち

「学び舎ゆめの森」(以下、「ゆめの森」)は、JR常磐線大野駅からバスで15分ほど走った、大熊町役場がある大川原地区復興拠点の中にありました。2019年春に帰還が開始されたとは言え、大野駅前周辺にもまだ復興途上の土地が多数残る町内で、この地区だけは、町役場や「ゆめの森」だけでなく、郵便局や医療・福祉施設、公営住宅等が立ち並んでいます(とは言え、周辺には復興途上の土地も残る)。
そのまだまだ新しい地区の中でも、一際目を引くのが「ゆめの森」の校舎です。認定こども園と義務教育学校からなる学び舎を囲う塀はなく、外装にも木材がふんだんに使われた広い1階部分と、建物の中央部に傘のように緩やかに突き出した2階や外光窓等の姿は、さながらこの地に広く根を張り、横に枝を大きく伸ばした木のようにも見えます。


玄関から校舎内に一歩足を踏み入れると、正面(建物の中心)には何階層にもなる、まさに森のような図書スペースである「わくわく本の広場」。本棚で小さく囲われた空間も複数あり、森の隠れ家のような場所で読書にふけることもできそうです。この広々とした図書スペースには、図書広場を見下ろす客席ともなる長い階段状の本棚も設けられており、全校の子供たちが集会を開くことにも使われています。この「本の広場」をぐるりと取り囲むように、乳幼児から小学生の低学年〜高学年のスペースと教室が並び、中学生のスペースは2階に配置されています(乳幼児・児童生徒数93名※2025年7月現在)。
出迎えてくれた南郷市兵校長に案内されて校内を巡ると、低学年のスペースでは、子供たちが教室前の空間で、それぞれがプリントの問題に取組んでいました。ある子供は椅子に座って先生にチェックをしてもらっており、ある子供は床に寝そべりながら一生懸命問題を考えています。

2階には、中学生のスペースの他、サイエンスラボ(理科室)と学習室等が配置されていますが、この日は高学年の子供たちが2つの学習室で学習中でした。5年生の子供たちは、自由進度学習で算数を学んでおり、それぞれが自らの進度で(ときに友達に意見を求めたりもしながら)学習を進めています。

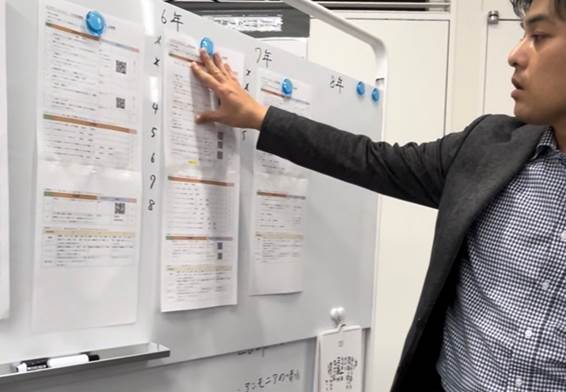
また別の学習室では6年生の子供たちが、地域の高齢者と共に、ブックトークを行っていました。

午後からは、小学校の子供たちが「本の広場」に集まって、「ふるさと創造学」での探究を通して、学んできたことの中間発表を行っていました。

子供たちは、それぞれの興味・関心に応じて、年齢の枠を超えてグループを作って探究したり、一人で突き詰めて探究したりしてきたことを発表します。将来、飲食店をやってみたいという思いを持っているグループは、地域のお店で学び、お菓子作りに挑戦した過程を発表し、友達とペアで地域の虫の採集に取組み続けた子供が、種類や採集場所・採集方法について詳細に発表したりしていました。
地域の人と関わって、多様な情報も得ながら取組んできた活動内容は、映像や画像(背後の壁面に投影)や手書きの資料も活用しながら発表。話を聞き終わった子供たちからは、それぞれの発表から詳細が分からず疑問に思ったことや、興味が湧いてさらに聞きたくなったことなど、質問が出され、それがまた次の探究への大きなヒントになっているようでした。
復興への解は教科書には記されていない

見学後、この「ゆめの森」の創設に携わってきた南郷校長に、このような学校を創設し、探究や自由進度学習、さらには地域と共に演劇づくりも行うなど、新たな視点からの学びづくりを推進してきている意味・意義について伺いました。

南郷市兵 氏
1978年東京都生まれ。2001年慶應義塾大学卒業。IT企業勤務を経て文部科学省入省。東日本大震災後は被災三県の学校で、子供たちが地域復興等に取組む「創造的復興教育」を推進。原発災害で避難対象となった福島県双葉郡の教育復興に携わり、2015年4月、福島県立ふたば未来学園高等学校の開校と同時に副校長として着任。同時に、全国の学習指導要領改訂を審議する中央教育審議会教育課程部会専門委員を務める。2023年4月から学び舎ゆめの森の校長・園長を務める。
「この大熊町には、2011年の原発事故で避難した時から(2019年の町民帰還後も)町に学校がなかったので、一昨年の2023年春に本校が開校してから地域の様子は一変しました。地域の方は、学校の存在意義を強く実感されており、学校がある、子供がいるというだけで、白黒映像と4Kカラー映像くらいの差を感じておられるようです。学校や子供は未来の象徴であり、その存在そのものが『確かに町が続いていく』ということを物語っているのだと思います。
例えば、探究や演劇などの活動を通して、町の方から直接声をかけられることもあります。象徴的なのは、地域の方と一緒に演劇(大熊町の過去と未来を劇化したもの)を行ったときのことで、地域の方は皆、涙を流されていました。同じような大熊町の思い出や大事さを我々大人が語ったとしても、おそらく地域の方は涙を流すことはないでしょう。それだけ、地域にとって子供たちの存在は大きいし、子供たちにも『君たちの力はものすごいよ』と伝えたところです。

その地域の方の涙には、子供たちの力とアートの力との両方が混じっていたと思います。アートの力(=演劇の舞台)を通して、愛する大熊町のもつ豊かさやつらい震災経験や未来の姿を町の方々が感じたということがあり、加えて、それを子供たちがやっているということが大きいのだと思います。そこには、町が子供たちに継承されているという思いと共に、自分たちに続く世代が、自分たちは見られない景色(=未来)を創ろうとしてくれているという感動があるのかもしれません。

『ふるさと創造学』では、子供たちが地産物で商品開発をして販売するというようなプロジェクトもしばしば行っており、そのときの地域の方のうれしそうな顔にも、同じような思いがあるのではないかと思います。
考えてみると、学校教育法でも『主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養う』ことを目標としながらも、これまで学校は社会より教科教育にばかり目を向けて、子どもたちを学校の中に閉じ込め学校が社会から孤立してしまった。そこに問題があったのではないでしょうか。
実際、大熊町や双葉郡が原発事故に見舞われたとき、復興への解は教科書には記されていませんでした。そのため、双葉郡の学校は、学校教育の目標について改めて考え、どのような力を育めば子供たちが幸せになれるのか徹底的に考えたわけです。当時は、探究という言葉は国内の教育現場ではほぼ使われていませんでしたし、アクティブ・ラーニングという言葉も大学教育の文脈で一部使われていたのみです。そのような状況の中で、双葉郡の人たちは自分たちの力で、『ふるさと創造学』という探究にたどり着いたのです。
おそらく、そのような思いに近いものを持っておられる首長や行政関係者、教育関係者は、全国のどの自治体にもいらっしゃるだろうと思います。しかし、その思いが共有され、教育理念や教育目標やカリキュラムが一気通貫した形で整えられているところは、他所にはまだないのかもしれません」

