【特別支援教育】学級経営①「多様性を尊重する学級」指導のポイントとアイデア
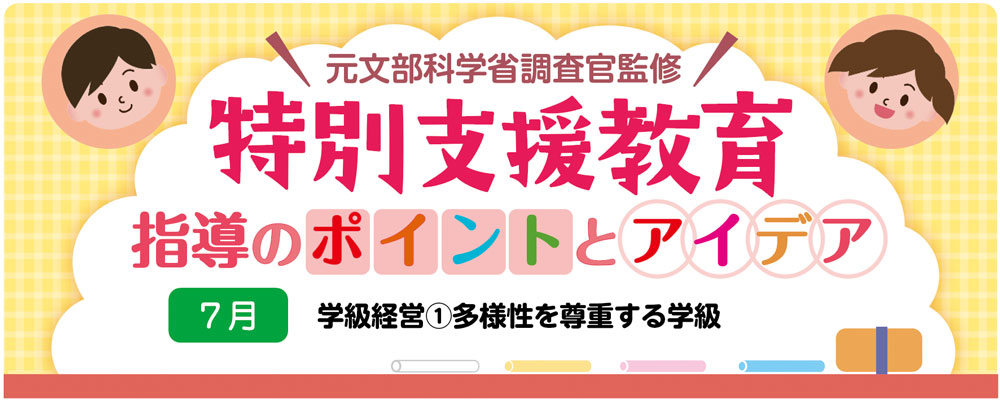
元文部科学省調査官監修による、特別支援教育の指導のポイントとアイデアです。今回は、〈学級経営①「多様性を尊重する学級」〉を紹介します。学級担任ができる多様性を尊重する学級づくりの手立ての具体的な例をお届けします。配慮が必要な子供と周囲の子供たちをつなぐヒントにしてください。
執筆/熊本市教育委員会総合支援課指導主事・山田光太郎
監修/元文部科学省特別支援教育調査官・加藤典子
白百合女子大学人間総合学部初等教育学科教授・山中ともえ
目次
特別支援教育 年間執筆計画
04月 児童理解①児童の状態の把握
05月 児童理解②個別の教育支援計画と個別指導計画の作成・活用
06月 児童理解③児童への具体的な対応
07月 学級経営①多様性を尊重する学級
08月 学級経営②集団指導と個別指導
09月 学級経営③多様性を尊重する学級
10月 授業づくり①ユニバーサルデザインの考え方を取り入れた授業
11月 授業づくり②合理的配慮についての工夫
12月 授業づくり③ICTの活用
01月 連携①保護者との関係づくり
02月 連携②校内連携
03月 連携③関係機関の活用
【解説編】多様性を尊重する学級づくり
多様性を尊重する学級づくりには、特別支援教育の視点が欠かせません。教師自身が子供の言動の背景要因に眼差しを向けること、子供同士が困っていることを素直に言えること、お互いを認め合いみんなで乗り越えられる学級づくりを目指していくことが大切です。
1 言動の背景要因に目を向け、肯定的な眼差しを向ける
多様性を尊重する学級をつくるためには、私たち教師が、子供の言動の背景要因に目を向けることから始めます。つい手が出てしまう、暴言を吐いてしまうことがある、といった子供の言動の背景には、そうせざるを得ない理由があります。
暴言を吐いてしまう子の背景要因には、例えば、「悔しい」とか「もどかしい」といった適切な表現方法が育っていない、身に付けた表現方法を焦りや混乱のためにうまく使えないといったことが考えられます。前後の経緯を丁寧に聞き取って、「悔しかったね」「もどかしいね」とその子供のそのときの気持ちを代弁したうえで、「次は友達や先生にそう伝えられるといいね」と伝えていきます。そんな関わりを繰り返すことで、その子供が同じような場面に出合ったとき、気持ちをうまく伝えて仲直りができたり、折り合いをつけたりすることができたら、一見当たり前に見える子供の言動に、「すごいね」と肯定的な言葉がけをすることができると思います。
子供たちが、このような教師の肯定的な関わりをモデルにすることで、多様性を尊重し合う学級に向かっていきます。
2 困っていることを素直に言い合える学級に
自己肯定感には2つの側面があります。できる自分に自信があることと、もう1つは、できないことがあるけれどもそれも含めて自分を認められることです。
自己肯定感がつぶれてしまうと、その子供にとって、学級が居心地の悪い、居場所のないものになってしまいます。できないことや苦手なことがあっても、学級の中で困っていることを言い合える学級は、自分の居場所が感じられ自分らしさを大切にすることができ、それが多様性の尊重につながっていきます。
多様性が尊重され、支持的風土のある学級づくりを目指すためには、子供たちが、困っていることをやり過ごしたり、カモフラージュしたりするのではなく、困りごとに対して周囲に援助を求めながら解決していく経験の積み重ねが必要です。
授業ではよく「できる人?」「分かる人?」と教師が挙手を求めることがあります。悪いことではありませんが、「分からない」ことを大切にすることも必要です。
困っていることを素直に言い合える発問の例として、
・「今困ってるーって人?」
・「ちょっと友達に手伝ってほしいよーって人?」
・「自信ないって、自信をもって言える人?」
といったように、いろんなバリエーションで困りを出せるようにし、困りをきっかけに教師のファシリテートで授業を深めていくことが、授業を通した学級づくりにつながります。
困っていることを言えたことが、課題の解決や成功体験につながったという経験が積み重なっていくと、ヘルプを出せてよかった、分からないことやできないことがあってもいいという自己肯定感の高まりにつながっていきます。

3 みんなで乗り越えられる学級に育てること
問題のない学級がよい学級というわけではありません。問題が起きたときにみんなで解決できる(解決する術がある)学級が、多様性を尊重する学級です。
担任の教師が子供の話をよく聞いているクラスはいじめが起きにくいものです。
担任の教師が共感的に話を聞くことで、子供は肯定された気持ちになるからです。
担任の教師が肯定的だと、子供は主体的に行動するようになります。様々な物事への興味や関心が広がり、自分から何かをやろうとする意欲や活力が高まるからです。
また、安心してトライアルアンドエラーを繰り返すようになります。トライアルアンドエラーの経験の積み重ねが、問題が起きたときにみんなで解決する学級づくりにつながります。
担任の教師が穏やかで話を丁寧に、共感的に聞いてくれること、これが、みんなで乗り越えられる、多様性が尊重される学級づくりのポイントとなります。


