「学級経営」アップデート|「個の思い」を大切にしながら「つながり」を支える技【中野裕己の授業技術アップデート13】

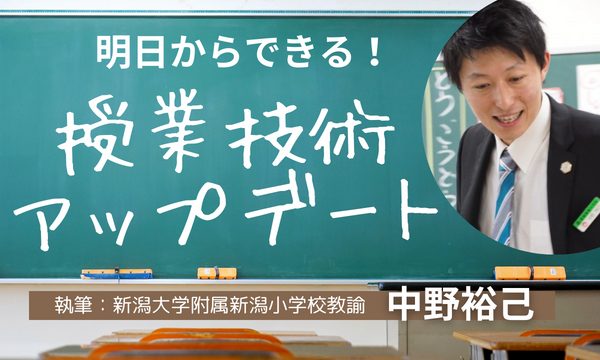
『授業はタイミングが9割』『対話型国語授業のつくりかた』の著者で、国語科、対話指導、ICT活用の研究を精力的に進める中野裕己先生による連載です。国語科の授業にとどまらず、“明日から”できて“ずっと”役に立つ授業の技を、多岐にわたってお届けします。
第13回目のテーマは、《学級経営のアップデート》です。
執筆/新潟大学附属新潟小学校教諭・中野裕己
目次
「学級経営」の光と影
連載第13回目となりました。新潟大学附属新潟小学校の中野裕己(なかの・ゆうき)です。
ゴールデンウィークが終わり、6月に入りますね。新しい学年に慣れてきた子供たち、そろそろ「その子らしさ」がはっきりと表れ出す時期だと思います。そんな時期だからこそ、今回は学級経営のアップデートを提案します。
学級経営とは、具体的にどのような事柄を指すのでしょうか。「経営」という言葉を辞書で調べると、次のような意味が示されていました。
1.事業を営むこと。また、その運営のための仕組み。
2.規模を定め、工夫をこらして物事を行うこと。
つまり学級経営とは、学級を運営するための仕組みをつくったり、工夫をこらして学級に関わる物事を行ったりすることを指していると捉えられます。
この学級経営の意義は、仕組みや工夫を適切に運用することで、子供たちが快適に集団生活を送ることができるようにすることです。
具体的には、次のような仕組みや工夫が考えられるでしょう。
・朝の会、帰りの会
・給食配膳
・日直・当番活動
・係活動
・生活のきまり
・学習のきまり
・トラブル対応
私も初任の時代には、上掲のような仕組みや工夫を、先輩の先生や書籍からたくさん学びました。それらは、今でもとても役立っています。
一方で、私にとってどうしてもなじまない学級経営があります。それは、「子供たちが学級をつくる」ということを強調した学級経営です。
もちろん前述した仕組みや工夫について、教師が一方的に決めてしまうのではなく、子供の意見を聞きながら共有していくことは大切です。しかしながら、例えば「どんな学級を目指したい?」「理想の学級になるために、何が足りないかな?」などといった、子供を積極的に学級に向き合わせるような学級経営は、得意ではありません。このことは、自分が小学校時代に、そのような集団活動があまり得意でなかったことに起因します。
当時、「自分と自分の仲良しの友達が元気で過ごせたらいいな」と考えていた私は、「学級」という単位で考えることが前提になった時点で、なんだか心がぎゅーっとなってしまう子供でした。教師になった今も、「私のような子供がいるかもしれない」と考えると、「どんな学級を目指したい?」「理想の学級になるために、何が足りないかな?」とはなかなか言葉にできません。
目指したい学級像を明確にさせたり、それに足りない部分を考察させたりすることは、自治的な学級集団を育てるために必要なのかもしれません。それでも私は、自治的な学級集団に埋没してしまった「個の思い」のほうが気になってしまいます(誤解のないように…自治的な学級集団を育てながら、「個の思い」を丁寧に尊重される実践者の方もたくさんいらっしゃることを付け加えておきます)。
ここからは、そんな私が学級で大切にしていることを2つ紹介します。
「自己発揮」を支える
まず大切にしていることは、一人一人の自己発揮を支えることです。
ここでの自己発揮とは、その人らしさが周囲によい影響をもたらす形で表れたものを指します。自己発揮には、子供同士の目に触れやすいものと、触れにくいものがあります。
<子供同士の目に触れやすい>
・積極的に自分の考えを主張できる
・運動が好きで、得意である
・漢字や計算など、個別的なスキルをよく習熟している
・ひょうきんで、いつも面白いことを話す
<子供同士の目に触れにくい>
・落ちているものを拾う
・係活動や当番活動などを、欠かさずに行う
・提出物を出すときに、ほかの人のものも含めて整えて出す
・友達の考えを柔軟に取り入れる
教師がやるべきことは、子供同士の目に触れにくい自己発揮を見取り、フィードバックすることです。例えば、落ちているものを拾う子供の姿を見付けたら、「拾ってくれてありがとう」と伝えるのです。簡単なようですが、アンテナを高くしておかないと見逃してしまうこともあります。さらに、その子供の実態に応じては、朝の会や帰りの会など学級全体の場で紹介することもよいでしょう。
また、子供の目に触れやすい自己発揮についても、時にはその価値を語ることが大切です。例えば、いつも面白いことを話す子供について「〇〇さんが話してくれると、教室が明るくなるね。先生はうれしいよ」などと、率直に思いを語ることもよいでしょう。
このようにして、どの子供も安心して自己発揮できるように働きかけるのです。この教師の働きかけは、繰り返していくと子供にも伝播していきます。教師のように声はかけなくとも、「あの人ってこんな素敵なところがあるんだ」と認められるようになっていくのです。すると、子供の心理的安全性が高まり、その子供らしい姿が教室にあふれるようになっていきます。

