「走れメロス」についてディスカッション 【「高校につながる英・数・国」の授業づくり #34】
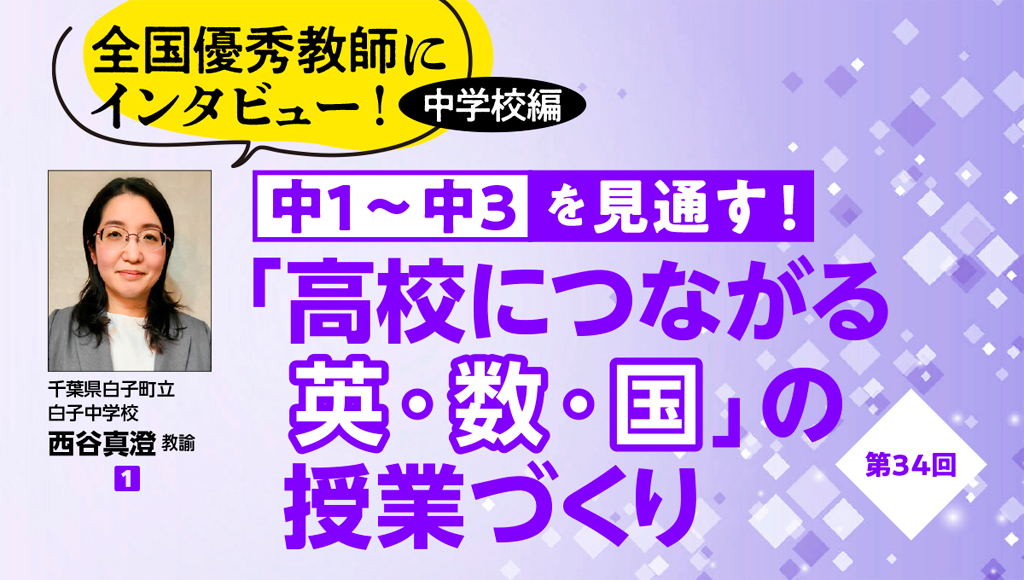
千葉県には、各教科等の指導において卓越した技能と専門性を発揮している教員を「授業づくりコーディネーター」として認定する制度があります。そこで今回からは、その国語の「授業づくりコーディネーター」である、白子町立白子中学校の西谷真澄教諭に、ご自身の単元・授業づくりの考え方や、その考え方を象徴する単元の実践事例について聞いていきます。
1回目となる今回は、西谷教諭の単元・授業づくりの考え方を象徴する、「走れメロス」の単元の実践事例について聞いていくことにしましょう。

西谷真澄教諭
目次
本好きになるための第一歩を踏み出すための単元
まず、この単元を工夫しようと考えた意図について、西谷教諭は次のように説明してくれました。
「教科書教材である『走れメロス』の単元では、発問を工夫して、『走れメロス』についてディスカッションをしていくような単元・授業もおもしろいと思います。ただ、(読書をする子供が少ない現代の)子供たちの実態も踏まえ、せっかくなので多くの本を読んでみる読書につなげたいと考え、この単元を工夫しました。
この単元では、まず『メロスは本当にヒーローなのか読んでみよう』と投げかけ、子供たちそれぞれが選んだ他の英雄物語と比較することで学習を展開していきます。メロスが『英雄か?』、と問うような読み方に異論があることは承知しています。しかし、そのような視点をもつことで、物語を比較しながら読んでいきたいと考えました。
単元自体は2学期に行いたかったので、事前の夏休み前に、英雄物語やヒーローものと呼ばれるような物語をたくさん集めてきておいて、その中から好きな本を選ばせて読ませていきました。ちょうど戦争が起こった時期でもあったため、『自己犠牲がすばらしい』というようにならないように、かつ生々しくならないように、基本的にはフィクションで、ファンタジーや神話など、多様なジャンルのものを用意しておきました。その中から子供たちに複数を手に取らせ、夏休み時期から読み比べさせておき、最終的にその中から自分たちが選んだ物語の登場人物とメロスを比較しながら、ヒーロー性について考えさせていったのです。
当然、子供たちは、メロスと比べる本を決定するまでにいろいろな本を読んで、『ああ、これじゃないな』とか、『メロスと比べるには少し弱いな』と考えていくので、読んでいる途中で選ばれなかった本も出てきます。そうやって、多い子供だと5〜6冊の本を読んで、最終的にメロスと比較する物語を決めていきました。
そのように選ばせていくと、子供たちはたくさん拾い出した本の中から一部だけを読んで、よいものだけを選んでいくわけです。そうすることで、子供たちの本の読み方が変わったなと感じました。これは余談になりますが、本が好きな人は書店や図書館で、本を手に取っただけで、あるいはパラッとめくっただけで、『この本はおもしろそう』『自分に合いそう』と感じる嗅覚のようなものをもっていると思います。
一方で、本を読み慣れない子供たちは、本を選んで1度読み始めたら、最後までそれを読み続けなければならないと思っていることがあります。しかし、こうした学習をすることで、合うものを選ぶ感覚や合わないものは途中でやめてもよいということに気付いていくのです」
そのような、本に慣れる、本好きになるための第一歩を踏み出すための単元ということができるのかもしれません。

