学級会でよりよい合意形成を目指す 提案理由の設定法【自治的な活動を促す 学級経営の極意Ⅱ⑤】


子供たちが自治的な活動を行えるようにするためには、教師はどのような指導をしていけばよいのでしょうか。学級経営・特別活動を長年、研究・実践してきた稲垣孝章先生が、全15回のテーマ別に特別活動の本流を踏まえて、学級活動の基礎基本を解説します。第5回は、学級会の提案理由について解説します。
執筆/埼玉県東松山市教育委員会教育長職務代理者
城西国際大学兼任講師
日本女子大学非常勤講師・稲垣孝章
学級活動(1)学級会での話合いの中核は「提案理由」です。「提案理由」は、学級会の話合いの目的を示すものであり、合意形成の際の判断基準にもなるものです。何のために話し合うのか、どのような活動を目指して話し合うのかという話合いの重要な視点ということができます。
そこで、学級会の提案理由を設定するにあたって、3つのキーワード「提案理由に盛り込む内容」「提案理由の提示方法」「提案理由とめあての関連」でチェックしてみましょう。
目次
CHECK① 提案理由に盛り込む内容
学級会の話合いは、学級生活の充実と向上を目指し、学級生活の諸問題を見いだして全員でその解決に向かって実践活動を展開するために行います。その話合いの目的を示し、話合いの判断基準となるのが提案理由です。ゆえに、提案理由に取り込む内容は、きわめて重要です。
基本的には、「①現状、②課題、③解決策」の視点で次のように設定していきます。
「現状と課題点、解決策」を盛り込みます
提案理由には、次のような内容を盛り込んで話合いの目的を明確にします。
①現状(今は、~のように仲のよいクラスだと思います)
②課題(でも、~仲のよい友達がグループ化していることが調査で分かります)
③解決策(そこで、仲よし集会を開いてもっと仲よくできるようにしたいと思って、議題を提案しました)
提案理由を明確にし、全員が理解できるようにすることが、適切な合意形成を図ることにつながります。提案理由を大切にした学級会を行っていきましょう。
CHECK② 提案理由の提示方法
提案理由の文言ができたら、次はどのようにその内容を学級会で提示するかを考えます。提案理由は、話合いの目的を示すものなので、どうしても長い文章になってしまいます。そこで、提案理由を発表する際には、その長い文章を読むだけでなく、視覚的にも分かりやすいものにすることが求められます。その際、学年の発達段階や学級の実態に応じた提示方法を工夫していきましょう。
発達段階に応じた提示方法を工夫します
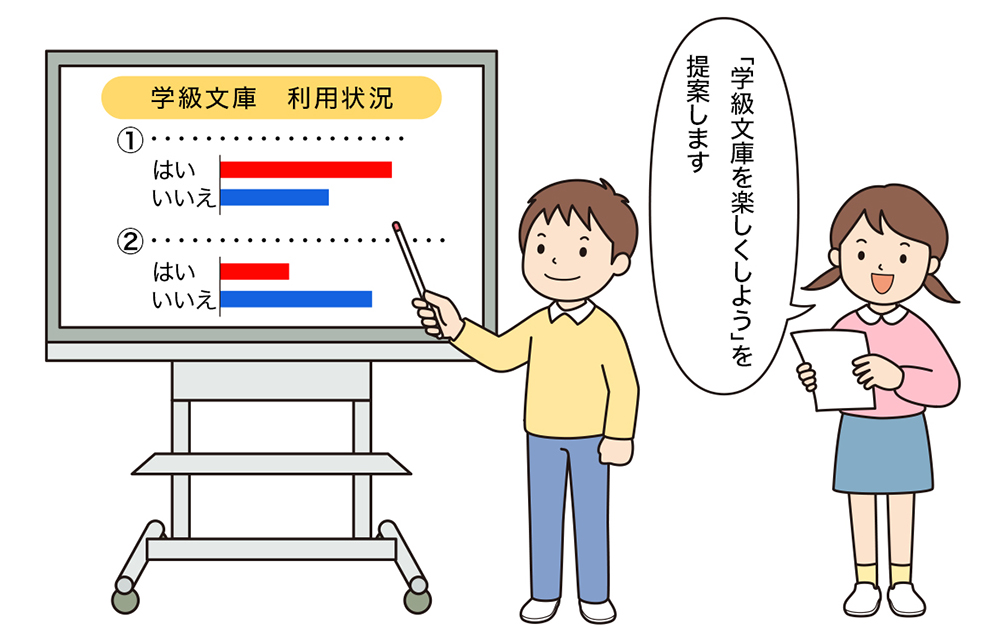
例えば、提案理由の提示の仕方には、次のような方法が考えられます。
「低学年」では、現状と課題と解決策の3つの場面を紙芝居風の絵に描き、提案者が説明するという方法、「中学年」であれば、3つの場面に即してロールプレイングを活用して役割演技で説明する方法、「高学年」であれば、アンケート調査等を活用した統計資料で説明する方法などが実践されています。視覚的にも分かりやすくなるように提案理由を再確認して、学級会の話合いに臨むと合意形成をしやすくなります。
CHECK③ 提案理由とめあての関連
学級会の話合いでは、「めあて」を設定することがあります。ときに、「1人1回発表しよう」といった話合いの技能に関することだけを取り上げる実践があります。技能面のめあても必要に応じて取り上げることは考えられますが、本来は話合いの内容に関する「めあて」を取り上げることが基本です。その内容は、次のように提案理由を凝縮したものとして考えていきましょう。
提案理由を凝縮してめあてを設定します
提案理由は、学級会の話合いの目的であり、合意形成の判断基準です。例えば、高学年であれば「今のクラスは、みんなとても仲がよいと思います。でも、アンケートでは、特定の人と関わることが多く、友人関係が固定化していることが分かります。そこで、誰もが関わり合い、友人関係を広げて、さらに仲のよいクラスになるようにしたいと思って仲よし集会を提案しました」との提案理由であれば、「誰もが関わり合い、友人関係を広げることのできる内容を決めよう」といっためあてを設定するという考え方です。
提案理由を明確にし、めあてを簡潔に提示して、よりよい合意形成のできる学級会の話合いを支援していきましょう。
イラスト/池和子(イラストメーカーズ)

