小4特別活動「これからよろしくね 集会をしよう」指導アイデア
関連タグ

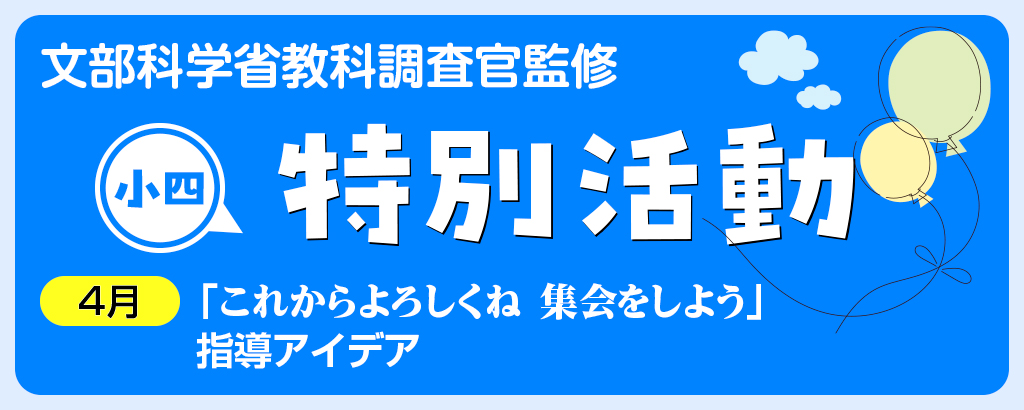
文部科学省教科調査官監修による、小4特別活動の指導アイデアです。4月は、学級活動(1)「これからよろしくね 集会をしよう」の実践を紹介します。高学年の仲間入りをした4年生。仲間意識が芽生えるこの時期に、みんなで「1年間協力して楽しく生活しよう」という思いを共有し、心理的な距離を縮めることを目指します。
執筆/熊本県公立小学校教諭・有内文香
監修/文部科学省教科調査官・和久井伸彦
尚絅大学教授・平野 修
目次
年間執筆計画
年間執筆計画はこちらをクリック
4月 学級活動(1) これからよろしくね 集会をしよう
5月 学級活動(3) ア 4年生になって
6月 学級活動(2) ウ じょうぶな歯
7月 学級活動(3) ア もうすぐ夏休み
9月 学級活動(2) イ 言葉を見直して笑顔の学級へ
10月 学級活動(1) 学級室内運動会をしよう
11月 学級活動(1) 係発表会をしよう
12月 学級活動(3) イ 落とそう、1年のよごれ
1月 学級活動(1) 給食の先生に感謝の気持ちを伝えよう(給食週間)
2月 学級活動(1) 10歳のパーティーをしよう
3月 学級活動(3) ア 高学年に向けて
学級活動(1)の指導について
学級活動(1)の授業では、自分たちの学級や学校の生活をよりよくするために、子供たちが自ら生活上の課題を見いだし、解決するために話し合い、合意形成したことに協力して取り組むことを通して自治的能力を育てます。実践後に一連の活動を振り返り、次の課題解決や新たな活動に生かすようにします。

