小学校の教室で行うアンガーマネジメント教育(低学年編) ~怒りの感情を知り、上手に付き合う~

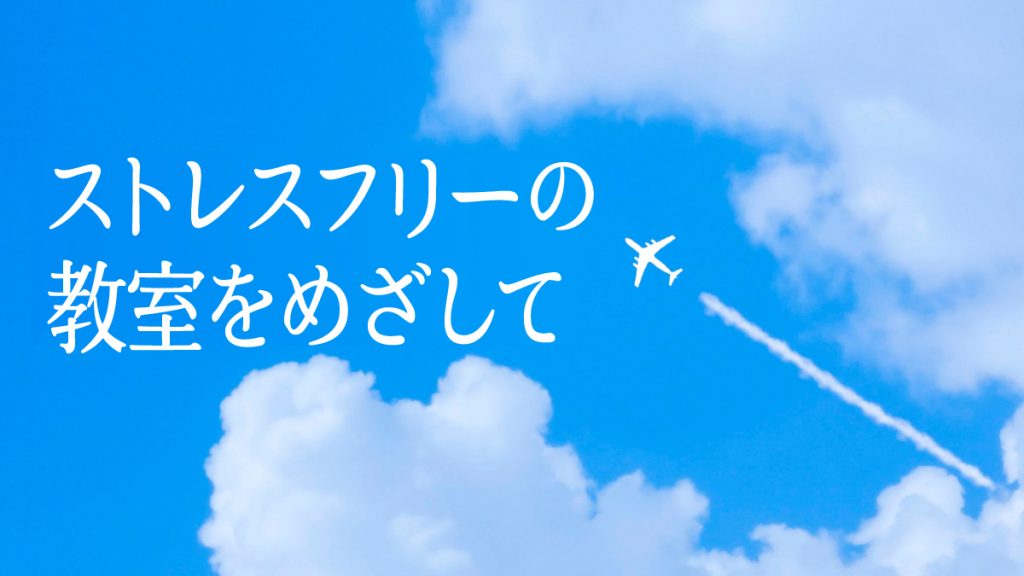
子どもたちは日々の生活の中で、思い通りにならない場面に遭遇し、怒りの感情を抱くことがあります。しかし、低学年の子どもたちは感情のコントロールが未熟であり、怒りを適切に表現するための方法を学ぶことが必要です。今回は、小学校低学年を対象にしたアンガーマネジメント教育の指導アイディアについてまとめました。
【連載】ストレスフリーの教室をめざして #22
執筆/埼玉県公立小学校教諭・春日智稀
目次
低学年向けアンガーマネジメント教育のポイント
低学年のアンガーマネジメント教育では、次のようなポイントを押さえましょう。
①怒りという感情がどういうものかを知る。
②怒りを感じたときに言葉で表現できるようにする。
③怒りを鎮める簡単な方法を身につける。
これらを通じて、子どもたちが自分の感情を大切にしつつ、他者との関係を円滑に築ける力を養っていきます。
指導アイディア①「感情カードゲームで遊ぼう!」
<目的>
子どもたちが感情の名前を覚え、自分の気持ちを言葉で表現する力を育てる。
<準備物>
・感情カード:おこる、かなしい、うれしい、びっくり、こわいなどの感情について、その表情が描かれたイラストのカードを用意します(感情ごとに複数枚)。
<導入>
・先生の説明:
「今日は、いろいろな気持ちについて考えてみたいと思います。みなさんは、どんなときにどんな気持ちになるでしょうか。みんなでゲームをしながら考えてみましょう。」
<展開>
ゲーム① 感情当てクイズ
【ルール】
① 先生がランダムに感情カードを1枚引いて、子どもたちに見せます。
②「この顔はどんな気持ちでしょう?」と問いかけ、子どもたちが手を挙げて答えます。
(例:「かなしい!」)
③ 正解した子には「どうしてそう思ったの?」と理由を尋ねます。
(例:「口がへの字だからかなしいと思ったよ」)
④ 同じ感情カードを見せながら、「この気持ちになるのはどんなとき?」と具体的な場面を考えさせます。
(例:「友達に遊んでもらえなかったとき」)
【ポイント】
まずは、表情を頼りにして感情に名前をつけていきます。そして、その感情を日常場面に結び付けていきます。日常場面は、なるべきたくさんの考えを引き出しましょう。感情は同じでも、場面は異なることを理解することができます。
ゲーム② 感情ジェスチャーゲーム
【ルール】
① グループを作ります。
② 一人の子どもが感情カードを引き、その感情を表すジェスチャーを行います。
③ 他の子どもたちが、そのジェスチャーがどの感情かを当てます。
(例:「悲しい」の場合、肩を落として泣くふりをする。「怒り」の場合、腕を組んで足をドンドン踏みならす)
【ポイント】
ジェスチャーゲームですので、声を出してはいけません。ジェスチャーは、多様な表現を認めましょう。感情は同じでも、人によって表現方法が異なることを理解することができます。
<終末>
・「今日の感想を教えてください」
・「今日はみんなの気持ちについてゲームをしながら考えました。どの気持ちも、とっても大切なものです。ときどき、今自分はどんな気持ちかな、と考えてみてください」

指導アイディア②「怒りを鎮める方法を学ぶ」
<目的>
子どもたちが怒りを感じたとき、適切な方法で気持ちを落ち着かせるスキルを学ぶ。
怒りに任せた行動を防ぎ、冷静な判断ができるようにする。
<準備物>
・「みんなの落ち着きリスト」作成のための模造紙
<導入>
・先生の説明:
「みんな、イライラしたり怒ったりすることがあると思います。今日は、その気持ちをどうやったら落ち着かせられるか、一緒に考えてみましょう」
※身近な例を挙げて、「怒ったときにどうなるか」を子どもたちに問いかけます。
(例:「お友だちとけんかしたとき、みんなの心や体はどうなりますか?」)
<展開>
活動① 深呼吸を学ぶ
「怒ったときには、体がドキドキしたり、息が速くなったりすることがあります。そんなときは、深呼吸をすると気持ちが落ち着きます。」
① 背筋を伸ばして座る。
②「鼻からゆっくり息を吸って、1、2、3…」。
③「口からゆっくり息を吐いて、1、2、3、4、5…」。
繰り返し練習し、「気持ちが落ち着いた!」と感じられるようになるまで練習します。
※「息を吸うときに、好きな匂い(花やフルーツなど)を思い浮かべてみよう」と伝えると楽しく活動できます。
<終末>
・「今日の感想を教えてください。」
・「今日はみんなの気持ちについてゲームをしながら考えました。どの気持ちも、とっても大切なものです。ときどき、今自分はどんな気持ちかな、と考えてみてください」
【ポイント】
・リラックスして活動できるよう、教室の環境(換気、明るさなど)を整えましょう。
活動② 数を数える練習
「怒ったときは、すぐに動いたり話したりしないで、心の中で1から6まで数えてみましょう。それだけで少し気持ちが落ち着きます」
①子どもたちに、怒ったときのイメージをさせながら「1、2、3……」とゆっくり心の中で数える練習をします。
②「もっと落ち着きたいときは、10まで数えてみましょう」と伝えます。
【ポイント】
・はじめは、みんなで声を出しながら数えてもOKです。
活動③「落ち着きリスト」を作ろう
「怒ったときに、自分を落ち着かせる方法をリストにしておくと便利です。一緒に考えてみましょう!」
①「みんなはどんなときに怒るかな?」と問いかけて、例を出します。
(「順番を飛ばされた」「おもちゃを取られた」など)
②「そんなときに、どうやったら気持ちを落ち着かせられるかな?」を子どもたちに考えさせます。
③出てきたアイディアを模造紙にまとめて、「みんなの落ち着きリスト」を作成する。
(深呼吸をする・落ち着く場所に移動する・好きなことを思い出すなど)
<ロールプレイ>
簡単な怒りの場面を設定し、「どうやって落ち着かせるか」を練習します。
①怒りの場面を設定し、説明する。
(例「友だちに順番を飛ばされたらどうする?」)
②子どもたちが「落ち着きリスト」から方法を選び、実践する。
【ポイント】
・「物を壊す」などの破壊的な行動を言う子がいます。正面から否定せずに、「壊さなくても済む方法はないかな?」と寄り添いながら考えましょう。
※怒ることは悪いことではなく、怒りをうまくコントロールすることが大切であることを伝えましょう。
【アドバイス】
①ポジティブなフィードバックを心掛ける
子どもたちが正しく実践できたときには、しっかり褒めてあげましょう。
②実践しやすい方法に限定する
子どもたちが日常で試せる簡単な方法を取り上げましょう。
③リストを見える場所に掲示する
作成した「落ち着きリスト」は、いつでも確認できる場所に掲示しましょう。

