【特別支援教育】児童理解①「児童の状態の把握」
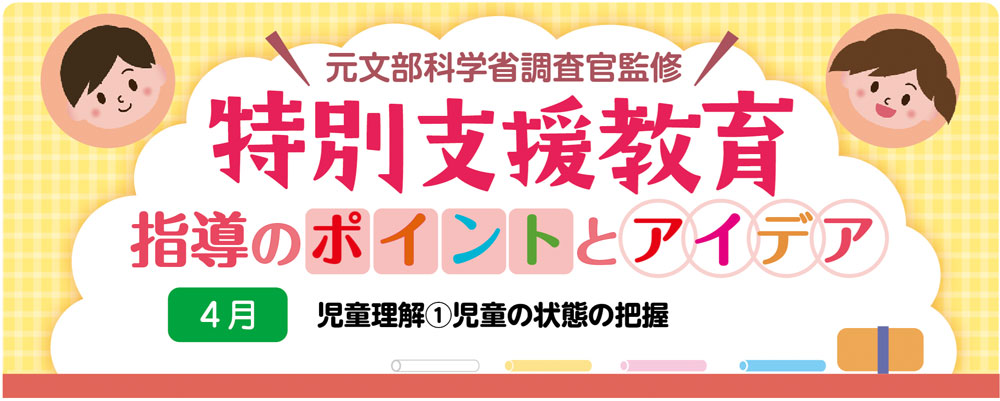
元文部科学省調査官監修による、特別支援教育の指導のポイントとアイデアです。今回は、〈児童理解①「児童の状態の把握」〉を紹介します。
4月に子供たちと新たな立場で出会うことは、大人も子供も期待や不安が入り混じるものです。年度当初の1週間は、知らぬ間に肩の力が入ってしまっているのではないでしょうか。児童理解は簡単なことではありませんが、児童理解なくして教員の仕事は成り立ちません。学校は子供たちが主役です。多様な子供たちをどのように理解していけばよいのか、一緒に考えていきましょう。
執筆/東京都公立小学校教諭・久保田奈美
監修/元文部科学省特別支援教育調査官・加藤典子
全日本特別支援教育研究連盟研究部長・山中ともえ
目次
特別支援教育 年間執筆計画
04月 児童理解①児童の状態の把握
05月 児童理解②個別の教育支援計画や個別の指導計画の作成
06月 児童理解③児童への対応
07月 学級経営①学級内での人間関係づくり
08月 学級経営②集団指導と個別指導
09月 学級経営③多様性を尊重する学級
10月 授業づくり①ユニバーサルデザインの考え方を取り入れた授業
11月 授業づくり②合理的配慮についての工夫
12月 授業づくり③ICTの活用
01月 連携①保護者との関係づくり
02月 連携②校内連携
03月 連携③関係機関の活用
【解説編】 子供の状態の把握
子供たち一人一人が自分らしく学び成長していくことができるよう、私たち教員は授業づくりを工夫するとともに、子供の学びや生活を支援する伴走者としての役割を果たすことが求められています。そのために必要となる情報を、学校生活全体を通して把握していくことが大切です。
学校生活全体を通して子供の実態を把握する視点や方法について解説します。

自分らしく成長することを支援するための状態の把握
どの子供も、自分らしく学び、自分らしく成長していくことを私たち教員は支援しています。では、その子らしく学ぶとはどのような学び方のことなのか。学びは、学習だけではありません。生活に関することも友達関係に関することも、すべて必要な学びです。
子供の実態を把握する目的は、支援に必要な情報を得ることです。決して、把握して仕分けすることではありません。子供がどのような状態なのかを把握し、教員がその子についてよく理解することで、学び方をどのように支援すればよいのかが分かります。
子供の状態を把握するといっても、学級には、様々な状態の子供たちがいるということが前提となります。まずは、違いや多様性を認める姿勢こそが、子供たちにとって大切です。先生自身に、子供たちは一様であるという思い込みがあり、他の子供とは少し異なる面に戸惑いを感じてしまうと、周囲の子供も敏感に反応してしまいます。子供たち一人一人が大切な存在であるという前提で、状態の把握を進めましょう。
日常の様子を観察する方法と、検査等を活用した方法
子供たちの実態を把握する方法として、様々な場面の行動観察を基本に行う方法と、標準化された心理検査やチェックリストを用いる方法があります。1人の子供に対する多面的なエピソードや意見は大切です。
1 行動観察等による実態把握
学校は様々な子供が通い、毎日いろいろなことが起きます。それらを丁寧に見取ることで、対象となる子供の支援に必要なヒントが見付かります。好きなことが分かれば、子供がチャレンジしやすい改善の近道が見えるかもしれません。また、なぜ嫌いなのかが分かれば、どこのハードルを下げれば取り組みやすいのか、意欲向上のキーポイントが見付かるかもしれません。
子供の生活を知っている人がもつ情報は膨大です。気になる行動は、起こったことの前後の出来事も正確に把握することで、その行動の意味が分かってきます。様々な場面を通して行動観察を行い、記録し、整理するようにします。
担任1人の見方だけではなく、保護者からの情報提供、関係している他の先生方からの情報など、 日頃から関わっている複数の関係者からの視点は大切です。日常の中で見過ごしていた場面に気付くことにもつながります。
また、学校全体を把握している特別支援教育コーディネーターに積極的に相談して子供を見てもらったり、校内で行われる校内委員会で話し合い、担任が知らない場面での情報をもらったりして、可能な限り複数の人から情報を得るようにします。
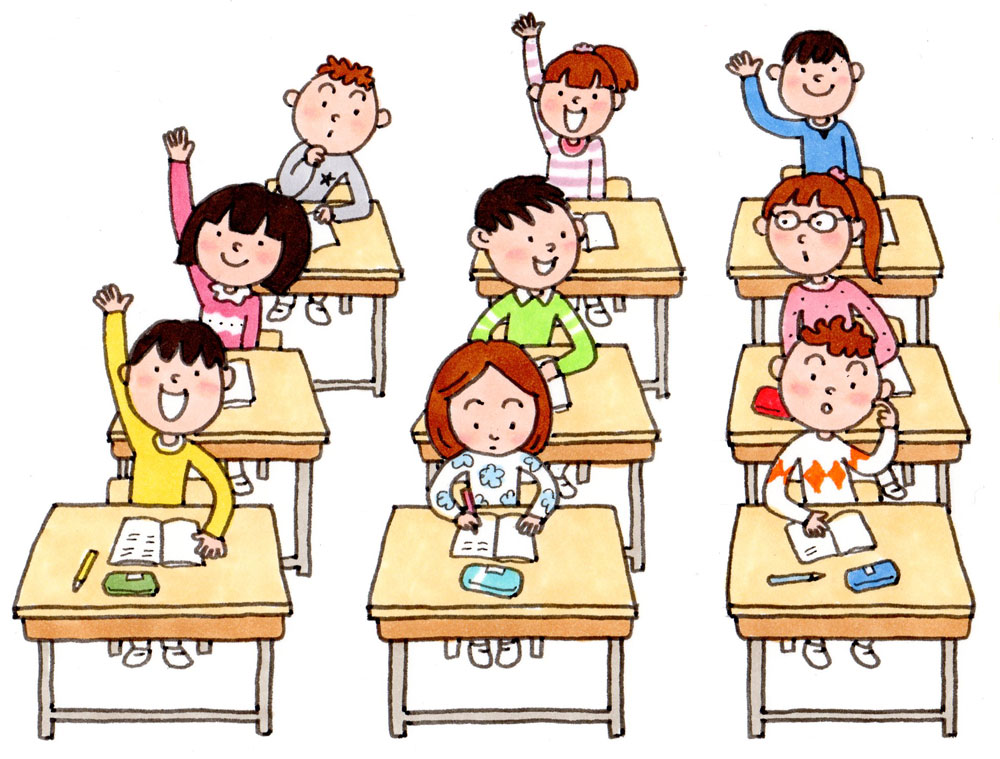
2 検査等による実態把握
子供の実態把握の1つとして、専門家が行う田中ビネーやWISC-Ⅳ(WISC-Ⅴに移行しつつある)などがよく使用されています。これらの検査は専門家が行うものであり、特別支援教育コーディネーターや担任はその検査で分析された結果を理解するようにします。
心理検査の情報があれば、その結果から、言語面、認知面、処理速度等の得意と苦手を知ることができます。その結果をどのように指導に生かすかは、心理を専門とするスクールカウンセラーや巡回相談の心理士等と連携を取って進めるとよいでしょう。
その他、担任が使えるものとしては、各自治体などで作成されている学習習熟度テストや学習面・行動面におけるチェックリストなど、また、標準化されている読み書きスクリーニング検査や音読検査などがあります。
収集した情報を3つのカテゴリーに整理
収集した情報を整理するときは、「学習面」「生活面」「社会性」の3つのカテゴリーで整理しておくと、個別の指導計画に反映することもできます。
「学習面」は、学力、いわゆる勉強に関することです。国語は苦手だけれど算数は得意など、得意な面と苦手な面を把握します。このとき、いつもは意欲が少ない国語だけれど、あの授業のときは生き生きしていたなどの「例外」をぜひ見付けてみてください。「例外」には重要なヒントが隠れています。
「生活面」は、活動中の行動も大切です。活動と活動の合間の時間をイメージすると、行動を把握しやすいものです。朝の時間や休み時間、給食時間や体育の着替えなど、学校生活の中では、活動と活動の合間に、子供たちが自分で考えて過ごしている時間が多くあります。家庭生活も含めた生活全般の様子が気になるかもしれませんし、手先の不器用さや段取りの苦手さが見えるかもしれません。
「社会性」は、その子供の「友達関係」や「コミュニケーション」などを思い浮かべます。友達関係ではどのような困りごとを感じているでしょうか。状況把握の苦手さから友達とのコミュニケーションを勘違いしたり過度に考え過ぎたりして、攻撃的に捉えてしまい、休み時間に喧嘩になることがあるかもしれません。また、うまく自分の気持ちを伝えられず、遊びの仲間に入れていないかもしれません。集団生活の場面や休み時間の様子をよく見てみましょう。

