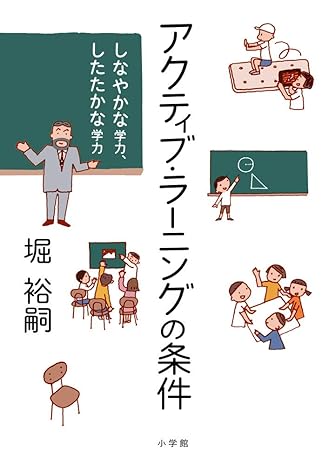【連載】堀 裕嗣 なら、ここまでやる! 国語科の教材研究と授業デザイン ♯4 分析・解析してはいけない教材ジャンル~「文脈」を読む力について・番外編~

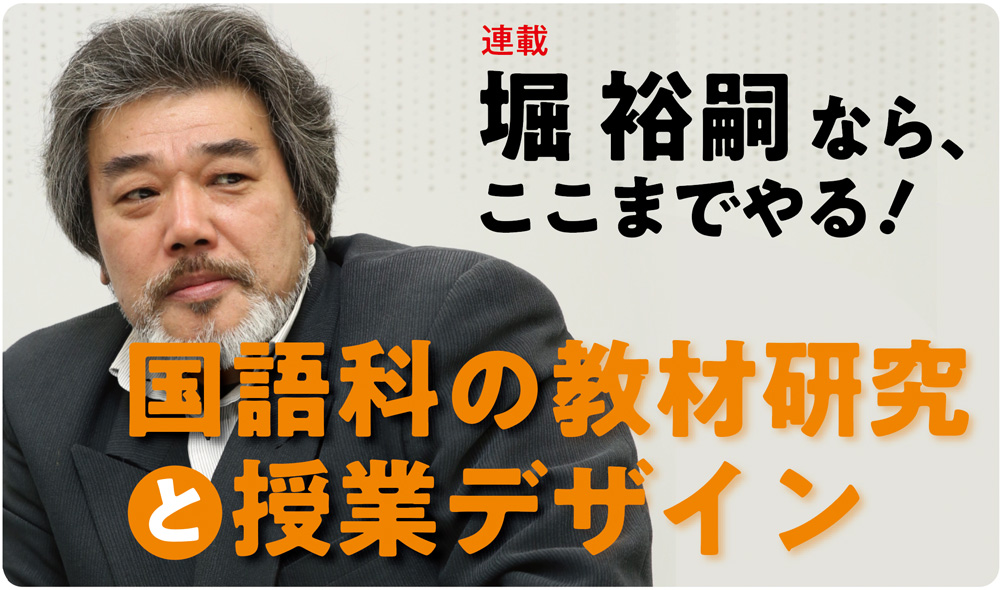
国語教師としての「倫理」に照らして、分析・解析すべきでない教材が存在する、と筆者は言います。今回の原稿は、筆者が大切な友人を喪ったわずか4日後から2日間にわたり執筆されました。なぜ、人は「書く」のか。文学とは、何のためにあるのか。その答えの一端に触れることができる第4回です。
目次
1.2025年1月23日(木)07:52
先日、個人的に大きな出来事があり、それを昇華しないことにはどうにも前に進めそうにないので、今回は、ほんとうは6回目か7回目あたりに書くはずだった内容を書くことにする。「文脈を読む」ということを詳しく書いた後に、最後に「但し書き」のような形で付け加える予定だった内容を先に書くことにしたい。
渡部陽介くんが逝った。1月23日、木曜日。7:52のことだ。48歳だった。それまでまったく元気だった彼が悪い菌に冒され、意識を失い、瞬く間に逝ってしまった。
いきなり「渡部陽介くん」と言われても、多くの読者には「?」に違いない。逆に私とリアルな付き合いがあって、北海道のセミナーにも来たことがあるという読者には、渡部陽介という人物が私にとってどれだけ重要な人間であったかということが、おそらく思い浮かぶはずだ。札幌で行われる私の道徳セミナーのほぼすべてに、渡部は参加していた(ここからは敬称を略す)。
渡部は私にとって、セミナー上、研究上の付き合いだけではない、まさに「友人」だった。ここ十年以上、セミナーの懇親会や個人的な飲み会で、年に20回程度は酒席をともにしていた。しかも、そのうち7~8回程度は二人で吞んでいた。コロナ禍においてさえ、私は渡部とだけは二人で吞んでいた。私の人生でそんな人間は、常に一緒にいた学生時代の友人を除けば、渡部だけである。そのくらい親密だった。この十歳年下の友人とは、いくら話しても話が尽きなかった。加えて、セミナーでは「潤滑油的役割」を担ってくれてもいた。一度でも彼に会ったことのある読者ならば、私の言っていることが目に浮かぶように理解されることと思う。
私はウィスキーのコレクターという一面をもっているのだが、「自分が死んだらこのコレクションはすべて渡部にやってくれ」と妻に言っていたくらいである。酒の好きな男で、酒の肴になるような「いただきもの」があるといつも渡部にお裾分けをしたし、彼も奥さんの実家のある山形に行く度に日本酒やウィスキーを贈ってくれていた。
いまこれを書いているのは、1月27日の月曜日である。まだ彼の死から4日目だ。もちろんまだ彼の死を受け止め切れていないし、心の整理がつくなどという状態はまだまだ先のことだろう。
いま現在、私が仕事上、私生活上の愚痴をこぼせる人間はわずか数人といったところだが、渡部は私が愚痴をこぼせる友人のうち、最も若い人間だった。仕事でムシャクシャしたことがあると、平日でも呼び出して愚痴る。いい店を見つけたから行きましょうと、平日にもかかわらず私を呼び出す。そんな人間を私は渡部陽介しか持っていなかった。人は年齢を重ねるにつれて、愚痴をこぼせる人間を失っていく。特に五十を迎えた頃に極端に減ってしまう。そしてそこからは長く、それに耐えなくてはならない日常が続いて行く。その意味でも渡部陽介という男は、私にとってかけがえのない友人だった。
渡部が私にとってどれだけ大切な人物だったか、少しは伝わっただろうか。渡部の死は、私の心だけでなく、私の生活にもぽっかりと穴を空けてしまった。おそらく私の日常生活を変えてしまうに違いない。
2.2025年1月27日(月)07:52
渡部の通夜・告別式に参列し、今日、4日振りに出勤した。札幌らしいピンッと張り詰めた空気、強い陽射しは東に向かって運転する度に目を刺してくる。しかし、これまで同じような朝を何度も経験したはずなのに、「朝」が違う。もちろん自然は変わらない。空気も陽射しも変わらない。街並みも変わらない。いつもの通勤路だ。でも何かが違う。彼の死が私の中の何かを変えてしまったとしか思えない。
こういうときは、ただ淡々と仕事をするのだ。淡々とルーティンに向き合うのだ。そうした営みだけがこうした想いを乗り切るただ一つの道、ただ一つの在り方だと、この国の昔からの庶民感覚は伝えている。そうした文章、そうした映画、そうしたドラマを、何度読み、何度観たか知れない。
こんな日だというのに、いい朝だ。見事な朝である。

私ももう還暦が近い。子どもの頃から慈しんでくれた祖母を亡くし、両親もまた既に亡くしている。16年以上一緒に寝ていた飼い犬も亡くした。しかし、どの死も、少しずつ弱って行く彼ら彼女らを見ながら、時間をかけて、ある種の「覚悟」をつくっていたのだろうと思う。今回の渡部の死とは意味合いが異なる。
覚悟を持たぬ死、突然の死、想像だにしたことのない死も経験した。
2001年の師匠の死。54歳。まだまだ死ぬはずのない突然の死だった。
2011年の大学時代の友人の死。44歳。これから一緒に仕事をしようと打ち合わせ最中の突然の死だった。
しかし師匠は、私より20近くも年上だった。友人は同年代だった。だから私は、「彼らの遺志を継ごう」と思うことができた。それで自らを納得させることができた。
しかし、渡部は違う。彼は私に継ぐべき「遺志」など遺さなかった。私は彼を導き、支える側の人間だった。自分の遺志を継いでもらおうとさえ思っていた。そんな彼が逝ったのである。私はいま、死生観において、人生で最も混乱の渦中にある。私は今後、この混乱を抱えながら、この混乱を同伴者として、あと何年続くかわからない、しかしそう長くはないだろう人生を歩んで行くことになる。
3.ぐっと来る一文
私は本連載において、「文脈」を徹底して細かく丁寧に読むことを繰り返し主張してきた。文章を分析し、解析することを薦めてきた。しかし、私の中には、決して分析も解析もしないことにしている教材ジャンルがある。それは、実話(的)作品として、「死」を描いている教材である。
光村図書の中1教材に「大人になれなかった弟たちに……」(米倉斉加年)がある。1987年版以来採用されている、もはや老舗教材の一つである。終戦間近の夏、米倉斉加年が経験した生まれたばかりの弟の死、そしてそれに伴う母親の姿を描いた、実話をもとにした物語である。もともとは米倉作の絵本を教材化したもので、文章も米倉が書き、絵も米倉が描いている。
この教材を、私は分析も解析もしていない。授業さえ、私が朗読し、「ぐっと来る一文に線を引きながら聞きなさい。幾つ引いても構いません」と指示し、それを交流するだけである。年によってはその後、作文を書かせた年もあったが、最近はやめてしまった。「ぐっと来る」その来方を文章化なんてしたら安っぽくなると感じたからだった。
私は生徒たちだけでなく、教師相手のセミナーでも講座としてこの授業を扱うことが稀にある。「ぐっと来る」と線を引く箇所は、子どもでも大人でもあまり変わらない。次のような箇所だ。
・母は穴を掘りながら、ヒロユキがおとなしいから助かる、と言っていました。
・母は自分が食べないので、お乳が出なくなりました。
・食いしん坊だった僕には、甘い甘い弟のミルクは、よだれが出るほど飲みたいものでした。
・でも、僕はかくれて、ヒロユキの大切なミルクを盗み飲みしてしまいました。
・それも、何回も……。
・僕にはそれがどんなに悪いことか、よくわかっていたのです。
・でも、僕は飲んでしまったのです。
・僕は弟がかわいくてかわいくてしかたなかったのですが、……それなのに飲んでしまいました。
・ところが、親戚の人は、はるばる出かけてきた母と弟と僕を見るなり、うちに食べ物はないと言いました。
・母はそれを聞くなり、僕に帰ろうと言って、くるりと後ろを向いて帰りました。
・そのときの顔を、僕は今でも忘れません。
・強い顔でした。
・でも悲しい悲しい顔でした。
・僕はあんなに美しい顔を見たことはありません。
・僕たち子供を必死で守ってくれる母の顔は、美しいです。
・生まれて初めて見る、それは桃源郷でした。
・疎開しても、ヒロユキのお乳には困りました。
・母の着物はなくなりました。
・僕は弟が欲しかったので、よくかわいがりました。
・ヒロユキは病気になりました。
・十日間くらい入院したでしょうか。
・ヒロユキは死にました。
・暗い電機の下で、小さな小さな口に綿に含ませた水を飲ませた夜を、僕は忘れられません。
・泣きもせず、弟は静かに息をひきとりました。
・母と僕に見守られて、弟は死にました。
・病名はありません。
・栄養失調です……。
・死んだ弟を母がおんぶして、僕は片手にやかん、そして片手にヒロユキの身の回りのものを入れた小さなふろしき包みを持って、家に帰りました。
・白い乾いた一本道を、三人で山の村に向かって歩き続けました。
・バスがありましたが、母は弟が死んでいるのでほかの人に遠慮したのでしょう、三里の道を歩きました。
・空は高く高く青く澄んでいました。
・道にも畑にも、人影はありませんでした。
・歩いているのは三人だけです。
・母がときどきヒロユキの顔に飛んでくるはえを手ではらいながら、言いました。
「ヒロユキは幸せだった。母と兄とお医者さん、看護婦さんにみとられて死んだのだから。空襲の爆撃で死ねば、みんなばらばらで死ぬから、もっとかわいそうだった。」
・弟はその小さな小さな棺に、母と僕の手でねかされました。
・小さな弟でしたが、棺が小さすぎて入りませんでした。
・母が、大きくなっていたんだね、とヒロユキのひざを曲げて棺に入れました。
・そのとき、母は初めて泣きました。
・父は、戦争に行ってすぐ生まれたヒロユキの顔を、とうとう見ないままでした。
・僕はひもじかったことと、弟の死は一生忘れません。
主だった文を抜き出しただけでもこれだけの分量になってしまったが、まだまだ美しい文、心に響く文がたくさんあるので、未読の読者には一度は読んでみて欲しいと切に思う。
4.国語教師としての「倫理」
「大人になれなかった弟たちに……」に描かれた出来事は1945年のこと、絵本が出版されたのは1983年のことである。その間、40年弱。おそらく米倉斉加年は弟の死を背負って生きてきた。弟に配給されたミルクを盗み飲みした米倉である。自分がミルクを盗らなければ弟は死なずに済んだのではないかとの思いに苛まれ続けてきたに違いない。「自分が殺した」という思いさえ抱いたことだろう。そんな思いが40年である。米倉斉加年は2014年8月26日に亡くなっているが、事実、晩年に至るまで彼はそうした思いをエッセイや対談で語り続けてきた。私なんぞには想像もできないような内省の日々だ。
私もいま、友人を失った悲しみに打ちひしがれているが、少なくとも、彼が自分のせいで死んだという思いは私にはない。それでさえこれほどに打ちひしがれるというのに、自らの責任論、自らの原罪論を抱えながら過ごす数十年とはいったいどういうものであったか。そんな背景を持つこの作品を切り刻むことなど、私にはとうていできない。
米倉斉加年は、いわゆる「プロの書き手」ではない。主たる仕事は昭和の名優であった。確かに文筆もあったし、絵画もイラストもあった。書籍も画集も絵本も何冊もある。しかし、彼の主たる職業は役者である。私も子どもの頃から親しんできた名脇役だ。いまで言う名バイプレイヤーだ。しかも、それしかしないのかはたまたできないのか、善人の役と変人の役しか見たことがない。それだけに子供心にも印象的な役者だった。
彼の演じる人物はいつも、瞳に哀しみを湛えていた。しぼり出すような声でゆっくりと語る。朴訥と語ることで観る者を惹きつける。そんな役者だった。それは彼がもともと、映画の役者やテレビドラマの役者である以上に、「演劇人」であったことが影響しているのかもしれない。
そんな、決して「プロ」とは言い難い書き手の、実話をもとにした死と罪の物語において、「教材解釈」や「教材研究」の名のもとに切り刻むことなど不遜極まりない。私にはそう思えるのだ。
これは私にとって、国語教師としての「倫理」なのだと思う。
「道徳」と「倫理」はよく類比的に扱われるが、両者はまったく異なるものだ。
道徳は時空に支配される。時空によって変容すると言ってもいい。日本の道徳と中国の道徳は異なるし、江戸時代の道徳と令和の道徳も異なる。道徳教育を推進する者は、いま自分が扱っているテーマが普遍でないかもしれないという可能性に自覚的である必要がある。道徳教育推進者にそのメッセージが感じられない。
一方、倫理は時空が変わっても変化しない。あくまで個に帰属する。宮台真司に倣って言えば、たとえ周りがすべて敵になっても、場合によってはそれを主張することで自分が殺されるかもしれないとしても、それでも自ら貫く規範、それを「倫理」と言う。私は道徳規範に敏感な人間よりも、自らの倫理に生きる人が好きだ。ちょっと文学的かもしれないが……。
「真善美」でいえば、道徳は「善」に帰属し、倫理は「美」に帰属する。そして、道徳に照らしたにせよ、倫理に照らしたにせよ、自らの判断を懐疑すること、これを良心と言う。そこに「真」が志向される。私は道徳と倫理と良心、真善美の関係をこうしたものだと捉えている。
5.個人的な美意識
戦時中に犯した罪を背負いながら生きる主人公を描いた教材としては、長く教育出版で教材として採択されてきた「夏の葬列」(山川方夫)がある。艦載機の銃撃の下、自分を助けに来てくれた少女を突き飛ばし、結果的に殺してしまった……そんな物語である。
読者の皆さんは、この教材も「大人になれなかった弟たちに……」と同様の構図であり、むしろ直接的に手を下している分だけ背負った罪は大きいと思われるかもしれない。その意味では、国語教師の倫理として、この教材もまた解析すべきではないと。
しかし、そうではない。「夏の葬列」はショートショートのフィクションに過ぎない。しかも、一度は自分は殺してなかったと勘違いする主人公が、「何の病気で死んだの?」と余計な質問をすることによって子どもたちの口から真実を知る……というどんでん返しのアイディアによってショートショートを構成したに過ぎない、謂わば「小品」である。なのに「夏の葬列」好きの国語教師たちがこの教材の内容を重く捉えすぎることによって、まるで戦争文学の代表作であるかのように錯覚されてきた経緯がある。むしろこの教材は私にとって、徹底して分析・解析されることによって、ショートショートとしての完成度が批評されるべき教材である。
ここまでを読んで、読者は、私が国語教師の倫理として解析すべき教材とそうでない教材とを分ける基準を、「実話か否か」という点に置いていると思われたかもしれない。
しかし、そうではない。
あまんきみこに「ちいちゃんのかげおくり」という作品がある。これも絵本だ。空襲警報の中、家族とはぐれたちいちゃんが、孤独の中で亡くなって行く様子をファンタジックに描いた名作である。これもまた、小学校の教科書(光村図書)に教材として採択されている。この物語もおそらくフィクションであろう。しかし、「かげおくり」のエピソードはともかくとして、このように親とはぐれて孤独に死んでいくしかなかったであろう子どもたちは、戦時中には現実に幾千幾万といたはずである。そんな子どもたちに思いを馳せるとき、私にはこの物語を解析することなどとうていできない。他ならぬあまんきみこ自身も、おそらくはその想いで、ちいちゃんを幻想世界で家族のもとに帰すことでちいちゃんを救ったのだろうと思う。
「国語教師としての倫理」などと大仰な言葉を用いながら、お前の基準は恣意的ではないか。そうした批判があるとすれば甘んじて受けようと思う。「倫理」というものは、先にも述べたように「個人の美意識」に帰属する。私は何に恥じることもなく、こう主張し続けようと考えている。
6.2025年1月28日(火)07:52
日が明けて、今日は1月28日の火曜日である。私は渡部陽介の告別式が終わって以来、毎晩1軒ずつ、渡部と二人で通った常連の店に渡部の死を報告して回っている。
渡部は義理堅い男で、一度仲良くなった店主の店には、ずーっと通い続ける男だった。そんな店が7、8軒ある。初めて会った人ともすぐに仲良くなるという特技を持っていて、いろいろな店で初めて会った客と笑いながら話し込む癖もあった。人見知りの私とは大違いである。
そんな奴だったから、どの店主ともほんとうに仲が良く、報告に行くとみんな大きなショックを受けていた。昨夜伺ったある店主などは、報告した途端に泣き出してしまい、しばらく仕事に手がつかなかった。私は開店の少し前に伺ったのだが、開店し、他の客が来ても涙目で対応する有様だった。私が渡部の遺影の写真を見せた瞬間、「無理です無理です。まだ全然無理です」と声を詰まらせ、しばらく奥に引っ込んでしまい、私の方が心配したほどだった。
こうした店主たちは、渡部と「公的な場所」でつながっていたわけではない。だから、元同僚や友人たちのように通夜・告別式の連絡が行くわけではない。しかし、何の緊張感もない、緩み切った、本音だけの渡部陽介と付き合っていたのは、むしろ彼らなのである。少なくともここ十年ほどの渡部陽介の「実態」をほんとうによく理解している人たちであるわけだ。そして、私もその一人だったということになる。
人と人とのつながりというものは、公的な「表文化」の中ばかりにあるのではない。むしろ、表には出て来ない「裏文化」での結び付きの方が強いってことが山ほどある。私の言う「国語教師としての倫理」の対象も、その人個人の、その人独自の「裏文化」を描いたものに対しては分析・解析をしない、ということなのかもしれない。そういえば私には、いかなる著名人を対象としていようと、マスコミがプライバシーを暴く報道をしていると反吐が出るほどの嫌悪感を抱くところがある。
今日も陽射しは暖かく、陽を纏った雪がちらちらと眩しい。北海道の冬の晴天は相も変わらず美しい。

この哀しみ……というよりはこの動揺と混乱を抱きながら、私は「渡部陽介のいない世界」を、もう少しだけ生きることになるらしい。
※ この連載は原則として月に1回公開予定です。次回もお楽しみに。
【堀 裕嗣 プロフィール】
ほり・ひろつぐ。1966年北海道湧別町生まれ。札幌市の公立中学校教諭。現在、「研究集団ことのは」代表、「教師力BRUSH-UPセミナー」顧問、「実践研究水輪」研究担当を務めつつ、「日本文学協会」「全国大学国語教育学会」「日本言語技術教育学会」などにも所属している。『スクールカーストの正体』(小学館)、『教師力ピラミッド』(明治図書出版)、『生徒指導10の原理 100の原則』(学事出版)ほか、著書多数。
写真/西村智晴
堀 裕嗣 先生のご著書、好評発売中です!
↓「スクールカーストの正体ーキレイゴト抜きのいじめ対応―」
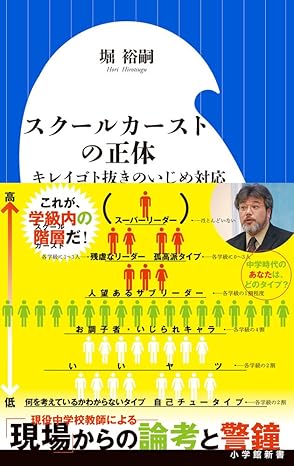
↓「アクティブ・ラーニングの条件ーしなやかな学力、したたかな学力-」