小4特別活動「10才の節目~5年生に向けて~」指導アイデア

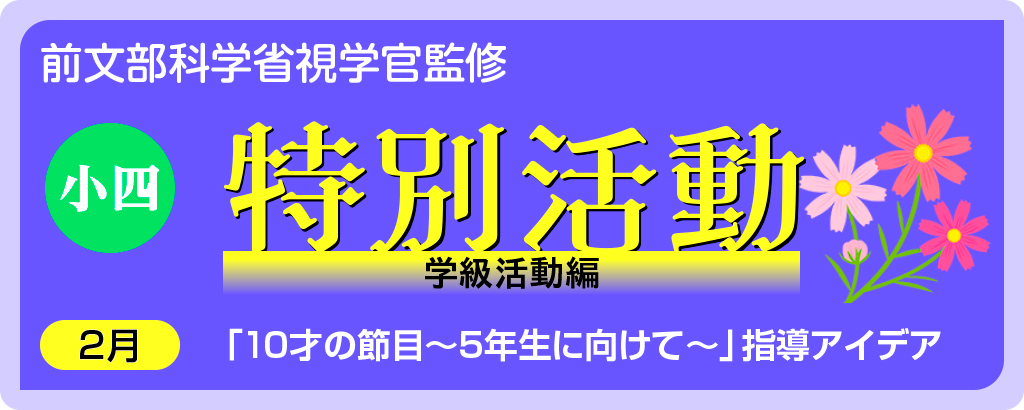
多くの4年生が10才を迎えている年度末。高学年である5年生を目前に控えた子供たちに、希望や目標をもって生きることの意義や、現在および将来の自己の生き方を取り上げることで、楽しく豊かな学級や学校の生活づくりにも主体的に関わることができるようにしたいものです。
本実践では、自己の生き方についての考えを深めることができるよう、これまでの自分の生活を振り返りながら10才を1つの節目と捉え、高学年である5年生に向けて「なりたい自分」について学級のみんなで考えます。これまでの成長に気付くとともに、「なりたい自分に向けてがんばりたい」「将来の自分をよりよい姿にしたい」という願いが芽生えていくことをねらっています。
今の学びが将来につながることを知り、友達と認め合い、高め合ってともに成長していくための意思決定を工夫した学級活動(3)の実践を紹介します。
執筆/青森県八戸市総合教育センター主任指導主事・馬渡静香
監修/帝京大学教育学部教授(前文部科学省視学官)・安部恭子
青森県公立小学校校長・河村雅庸
目次
年間執筆計画
4月 学級活動(3) ア 4年生になって
5月 学級活動(1) 係を決めよう
6月 学級活動(2) ウ 歯ぴかぴか大作戦
7月 学級活動(3) ウ 見直そう自分たちの読書
9月 学級活動(1) オリジナルチャレンジ集会をしよう
10月 学級活動(1) 4年生仲良し集会をしよう
11月 学級活動(2) エ よりよい給食のマナー
12月 学級活動(1) 『学校をきれいにしよう大作戦』をしよう
1月 学級活動(1) 2年生と笑顔いっぱい集会をしよう
2月 学級活動(3) ア 10才の節目~5年生に向けて~
3月 学級活動(1) 4年生がんばったね集会をしよう
学級活動(3)について
学級活動(3)「一人一人のキャリア形成と自己実現」は、現在及び将来の生き方を考える基盤になるように、学校の教育活動全体を通して行うキャリア教育との関連を考慮して、設定している年間指導計画に沿って、教師が意図的に指導する内容になります。
また、本題材は「ア 現在や将来に希望や目標をもって生きる意欲や態度の形成」の内容です。学級や学校での生活づくりに主体的に関わり、自己を生かそうとするとともに、希望や目標をもち、その実現に向けて日常の生活をよりよくしようとすることをねらいとしています。

