学級に支持的風土をつくる「関連発言」の指導法【主体的に生きる力を育む学級経営の極意⑩】

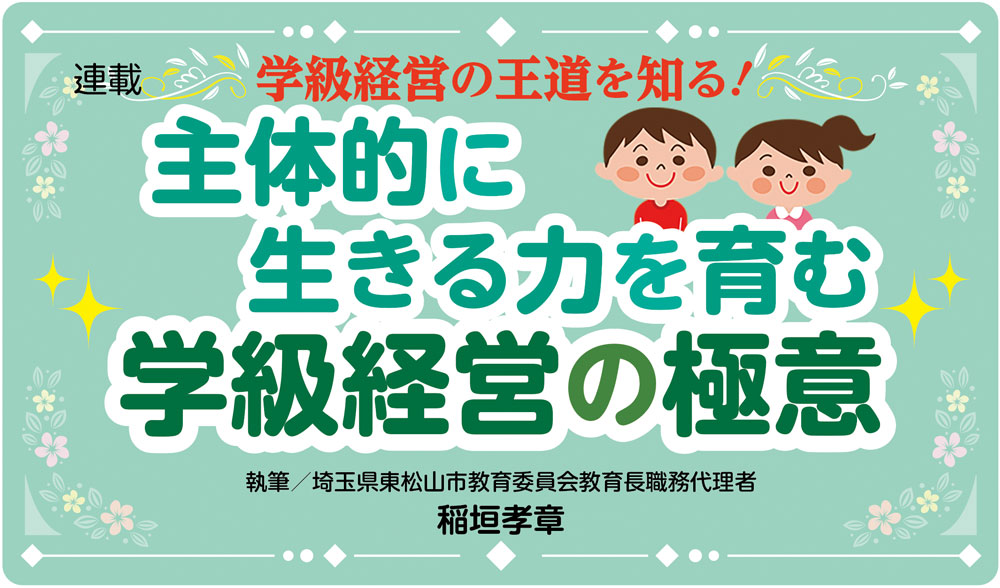
子供たちが多様な他者と関わりながら社会につながり、主体的に生きる力を育んでいくために、教師はどのような学級経営をしていけばよいのでしょうか。学級経営・特別活動を長年、研究・実践してきた稲垣孝章先生が、全15回のテーマ別に学級経営の本流を踏まえて基礎基本を解説します。第10回は、「関連発言」の設定法について解説します。
執筆/埼玉県東松山市教育委員会教育長職務代理者
城西国際大学兼任講師
日本女子大学非常勤講師・稲垣孝章
「関連発言」は、「主体的・対話的で深い学び」に向けた授業改善の中核と言っても過言ではありません。一見、子供の挙手が多く、活発に学習しているような授業でも、教師の発問に対して、子供たちの反応が「一問一答」となるようなピンポン式の授業からの脱却は急務です。授業の中で子供たちの「関連発言」が効果的に展開できるように「聞くことの指導」「関連発言の話型」「実践上の配慮事項」の視点でチェックしてみましょう。
目次
CHECK① 聞くことの指導
「主体的・対話的で深い学び」の授業改善の柱とも言える「関連発言」を授業の中で展開するには、「聞くこと」の指導が不可欠です。相手の意見を傾聴しながら「聞くこと」ができてこそ、関連した発言が可能となります。
発言の際に「主語」を付けて、発言の「理由」も発表できるように指導します。「私は、~」の発表を受けて同じ考えであれば、「私も〇〇さんと同じ考えで~」と発表します。これは、相手の意見を聞いていないと発表できません。まずは、聞くことに集中して学習に取り組むような指導をしましょう。
「聞くこと」によって、自分の考えとの比較ができます
「聞くこと」には、相手の考えの意図を類推して聞くことや、相手の思いや願いを推し量りながら聞くこと、自分の考えとの相違点を考えながら聞くことなどがあります。相手の考えを傾聴しながら「聞くこと」によって、自分の考えと比較することができ、多様な考えがあることを体感し、学びが深まります。
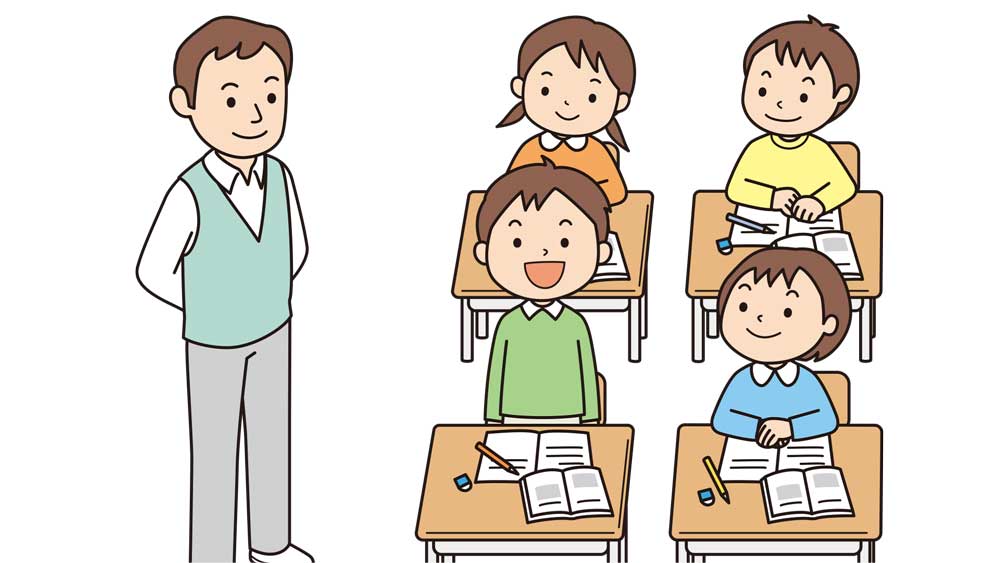
CHECK② 関連発言の話型
「関連発言」とはどのような発言なのか、具体的に子供たちに指導することが求められます。「関連発言」の話型(話し方)には、多様な種類があります。学年の発達段階に応じて、指導することが望まれます。ここでは、基本的な話型の種類について取り上げます。
「関連発言」の基本的な話型を指導します
①「質問」(~については、Aさんはどのように考えていますか)
②「確認」(Aさんの考えは、~ということでよいのでしょうか)
③「付加」(私は、Aさんの考えに~を付け足すとよいと思います)
④「統合」(私は、AさんとBさんの考えを合わせて~にしたらよいと思います)
⑤「承認」(私は、Aさんの考えの~というところがよいと思います)
⑥「再考」(私は、みんなの考えを聞いて、~という考えに変えました)
⑦「発展」(私は、Aさんの考えに~を加えるともっとよくなると思います)
⑧「援助」(私は、Aさんが言いたいのは、~という考えだと思います)
⑨「賛成」(私は、Aさんの考えに賛成です。理由は、~だからです)
⑩「修正」(私は、Aさんの考えを~に変えるとよくなると思います)
CHECK③ 実践上の配慮事項
「関連発言」とは、自分と異なる他の意見を受け止め、それに関する自分の意見を発表することです。他の意見をしっかり聞くことが「自分のため」になること。また、自分の考えを友達に伝えることが「みんなのため」になることを指導していきましょう。
支持的な風土、共感的な雰囲気が基盤となります
「関連発言」を可能にするためには、どのような意見を言っても受け入れてくれる学級の「支持的な風土」が不可欠です。また、たとえ自分と異なる考えであっても、受け入れて共に考える「共感的な雰囲気」があることが大切です。「主体的・対話的で深い学び」の授業改善に向けた指導として、「関連発言」を重視した授業展開となるようにしていきしましょう。
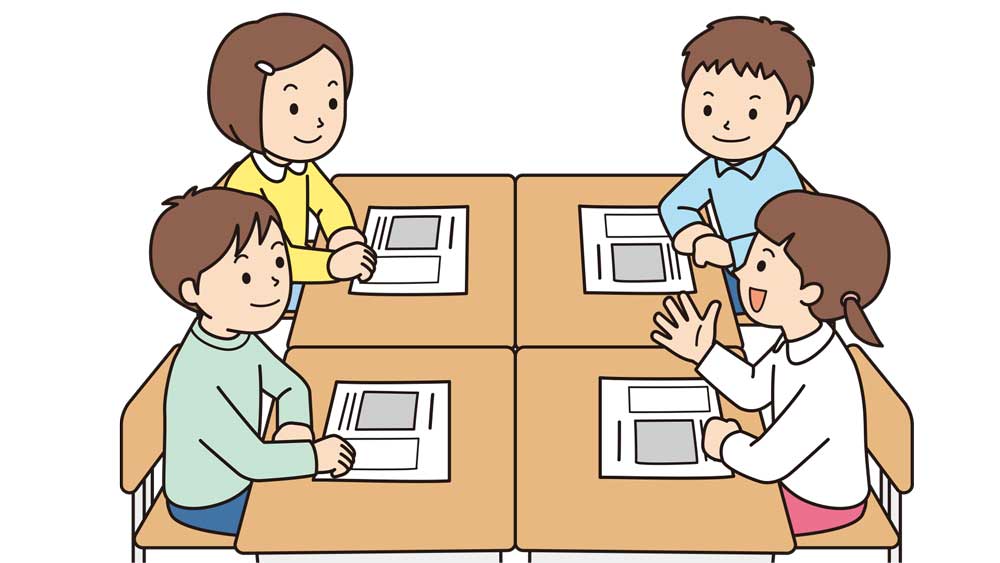
イラスト/池和子(イラストメーカーズ)

