子供が生き生きと活躍し、保護者の信頼が深まる「授業参観」の進め方【主体的に生きる力を育む学級経営の極意⑬】

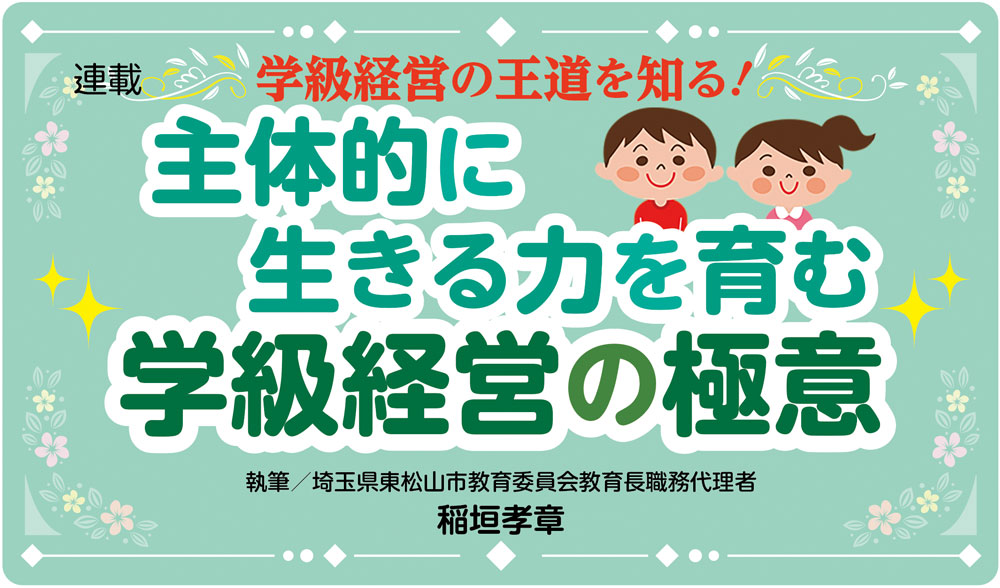
子供たちが多様な他者と関わりながら社会につながり、主体的に生きる力を育んでいくために、教師はどのような学級経営をしていけばよいのでしょうか。学級経営・特別活動を長年、研究・実践してきた稲垣孝章先生が、全15回のテーマ別に学級経営の本流を踏まえて基礎基本を解説します。第13回は「授業参観」の進め方について解説します。
執筆/埼玉県東松山市教育委員会教育長職務代理者
城西国際大学兼任講師
日本女子大学非常勤講師・稲垣孝章
「授業参観は、学校と保護者の信頼関係を築く貴重な行事です。保護者は、授業参観を通じて子供の授業での様子を把握するとともに、担任の指導力や人間性、教育への情熱等を感じ取ります。保護者が時間を割いて学校に来てよかったと感じるような時間にすることが求められます。次の3つのキーワード「教室環境の整備」「授業展開の工夫」「実践上の配慮事項」からチェックしてみましょう。
目次
CHECK① 授業参観時の教室環境の整備
最初の授業参観が肝心です。まずは、保護者に参観のルールを提示しておきます。例えば、「出入り口付近ではなく、教室の奥から詰めて入るように。教室内や廊下での私語には十分な配慮を。写真撮影はご遠慮を」などについて提示しておきます。
教室環境は、保護者に教師の指導力を印象付けるものです。「教室内に全員の子供の作品が掲示されていること。ロッカーや用具等が整然としていること。黒板がきれいに消されていること」などの物的な環境整備にも十分に配慮しましょう。

保護者に授業参観の視点を伝えます
授業参観では、保護者が帰宅後、子供に称賛の言葉をかけることができるよう、視点をもって学習の様子を観るように伝えましょう。
特に、挙手の回数等の表面的なことだけでなく、話を聞く態度や学ぼうとする意欲を見取ることの大切さについて伝えます。また、他の子供との比較ではなく、その子なりのよさに目を向ける視点をもつことの大切さを伝えていきましょう。
CHECK② 授業展開の工夫
授業参観で、教師が子供たちの学習意欲を喚起し、一人一人の子供が生き生きと学ぶ姿をみると、保護者も安心できます。
教師が全員の子供に温かな笑顔で視線を送り、一人一人の学ぶ姿を見取り、称賛していこうとする姿勢は、参観する保護者にも伝わります。
子供の学習意欲は授業展開で変わります
授業では、子供たちから「え~」といった疑問や、「わ~」といった驚き、「う~ん」といった疑問などの声が上がるような資料提示の工夫が大切です。
また、現在は、多くの授業でICTを取り入れています。授業のねらいを達成するための手段として効果的に活用し、ICT活用が目的にならないよう工夫しましょう。

CHECK③ 授業参観を実践する上での配慮事項
授業参観では、いつもはよく発言していても急に発言しなくなる子供、またはその逆の子供もみられます。
仕事等の都合で、保護者が来校できない家庭もあります。また、親子関係が良好な家庭ばかりでないことも考えられます。このようなことを念頭に置いて、個に応じた授業を展開していくことが求められます。
授業参観だからこそできることがあります
授業参観で、保護者にも授業に参加してもらうことは、普段の授業ではできにくいことです。例えば、理科のグループごとの実験に一緒に参加してもらったり、総合的な学習の時間のグループ発表を参観してもらったりするなどの方法もあります。
授業参観では、どの子も活躍できる授業、どの子も称賛される場を設ける授業となるように努めていきましょう。そして、保護者が時間を割いて来校してよかったと思えるように様々な配慮をしていきましょう。
イラスト/futaba(イラストメーカーズ)

