<連載> 菊池省三の「コミュニケーション力が育つ年間指導」~3学級での実践レポート~ #11 千葉県船橋市立田喜野井小学校5年1組②<前編>

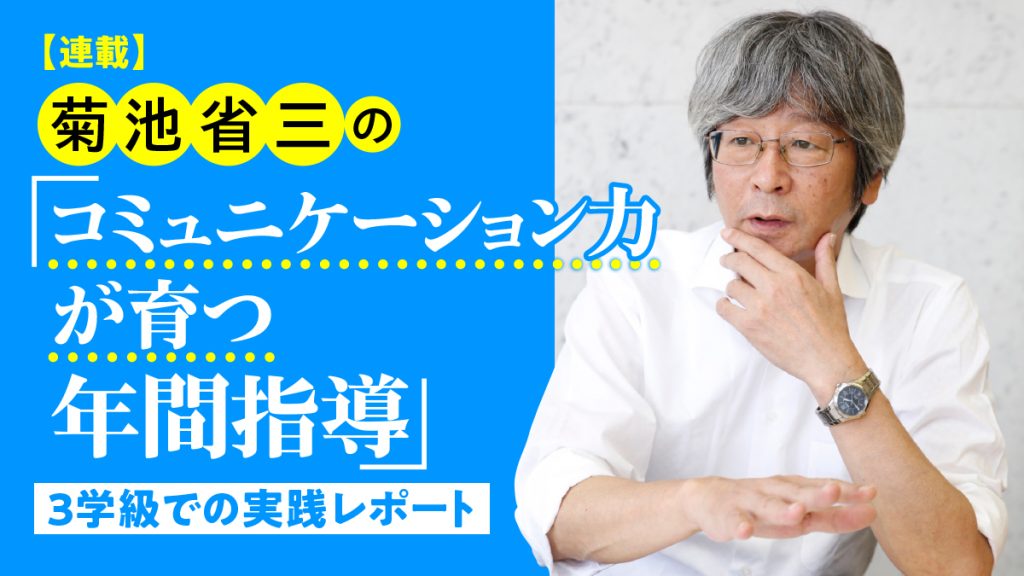
菊池実践を追試している3つの学級の授業と子供たちの成長を、年間を通じてレポートする連載。 今回からは、千葉の植本学級(5年生)における9月下旬の授業レポートです。菊池先生と植本先生による、2時間続きのディベート(総合)の合同授業です。

目次
担任・植本京介先生より、学級の現状報告
9月に入り、学級全員が同じ場面や同じタイミングで笑うようになってきました。7月までは授業中にユーモアのある発言が出ても、一斉に「わっ!」と盛り上がることはあまりありませんでした。みんなで盛り上がる場面を見る度に、子供たちの関係性が築かれ、聞く力が身に付き、学級の中で一人一人の個性が少しずつ発揮され始めたのかな、と考えています。
前回、6月の菊池先生の訪問授業の際には、「かみ合った話し合いに向かう」ことをテーマにしていました。
しかし、それを意識するあまり、「話し合いのもつ知的な楽しさ」から遠ざかってしまいました。根拠を伴った話し合いをすることや、相手の意見を引用して話し合うことなどを意識するあまり、話し合いが窮屈になってしまったのです。
その時の菊池先生の授業は、「相手の意見の理由付けの部分を “ひっくり返す”、そこを面白がる」というもので、1時間の中で子供たちの表情がどんどん柔らかくなっていったことを感じました。
「話し合いは楽しい」という原点に改めて気付かされました。
それ以降、「相手の意見をひっくり返すことを楽しもう」「考え続けることの面白さを大事にしよう」という思いを強く持ちつつ、国語科や社会科、道徳科など様々な授業に話し合い活動を取り入れ、総合的な学習の時間ではディベートに取り組み始めました。 これまでに学級ディベート、マイクロディベートを経て、今回の授業ではいよいよディベートに臨みました。
菊池先生と植本先生の合同授業レポート
「ディベートは、一生懸命聞き合うゲームです。今日はみんながどれぐらい聞き合っているかを見せてもらおうと思っています。一生懸命聞き合うためには、誰かが発表しているとき、自分のチームも相手チームも審判も、みんながメモを取るはずですね。全部で4試合もあるので疲れるかもしれないけれど、先生も今日の授業は “日本一” のディベート大会のつもりで見ます。
ディベートは思いやりのゲームです。同じチームの友達が困っていたら、メモを渡したり、作戦会議でアドバイスしたりして、助けてあげてください。審判の人は、勝ち負けだけではなくて、『ここがよかった』『もっとこうしたらいいよ』とアドバイスできるようにしてください。
みんなで思いやりのゲームを楽しみましょう!」
授業の冒頭、菊池先生が、みんなにディベートの “心構え” を話すと、子供たちが大きな拍手をした。
![]()
ディベートというと、話すことに目が向きがちですが、じつは “聞き合う” ことがキモになります。
立論= “議論をつくる” こと、質疑や反駁= “議論をする” こと、そして、審判= “議論を読む” ことです。
自分のチームが発表しているときも相手チームが発表しているときも、それを審判しているときも、その発表をしっかりと聞いていなければ、議論をすることも、議論を読むこともできません。
ディベートには勝ち負けがあるので、子供たちは “しっかりと話すこと” に力を入れますが、聞き合うことに子供たちの目を向けることが、後々のディベートの迫力につながっていきます。そこを意識させるため、冒頭で聞き合うことの大切さを明示しました。
「いい緊張感ですね。でも緊張しすぎかもしれないので、隣の人と笑顔で『頑張ろう!』と言い合いましょう」
と植本先生が話すと、菊池先生が、
「今、思いやりって言ったけど、負けちゃだめだよね(笑)。じゃあ、チーム同士で『負けないぞ!』と怖い顔で言え!」と続けた。二人の言葉かけに、
「頑張ろう!」「負けないぞ!」
と子供たちが奮起した。緊張気味だった教室の空気が一気にほぐれ、盛り上がった。
8チームでディベート開始
<ディベート論題>
「船橋市の小・中学校は夏休みを半分にするべきか」
<今回のディベートのルール>
まずチーム同士で立論を考え、あらかじ め表明。立論に基づき、相手チームへの質問や反論を考え、発表。発表、作戦時間はすべて1分間。
①賛成側立論 →作戦タイム → ②反対側質問
③反対側立論 →作戦タイム → ④賛成側質問
⑤反対側反論(第1反駁)
⑥賛成側反論(第1反駁)
第1反駁は、質問した内容に対してだけでなく、立論に対して反論してもよい。
⑦反対側反論2(第2反駁)
⑧賛成側反論2(第2反駁)
計4試合のうち、最初の3試合は第1反駁まで、 最後の1チームは⑦⑧の第2反駁まで発表。審判は、発表の2チーム以外の4チームが行う。
まず一人一人で勝敗を考え、判断してから、それぞれの審判チームで相談し、どちらかに絞って決める。
第1試合 賛成側:TMACチーム、反対側:ラムネチーム
菊池先生が、
「審判の人は、『自分だったら、ここを質問したいな、ここに突っ込めるな』と考えながら聞きましょう。『なぜそう言ったのか』『なぜこんな質問をしたのか』」と、『なぜ』を見つけていきましょう」 とアドバイスした。
①賛成側立論
「宿題のストレスが減る」
理由:夏休みの宿題は、自由研究や読書感想文でストレスがたまる。宿題へのやる気がなくなり、後回しになる。夏休み後半にやると宿題に負われ、家族からも「宿題をやりなさい」と言われ、それもストレスになる。夏休みが半分になれば宿題が減り、ストレスも減る。
②反対側質問
質問)宿題が多いからやる気が減ると言いましたが、宿題が減ればやる気が増えるということですか。
回答)はい。
質問)遊んだりして楽しくなって、宿題が後回しになるのですか。
回答)はい。
質問)宿題に負われてストレスになると言いましたが、どれくらいのストレスになるのですか。
回答)けっこうあります。
③反対側立論
「教員不足になる」
理由:教師を辞めたい人が増えている。夏休みが半分になると教員の働く時間が増えるので、辞める人が増えて教員不足になる。
④賛成側質問
質問)教師を辞めたい人は、何%いるのですか。
回答)大体68%くらいです。
質問)夏休みが半分になると教員の働く時間が増えると言いますが、生徒の下校時間が早くなるのでは。
回答)あまり影響はありません。
質問)やめる人が増えるというのは、予想ですか。
回答)はい。
⑤反対側反論
宿題をやらない日が増えると言うが、半分になっても変わらない。 楽しくなって後回しにするなら、ストレスになっていない。
⑥賛成側反論
予想だったら、減っていく可能性がある。32%は辞めないし、辞めてもまた新しい先生が入ってくる。下校時間を早くすれば、先生たちはもっと仕事にあてられる。
<判定>
賛成0:反対6で、反対側の勝ち
<反対判定の理由>
審判を代表して、1人が理由を発表した。
「(2人が欠席した中で)たった2人でも頑張ったのは準備力があったから。賛成派はちょっとかみ合っていなかった」。
<菊池先生の判定>
賛成側の勝ち
反対側は、連続で質問した人がいた。4つめの質問は、2つめに質問したことに関係した質問だった。これは凄いこと。ずっと「なぜか」を考え続けていたから、質問できたことだった。
反対側の反論では、「遊んで後回しにするからストレスになる」という意見に対して「宿題をやらない日は、夏休みが半分になっても変わらない」という反論だったが、あまり強い反論ではなかった。
賛成側の「先生は早く帰って仕事ができるので、負担が減る」という反論は、とても納得できる有効な反論だった。こうしたことから、賛成側が勝ったと判定した。
<植本先生の感想>
賛成側は「次はこうしたいね」と反省会をしていた。反対側は、ずっとしっかり話を聞いていた。次はもっと強くなれるだろう。
![]()
ディベートにまだ不慣れな子供たちには、「メモをとりましょう」と言葉をかけるだけではなく、子供たちの意見をもとに、教師が黒板にフローシートを記入してあげるといいでしょう。子供たちには、自分で書いてもいいし、写してもいいことを伝えます。
「今の反論は、立論のこの部分からつながっているんだね」というように、解説をしながら、記入していきます。教師が書いた自分のフローシートを、机間巡視をしながら、子供たちに見せて回ってもいいでしょう。
このように細かく丁寧に指導していくことで、「こういう風に書けばいいんだ」と理解できれば、子供たちも書けるようになってきます。

