仕事がつらいと感じる若手は要チェック! 成長できる教師、3つのマインドセット

「2学期、あの子は元気に学校に来てくれるかな?」。少しの不安とともに、そう思い浮かべる子供はいませんか? 「教育の本当の面白みを教えてくれるのは、そんな子供たちです」と言うのは、ハヤトカゲこと花まるエレメンタリースクール校長の林隼人さん。花まるエレメンタリースクールのスタッフへのインタビューから、成長できる教師がもっているマインドセットについて探ります。
目次
心得1 「この子としっかり向き合おう」と覚悟を決めよう
お話を伺ったのは、花まるエレメンタリースクールの校長、ハヤトカゲこと林隼人先生と、AKIこと町山阿記さん、RYUことサターフィルド龍さんです。花まるエレメンタリースクール(通称・花メン)は、学校に行かない選択をした子供たちのためのフリースクールです。
★事例は本人が特定できないよう適宜調整を入れています。
教育の醍醐味を教えてくれるのは、誰?
教師の毎日は、授業をして、保護者対応をして、校務をこなし‥‥‥。ある時ふと、「これが本当に『教師になる』ってことなのかな?」と疑問に感じたことはありませんか?
ハヤトカゲ校長は、こんなふうに言います。
教育という仕事の楽しさは、授業以外のところにあります。
ハヤトカゲ 授業中に見えている子供の姿は、その子の2割くらいにすぎません。もちろん授業も大切ですが、授業以外の時間で課題のある子と向き合い、悪戦苦闘した結果、その子が変わっていく瞬間に立ち会えた……という経験は多くあります。
子供が変わる瞬間を目の当たりにすると、教師という職業が、より面白く深いものだと気付けます。
そういった「子供と向き合うことの醍醐味」を教えてくれるのが、課題のある子供たちです。そうした子たちと向き合うことにこそ、教師という職業の難しさも、嬉しさも詰まっていると僕は考えています。
自分から一歩、子供に踏み込む瞬間
AKI 花メンには、「3~4年間学校に行っていない」「小学校を2~3校たらい回しにされた」「すぐに手が出る子というレッテルを貼られている」など、前評判だけだと、「大変そうな子」がたくさん通って来ています。
そうした課題のある子を初めて担任する時は、「そんな子、担任したことがないから」と誰だって不安になります。でも、教師生活の中で、課題のある子と関わる場面は避けられないわけですよね。若いうちにそうした子と真剣に、真正面から向き合う経験はとても大切で、それがなければ教師としてはいつまでも薄っぺらいままだと思います。
実際に課題のある子と向き合っていると、どんな子も、一対一で接している分には、意外と「普通の子」だと感じます。普通に「へぇ~、この子、鉄道が好きなんだな」みたいなことを感じるわけです。
どの子にも、可愛い一面が絶対にある、ということです。
RYU いくら前評判が芳しくない子でも、最年長でも12歳までの子供ですよね。「教師としてその前に立っている俺たちは、何歳なんだ?」という話です。「俺たちが余裕を持って関わらないで、誰が関わるんだ?」と思いながら、子供たちと向き合っています。
もしかしたらこれから、「授業をするのはAI」という時代が来るかもしれません。「じゃあ、人間がする教育って、何なんだろう?」と考えた時に、僕は「一人の人間として子供と向き合うこと」だと思っています。そこに真剣に取り組まなければ、「何のために教師になったのか?」と問われてしまうでしょう。
心得2 子供の心が「ぐっと近付いてくる」瞬間を体験しよう
その子のストーリーを知ろう
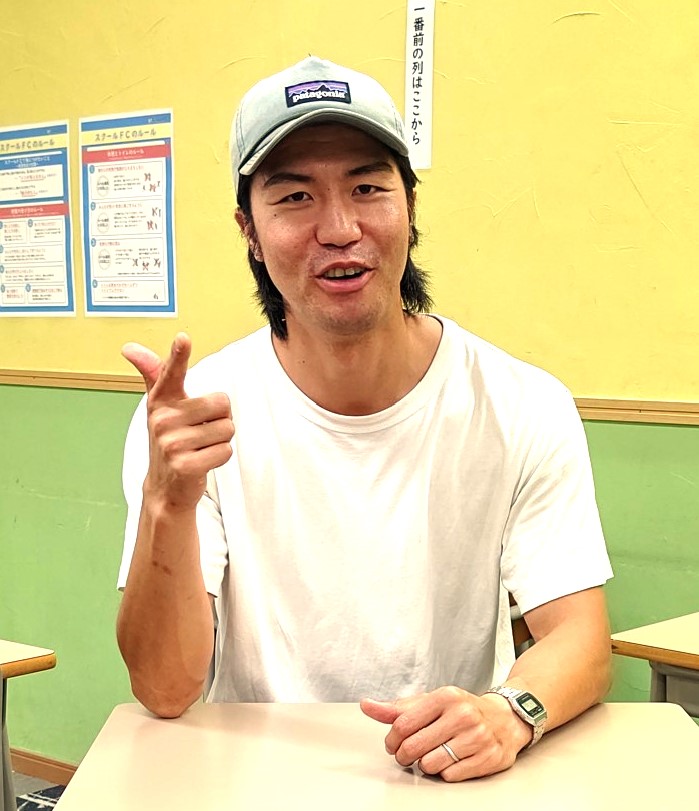
ー 子供に向き合いたいと思いつつも、一歩踏み込む勇気が持てない時は、どうしたらいいですか?
AKI 子供のことを知ることだと思います。たとえば、子供のことは基本、学校生活の中でしか見ることができませんが、どの家庭にもストーリーがあります。
僕が経験した例だと、就学前にご両親が離婚し、その後お母さんには彼氏ができた。子供はお母さんの彼氏が苦手だ、という状況を知ったことで、自分の中に眠っていた「この子を何とかしたい」という身体の中から突き動かされるような衝動を感じました。
その時初めて、「授業をしているだけでは、この子のことを何も知ることができていなかった……」と気が付きました。
RYU 「この子としっかり向き合う」と決めて、一人の子と徹底的に向き合う体験をすると、「子供一人ひとりの何かをもっと見てみたい」という気持ちが生まれましたね。
「あ、本当だ!」という瞬間が訪れる
AKI 課題のある子に向き合おうと決めて、腰を据えていると、どこかでその子の心をぐっとつかむことができる瞬間が来るんです。
RYU 僕も感じたことがあります。それを感じると、その子のことをぐっと可愛く思えてきます。
あ、本当だ。ハヤトカゲが言っていたこと、本当だ!――と思う瞬間です。
「あ、本当だ」という瞬間を20代のうちに経験できたのは、ものすごく大きかった!
この「可愛く思えてくる感じ」が一番重要で、そうなった後は、その子と歯車が嚙み合っていきます。
このように子供の心がぐっと近付いてくる体験をした時に、教育という仕事の醍醐味を感じます。学校に行けなくなってしまう子たちは、基本的にしっかりと自分を持っています。彼らときちんと向き合うと楽しいし面白いです。
ハヤトカゲ 教育という仕事を選んだからには、みんな本来、子供が好きなはずですよね。だから若手の先生方には20代のうちに、そうした経験をぜひ積んでほしいと考えています。
でも、職場で「教育って仕事は、そういうところが面白いんだぞ!」と教えてくれる先輩に出会えていない場合、「毎日の授業や校務を滞りなく進めること」に重きを置きすぎて、意識せずに課題のある子を排除してしまう可能性もあります。
心得3 子供たちの最も主体的な行為である「ケンカ」。適切な仲裁を体験しよう
子供との「雑談」の大切さ
ー 教育の醍醐味を教えてくれる先輩に出会えていない場合、どうしたらいいでしょう?
AKI 子供との距離を、今よりも縮めてみてはどうでしょう?
自分が学生だった頃を思い返しても、子供との距離を縮めるのが上手な先生はいました。上手な先生は、自然と「どんな会話をすれば子供と距離が縮まるか」を知っているんですよね。
僕が子供だった頃は、先生が「ドラクエをしている」と言っていて、「先生、ドラクエしているんだ」と親近感を抱きました。
RYU 意識して子供と「雑談」するだけでも違うと思います。子供と一緒に流行りものの話をするのも面白いですよ。どんなアーティストが好きなのかを聞いて、それを調べて「この歌詞いいよね!」と伝えるのもいいし、「YouTubeでは、何を見てるの?」「Tiktokはやってるの?」とか、話題をつくるのもいい。そんな他愛のない会話から、子供が見えてくることもあります。
ケンカは主体性のある行為
ハヤトカゲ 僕としては、ぜひとも「ケンカの仲裁」をお勧めしたいです。ケンカって、人間として主体性がある行為でしょう? 実際に教育に熱い想いを持っている若い先生方と話していると、「ケンカの仲裁って大事ですよね……。でも、どうすればいいのかが分からないんです」という声を聞きます。
AKI 確かにケンカという場面は、その子の「人間である部分」が最も顕著に出ます。この時期に学ばなければならないこともあるので、僕ら側も全力で対応せざるをえない……。だからこそ、教師として成長できる場面だと思います。
RYU 僕が「ハヤトカゲが言っていたこと、本当だ!」を最初に体験したのは、ケンカの仲裁の場面でした。でも、ケンカの仲裁って、やっぱり事前にノウハウを教えてもらっていないと厳しいな、とも感じます。

人間関係の悩みを子供は隠す
ハヤトカゲ 子供が親に語る「不登校の表向きの理由」として多いのは、「大きな音がつらい」とか「先生と合わない」といったものです。音に対しての感覚過敏や教師との関係の問題であれば、子供は親に打ち明けやすいからです。
でも、本音を聞いていると、子供たちが学校に行きたくない理由の根底には、必ず子供同士の人間関係の問題があります。
そして、子供にとって、友達との関係で苦しんでいることを一番知られたくないのが、親なんです。友達との関係がうまくいっていないことを、子供は基本的に親には隠します。
これは僕の持論ですが、人間関係で受けた傷は、人間関係の中でしか癒やせません。
だからこそ、ケンカをはじめとする子供同士のトラブルを仲裁する「技術」を、教師が持っていなければなりません。その「技術」を持っていれば子供の心の傷を悪化させずに済みますし、子供たちにトラブルの中で互いに理解し合う体験をさせ、傷を癒すことも可能です。
それくらい、子供にとって「ケンカ」は重要で、意味がある行為だと、僕は考えています。
ケンカの仲裁は、教師にとって必須の「技術」です。
ハヤトカゲは、ケンカの仲裁は、教育のプロとして必須の「技術」だ、とハッキリ言い切りました。
確かに、人間関係のトラブルの仲裁が上手な先生がいてくれれば、子供たちは安心して友達と関わることができるでしょう。集団としての成長の初期段階においては、そんなクラスこそが安心安全な場だと言えるはずです。
さて、そこで気になるのがケンカを仲裁する「技術」の具体です。その点については、次回に深掘りしますので、どうぞお楽しみに。
教師の最重要スキル「ケンカの仲裁」。その具体的ノウハウを3ステップで解説
取材・文 /楢戸ひかる
花まるエレメンタリースクール 「メシが食える大人に育てる」花まる学習会が運営するフリースクール。これからの時代に必要な力を”体験”を通して”五感”を使って身に付ける。不登校の子、不登校でなくても才能を伸ばす新たな学びの場を探している子が通っている。HPは、コチラ。インスタグラムは、コチラ。

