梅雨の時期がチャンス!! 4年「雨水の行方と地面の様子」【理科の壺】

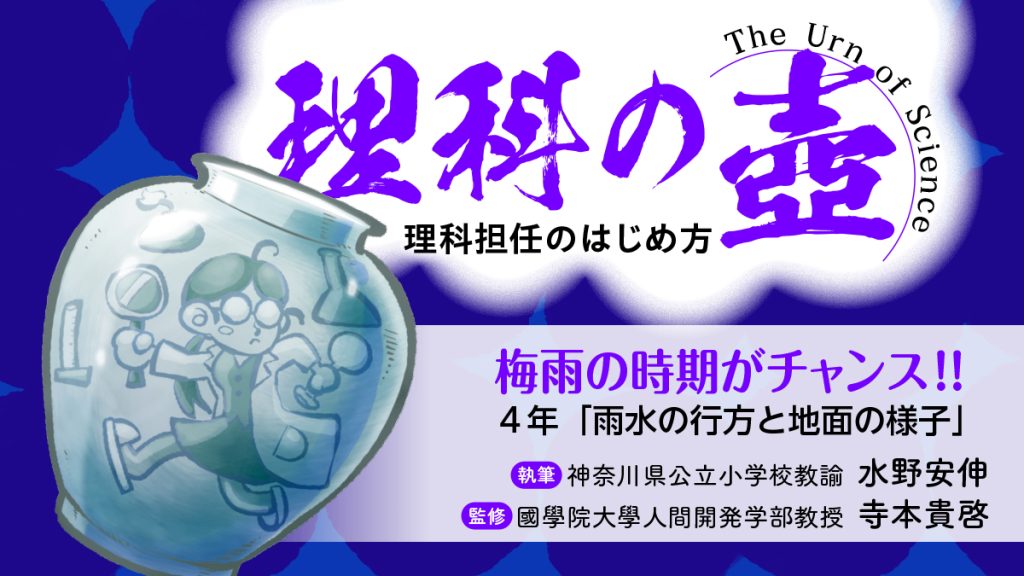
雨の日は残念に思うことが多いですが、理科の「雨水の行方と地面の様子」は数少ない、雨をありがたく思う機会ですね。雨待ちにすると計画通りに授業が進まないこともあり、どのような天気でも対応ができるようにしなければいけない単元でもあります。今回は体育の授業と絡めて、校庭の水はけについて考えてみましょう。優秀な先生たちの、ツボを押さえた指導法や指導アイデア。今回はどのような “ツボ” が見られるでしょうか?
執筆/神奈川県公立小学校教諭・水野安伸
連載監修/國學院大學人間開発学部教授・寺本貴啓
はじめに
理科の醍醐味の一つとして、「自然」について子どもたちが科学的に学んでいくことがあると言えます。自然を対象としていると、子どもたちも興味をもちやすい一方で、先生にとっては、「天候に左右される」ということもよく聞きますよね。観察に行きたいのに「雨が降ってしまった」、天気による1日の気温の変化を調べたいのに、「天気は思い通りにいかない」当然ですが、難しい悩みです。この悩みは理科だけではありませんよね。体育をやりたいのに…。最近は、「晴れているのに暑すぎて…」なんて言葉もよく聞こえてきます。天気単元で言えば、第4学年に「雨水の行方と地面の様子」があります。暑くて校庭での体育が実施できないときにも、この単元を学習するチャンスととらえましょう。
心得1 意外とよく知らない、「校庭の水はけ」
自然に親しみ、理科の見方・考え方を働かせ、見通しをもって観察、実験を行うことなどを通して、自然の事物・現象についての問題を科学的に解決するために必要な資質・能力を次のとおり育成することを目指す。
小学校学習指導要領解説 理科P12
⑴ 自然の事物・現象についての理解を図り、観察、実験などに関する基本的な技能を身に付けるようにする。
⑵ 観察、実験などを行い、問題解決の力を養う。
⑶ 自然を愛する心情や主体的に問題解決しようとする態度を養う。
ある日の朝、出勤すると、前夜の雨の影響により校庭には水たまりがありました。
「今日は1時間目が体育なのに」
そう思ったのは先生だけではありませんでした。私は水たまりがあることから石灰でラインを引くことをせず、今日の体育は中止と判断しました。1時間後、子どもたちが登校し、
「1時間目の体育は無理かな」
と話をしていました。教室は校舎の4階にあり、ベランダから校庭の全体が見渡せます。
「あれ、いつのまにか水たまりがない」
と気づきました。子どもたちは、
「水たまりがないから体育ができる」
「でも、地面がぐちょぐちょのはず」
と意見が分かれたので、実際に校庭の地面の様子を確かめに行きました。
「今日はリレーの学習が最後だから、どうしてもやりたい」
と言う子もいましたが、最終的な判断は、
「リレーゾーンにぐちょぐちょが残っている」
「長靴で来た子もいるから中止」
でした。
「こんなに水たまりがなくなるのが早いなら、普通の靴でくればよかった」
と言う子がいる一方で、
「いつも遊んでいる公園はもっと水たまりがなくなるのが早いよ」
「私が遊んでいる公園は、今日は放課後も水たまりだから遊びに行けないな」
という対話が始まりました。水たまりがなくなることは常識ですが、校庭、公園と、場所によって水たまりがなくなる早さについては深く考えたことがないようです。
後々になってですが、2時間目に体育をしているクラスがあったことを知り、
「そこまで乾いていたんだ」
と子どもたちには驚きだったようです。

