「3人組での話合いに挑戦しよう」対話型授業と自治的活動でつなぐ 深い絆の学級づくり #5

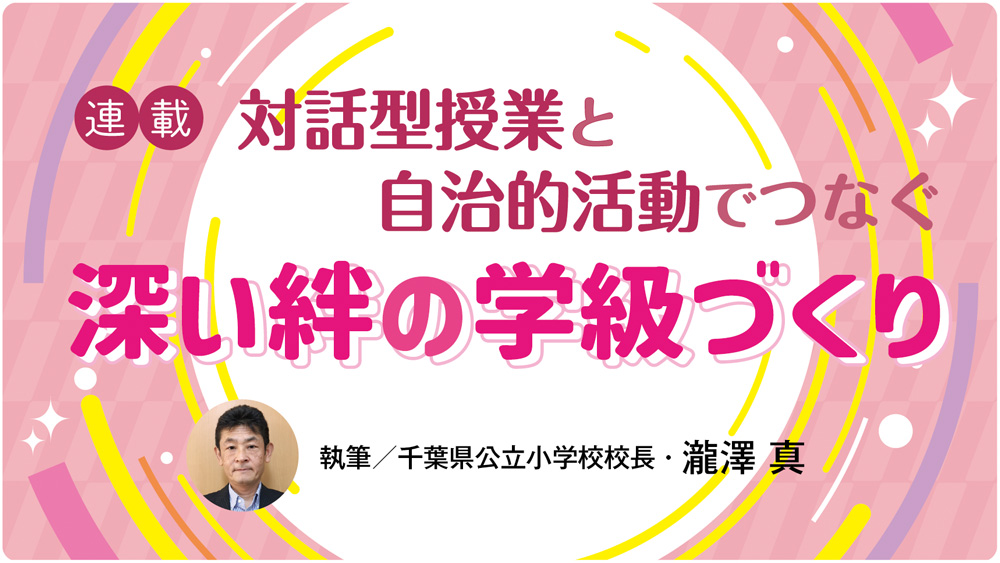
コロナ禍以降、コミュニケーションに苦労する子供や人間関係の希薄な学級が増えていると言います。子供たちが深い絆で結ばれた学級をつくるには、子供同士の関わりをふんだんに取り入れた対話型授業と、子供たちが主体的に取り組む自治的な活動が不可欠です。第5回は、「3人組での話合い」について丁寧に解説します。
執筆/千葉県公立小学校校長・瀧澤真
目次
ペア対話に慣れたら、次のステップへ!

ペア対話には十分に慣れたでしょうか。
毎回の授業で1回はペア対話を取り入れると、1日で5回はできます。とはいえ、授業内容によってはペア対話ができないこともあるでしょうから、少し控えめにして3回とします。
新学年が始まっておおよそ3か月。授業日数は、50日は超えていると考えると、3回×50日=150回はペア対話ができているはずです。
よく言われることですし、自分の経験則としてもそうだと思えるのが、どんなことであれ、100回くらい行うと定着してくるものです。
例えば、辞書を引く取組も、100回くらい行えば、授業の進行に支障のないくらいに素早く引けるようになります。
ペア対話をやろうと思っていたけど、そういえばまだ50回くらいしかやっていないな。そんな方は、ぜひともまずは100回を目指してください。
私は時々、出張などで担任不在の教室に飛び込みで授業をさせてもらいます。すると、日々ペア対話に取り組んでいるクラスはすぐに分かります。話し慣れているのです。話題を設定し、「では、隣同士で話し合って」と言えば、すぐにやりとりが始まります。
逆にほとんど取り組んでいないクラスは、話が弾みません。一見よく話し合っているなと思っても、実際には一方の子供がずっと話をしているということもあります。それでは、話合いが深まっていくはずもありません。
ですので、質は問わずに、まずはペア対話100回を目指しましょう。
そして、それが達成できたら、今回のステップ、3人組での話合いに進みましょう。
3人組での話合いは複雑
3人組での話合いは、ペア対話に1人加えるだけ。そんなに変わらない。そんな認識だと、うまくいきません。
2人だとその関係性は3通りです。
・A=B どちらも同等
・B>A Bのほうが有利
・A>B Aのほうが有利
ここに1人加わったらどうでしょうか。
「A>B>C」という関係もあれば、「A=B>C」もありますね。ここで全ての組み合わせを挙げなくても、1人増えただけで何倍もの関係性が生まれることが分かると思います。
こうしたことから、3人組になると、複雑な関係性が生まれ、それによって話に深まりが出るのです。ぜひ3人組での話合いも、積極的に取り入れてほしいと思います。
ただし、関係が複雑になるために、ペア対話と同じ要領でやろうとしても、話合いがうまくいかないこともあるのです。そこで、慣れるまでは型を与え、その通りに話し合うようにさせます。

