分数の教材理解に大切なことは「分数とは、子供が何を学ぶ学習なのか」【「系統」を見通し、学年ごとに押さえる! つまずきなしの「分数」指導法 #13】
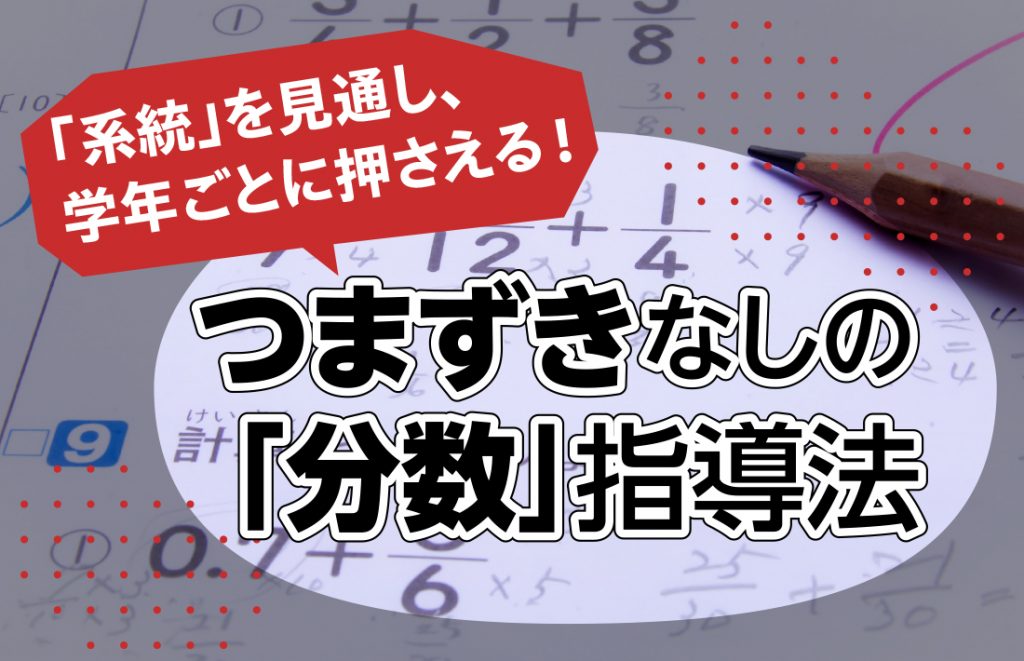
この連載では、2学年~6学年までの分数の授業づくりについて、新潟市立上所小学校の志田倫明教諭に、系統性を踏まえながら説明していただいてきました。最終回となる今回は、その学習をふり返りながら、授業づくりをしていく上で志田先生が重要だと考えることなどについてお話しいただきたいと思います。
目次
良い授業づくりには「教材研究」が重要

これまで分数の授業づくりについて、10数回にわたって説明をしてきましたが、私自身もまだまだ足りないところがあります。ただ結局は、教師が分からないことは子供に指導することはできません。ですから、より良い授業づくりをしていく上で重要なことは、やはり「教師の教材研究」に尽きると思います。
教材研究には大きく2つの視点があって、一つは学習内容つまり指導内容を理解するということで、もう一つは子供の分かり方を理解するということです。
まず指導内容を理解していくときに大切なことは、指導内容を主語にして一言で話してみることだと思います。つまりは「分数とは、子供が何を学ぶ学習なのか」と簡潔に話してみることで、指導内容の価値や本質が明確になるということです。このシリーズで出てきた内容で言えば、「たし算というのは、何を学ぶのか」「かけ算というのは、何を学ぶのか」と話してみるわけです。「たし算とは、同種同単位のものをたすという原理原則を学ぶのだ」「かけ算というのは、比例を前提とした倍を学ぶことなのだ」と、その学習を一言で説明してみる努力をすることが大切だと思います。
そうして、一言で説明しようと思いながら指導内容を見てみるとしましょう。例えばたし算ならば、1学年から6学年までずっとありますから、それらについて考えてきたときに、「何だ、たし算って結構、同じところがあるんだな」ということが見えてくるでしょう。そうやって気付いた指導内容の価値であり、学習内容の本質であるものを、一言で説明する努力をすることが大事だと思います。
ちなみに、「たし算とは、同種同単位のものをたすという原理原則を学ぶのだ」と私は説明しました。しかし、それも含めて今回、連載で紹介してきた内容については、私が私の理解、私の考えを説明したものです。しかし、これについては正解があるわけではありませんから、視点の当て方によっても、指導内容の価値が変わってくることがあります。例えば今回の説明の中で、分数の用い方によって分割分数、量分数、単位分数、割合分数、商分数と分けましたが、これも異なる分け方をする見方もあるくらいです。
ですから、誰かが言ったことをうのみにし、あたかも正解のように受け売りで言うのではなく、自分で「この指導内容にはこんな価値があるんだろうな」と考えたことを説明することが大切なのです。

