保護者を炎上させないための対応術|校長なら押さえておきたい12のメソッド #3

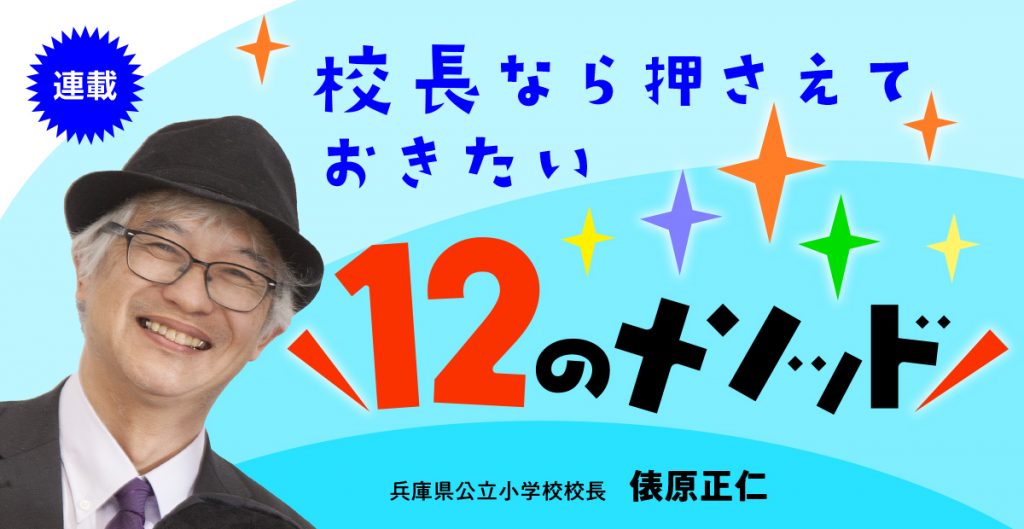
新任や経験の浅い校長先生に向けて、学校経営術についての12の提言(月1回公開、全12回)。校長として最低限押さえておくべきポイントを、俵原正仁先生がユーモアを交えて解説します。第3回は、「保護者を炎上させないための対応術~打たれ弱いZ世代教師に伝えるべきこと~」を取り上げます。
執筆/兵庫県公立小学校校長・俵原正仁
目次
1人で悩むな。力を借りて、先手必勝!
昼休み、一人の若い先生が、連絡帳を持って、不安そうな表情でやってきました。
学生時代、それほど叱られた体験がない人も多い若い世代は、私たちが思っている以上にクレームに対する耐性が低いことがあります。保護者からの(私たちから見たら)ちょっとしたクレームで自信をなくして必要以上に落ち込んでしまったり、自分を守ろうと逆に攻撃的になってしまったりするのです。管理職としては、そうならないように、あらかじめ手を打っておかなければいけません。ただ、起こってもいないクレームに対して具体的な指導を行うことはできません。そこで、私は、とりあえず次の1つのことを徹底するように伝えます。
保護者から何か言われたら、同じ学年の内藤先生か管理職に相談してくださいね
1人で抱え込むことなく、周りに相談する
ということです。周りの先生がいっしょに取り組むことで、若い先生が1人落ち込んで元気をなくしてしまうことや逆ギレして事態がさらにひどくなる可能性が低くなります。今回、この若い先生が私に相談に来たということは、私の話をしっかり受け止めて実行してくれているということです。
どうしましたか?
連絡帳に書かれている内容は「自分の子が友達から無視をされているようだ」というものでした。相談に来た先生の話は続きます。
子供たちを呼んで話を聞いてみたのですが、どうやら辻さんの誤解だったようです。辻さん自身も納得していました。
連絡帳を見て、すぐに行動したようです。このように、すぐに行動に移していたら、めちゃくちゃほめてください(まだの場合は、すぐに行動に移すように話をしてください)。
すぐに子どもたちに話を聞いたことは素晴らしい。ばっちりですね。
はい。内藤先生に相談したら、「すぐに子供から話を聞きましょう」とアドバイスしてくれたので……。話もいっしょに聞いてくれました。
私は4月の職員会議で、「子供の話を聞くときは複数で対応してください」とお願いをしています。学年の先生もきちんと対応してくれているようです。
すぐに相談したこともよかったですよ。で、何を聞きに来たんですか?
連絡帳の返事をどのように書いたらいいのか、アドバイスをもらいに来ました。内藤先生が教室にいなかったので……すみません。
トラブル的には対応済みで、すでに解決しているようなものです。ただ、改めて連絡帳に書こうとすると、どう書いていいのか分からなくなってしまったようです。実際、中途半端な書き方をすれば、保護者の不安をあおってしまいます。丁寧に指導した経過を書く余裕がないような時は、無理して書く必要はありません。次のように話しました。
連絡帳の返事をどのように書くか迷うような場合は、電話連絡してください。文字だけの連絡帳よりも、こちらの言いたいことが伝わります。
若い先生はうなずきながら聞いています。
できれば、今すぐにかけた方がいいと思いますよ。
電話連絡なら放課後にかけると思っていたでしょう、「今からかける」という言葉に対して、少し驚いた表情をします。そして、次のように続けて伝えました。
「今回の場合、すでに解決しているようなものですし、早く連絡して、お母さんを安心させてあげた方がいいと思いますからね。すぐに対応してくれたと、先生の株も上がるはずです。
それに、もしかしたら辻さんは納得していなくて、家に帰ってから不満を言うかもしれません。自分の子供の不満を聞いた直後に、『解決しました』という電話がかかってきたら、逆に不信感をもたれます。だから、辻さんが帰ってくる前に事情を説明した上で、『辻さんも納得したようですが、また様子を見てあげてください』と連絡しておいた方がいいということです」

この言葉を受けて、若い先生は、すぐに電話連絡をしました。素早い対応にお母さんも喜んでいるようです。
既に、電話で話をしているので、連絡帳の返事は、「ご連絡ありがとうございました。引き続き、学校でも様子を見ていきます。また、何か気になることがありましたら、ご連絡ください」で十分です。いつものお決まりの文章です。これなら、すぐに書けるはずです。
AかBか……決断をしなければいけない状況。さぁ、どうする?
放課後遅くなっても、辻さんのお家から「実はうちの子は納得していなかったみたいです。もう一度話を聞いてください」という電話はありませんでした。一件落着です。

「お疲れさまでした。すぐに解決できてよかったですね。これも、先生の対応が早かったからです。これからも、今日のような感じでがんばってくださいね。すぐに内藤先生に相談したこともとてもよかったです。ただ、次に何かあった時、近くに相談する人がいないことがあるかもしれません。そして、そのような状況で、すぐに、AにするかBにするか決断を迫られることもあります。その時は、自分にとって大変そうな方、つまり、面倒くさいなぁと思う方を選んでください。例えば、電話連絡か家庭訪問かで迷ったとします。この場合は、家庭訪問を選択します。面倒だなと思いながらも、頭に家庭訪問が浮かんだということは、どこか引っかかるところがあるということです。その違和感を無視してはいけません。私は、この判断基準で後悔したことは一度もありません」
そもそも、本当に何の心配もなく必要性がないのであれば、家庭訪問という選択肢が頭に浮かぶことはありません。うまく言語化できなくても、何か気になることがあるからこそ、その選択肢が出てきたということです。私の体験上、大丈夫だと思うけど(思いたいけど)、なんか違和感がある……という時に、その違和感を無視していい結果になったことは、ほぼありません。
迷った時は、大変そうな方を選ぶ
アントニオ猪木さん流に言えば、「迷わず行けよ。行けばわかるさ」ということです。
ちなみに、自分が選んだものが期待した結果にならなくても、私が後悔しない理由は、「たぶんBを選んでいたら、もっとひどい目にあっていただろう。よかった。これぐらいですんで……」と思うようにしているからです。こう考えることで、必要以上に落ち込むことなく、前向きにがんばってみようという気になることができます。

