今どき教育事情・腑に落ちないあれこれ(その5) ─国語科教材表記論「分かち書き踏襲症」と「漢字敬遠症」─ 【野口芳宏「本音・実感の教育不易論」第64回】

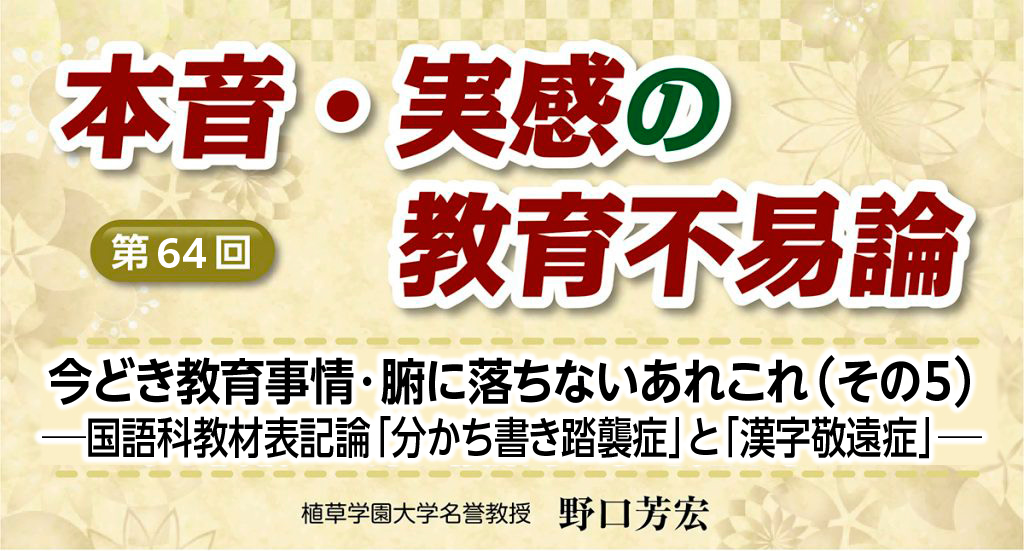
教育界の重鎮である野口芳宏先生が60年以上の実践から不変の教育論を多種のテーマで綴ります。連載の第64回は、【今どき教育事情・腑に落ちないあれこれ(その5)─国語科教材表記論「分かち書き踏襲症」と「漢字敬遠症」─】です。
執筆
野口芳宏(のぐちよしひろ)
植草学園大学名誉教授。
1936年、千葉県生まれ。千葉大学教育学部卒。小学校教員・校長としての経歴を含め、60年余りにわたり、教育実践に携わる。96年から5年間、北海道教育大学教授(国語教育)。現在、日本教育技術学会理事・名誉会長。授業道場野口塾主宰。2009年より7年間千葉県教育委員。日本教育再生機構代表委員。2つの著作集をはじめ著書、授業・講演ビデオ、DVDなど多数。

「腑に落ちない漢字指導の現実」と題して、前号に次を述べた。
1、小学校から高校までの国語勉強会(オンライン 240回超)
2、漢字が多く読めることの重要性(読めない漢字が多い苦痛)
3、読字力の形成原理は「早くから何回も」(幼児も漢字を読む)
4、漢字の読字力向上は石井方式(幼児でも新聞が読める)
5、幼児の音読・作文コンクール異聞(二つの全国コンクール)
上記の内容を要約すると、
ア、多くの漢字を読む力をつけることが国語学力の基底になる
イ、この読字力は漢字板書によってかなりの効果を生む
ウ、その実践は簡単であり、幼児教育界では多くの実績を上げている。
幼児の音読、作文の全国コンクールが長い歴史を持って続いている。
エ、これらの事実が学校教育では無視、否定されていて残念だ。
というようなことになる。本稿はこれらを受けて話を進めたい。
目次
6、仮名文字表記上の不便
ある幼稚園長の体験談である。
靴箱の記名を平仮名で示したのだが、間違えて他の場所に入れてしまう例が絶えない。そこで漢字で表記したところ、間違いがなくなったというのである。
これは、漢字が読めるようになったというよりは、漢字の方が異同を見分けるのに容易である事実を示している。平仮名はどの字も同じように見えてしまって識別が困難なのであろう。
石井勲先生は、ハト、はと、鳩の三つの表記を見せ、一定時日を経てその記憶、識別の率を調べたところ、漢字表記の「鳩」が最も多くの幼児に読めた事実を報告している。
これは、単純な仮名文字よりも複雑な漢字の方が相互の差異の識別にはむしろ有利、簡単であることの証左とも言えるだろう。
書字力という面からは明らかに仮名文字の方が容易、単純であるが、読字、差異の識別という面からは複雑な漢字の方がかえって識別上は容易だということを示している。
どなたの報告かは忘れたが「めやね」と板書して先生方に示し、「どんな意味か」と問うてみたところ、殆どの教師が何のことか分からない、と答えたそうである。私も何のことか分からなかった。実は「芽や根」のことだと知らされた。そのように書いてくれれば誰だって一目見れば得心がいく。
以下は、よく知られている例であるが、これも仮名書きであることによる不便さの好例であろう。
「にわにはにわにわとりがいる。」
この表記の意味を即座に理解する人は大人でも少ないだろう。いくらか迷ってから、ははあ、と得心するのが普通だろう。言うまでもないが、
「庭には二羽鶏がいる。」
という意味である。
これらの例からも分かるように漢字表記を早く取り入れることが、国語学力を高める得策なのだということは自明とさえ言えるのではないか。その故にこそ、日本語の表記法は「漢字仮名交じり文」と定められているのであろう。適切に漢字と仮名を交ぜて書くことによって読み易くなり、意味が分かり易くなるのである。
ところが、学校教育の現場では漢字の提出、指導、習得、活用についてはかなり及び腰で、なるべく控えめにしようとする空気が強い。そのような考えの教師が圧倒的に多いので子供の漢字の読字力は常に低いままである。このことが、国語の読解力を低迷させている最大の要因ではないかというのが私の考えである。如何であろうか。

7、分かち書き不要論
一年生から二年生の教科書の上巻までは、大方の教科書出版社が「分かち書き」を採用している。「分別書き」「分け書き」とも呼ぶそうだ。「文章を読みやすく理解を容易にするため」とその目的が述べてある。出典は日本国語教育学会編『国語教育辞典』(朝倉書店 2001年8月刊)である。
分かち書きは、明治17年(1884)の『読み方入門』(文部省編)で採用し今に続いている、とある。この解説の中に「通常使用している漢字仮名交じり文では、漢字が意味のまとまりの役目をしているので、分かち書きの必要は起こりにくい。仮名が多く漢字の少ない文章およびローマ字の場合にその必要が出てくる。」という一節がある。「通常使用している漢字仮名交じり文」という文言に注目したい。そこでは「分かち書きの必要は起こりにくい」とある。つまり、「分かち書き」は「通常」の表記法ではないのである。低学年の一時期の、「仮名が多く漢字の少ない文章」の場合にのみ必要なのだ。
ということは「通常の漢字仮名交じり文」にすれば不要だということになる。また、「ローマ字」の文では必要である、ともある。英文はアルファベットなので続けて綴ったら全く意味が分からなくなるので、単語ごとに区切ることが必要になるのである。これは当然だ。
明治17年というのは、学制が頒布されて10年ほどの時期である。以下は全く私的な想像だが、日本が寺子屋から学校に切り替える時期には欧米の学校制度を参考にせざるを得なかった事情がある。欧米のテキストは全て「分かち書き」である。寺子屋のテキストは中国の『大学』や『実語教』であり、それらは分かち書きではない。そこで文部省は分かち書きという新しい表記方式を真似て採用したのではないか。本来日本語の通常表記は分かち書きを採らない。学校という新しい制度の中で誕生したらしい「新しい表記方式」は、漢字が使われる大人の日常であれば当然不要な表記法になる。
低学年における「分かち書き」が、国語学力形成上有益、有効であるという実証データはあるのだろうか。漢字敬遠論者が、欧米の表記法に出合って、その真似をし、それがずっと踏襲されているだけのことではないのか。いずれも私的な妄想だろうか。
学制頒布から150年も続いてきた「分かち書き」は本当に有効であるのか、という問題提起はこれまでになされたことがあったのか。不明にして私はそれを知らない。──にもかかわらず、「分かち書き」は、「教科書用国家検定規準」(昭和27年、文部省告示)の中に次のように書かれている由だ。
「低学年においては、字間がじゅうぶんにとられ、また、分かち書きなどによって語間もじゅうぶんにとり、意味がよく読み取れるようにくふうしてあるか」──と。
「わかち書き」などによって意味がよく読み取れるようにくふうしてあるか」と書かれているが、「意味がよく読み取れるような」工夫と言うのなら漢字仮名交じり表記にするのが得策なのだ、と私は考えている。
「しばらくすると、ありは、せっかくはこんだたねをすの外にすてています。すてられたたねからは、もともとついていた白いかたまりが、なくなっています。どうやらたねはたべないようです。」
これは意図的に分かち書きをせずに私が書き改めた教材文である。これを意味が分かるように音読する、あるいは音読できる力こそが大切なのだ。それを「分かち書き」によって、「意味がよく読み取れるようにくふうしてある」ようにすると、国語学力の中核となる「語形認知力の形成」を妨げることにならないか。
かかる理由によって、私は分かち書きは止めた方がよいと考えている。輿水実先生は、「現在、小学校の二年まで、あるいは三年まで教科書におこなわれている分かち書きは、かなが多くて読みにくいこと、読みの入門的段階であることなどから、便宜に切ってあるのであって、語形認知を重く見るよりも、文としての読みやすさを重く見ている。」(『国語教育用語辞典』明治図書 1960年6月刊)と述べている。 分かち書きは、便宜上の一策であり、語形認知を重く見たものではない、ということなのだ。これは非常に重要な指摘である。
8、私の社会実験的挑戦
A
17 毎晩お風呂に入り、体を清潔にします。
(1日の疲れと汗を、洗い流しましょう。)
18 手や足の爪は、短く切っておきます。
(長い爪は、人を傷つけたり、病気の元をつくったりします。)
19 大人の時間と、子供の時間は違います。
(夜更かしはしません。睡眠不足は、成長の妨げになります。)
上記Aの表記は一般社会で通用する「漢字仮名交じり文」であり、学年配当漢字表に準拠してはいない。
上記Aの引用文は『日本の美しい言葉と作法』というA5判、156ページの「音読・道徳教科書」と銘打たれた冊子の一部分である。子供は当然全く読めないので、教師が音読し、子供は教師の音読に合わせて読字箇所を指でなぞりながら、追い読みをする。見開き2ページを一週間繰り返して読むので、週末にはどの子も全文が音読できるようになる。声を揃えて音読をするだけの連続だが、文章の内容は日常生活の望ましいあり方を盛りこんであるので、道徳教育にもなる。まさに「音読・道徳教科書」なのだ。
B
すみれは、なかまを ふやす ために、いろいろな ばしょに めを 出そうと します。
しかし、じぶんでは、
上記Bはある国語教科書の二年上巻の一部分である。平仮名ばかりの分かち書きである。
ごく一般的には、引用Aが高学年用、Bが低学年用の文章だと思うだろう。実はそうではない。前者Aを毎日使って読んでいるのは実は幼児なのだ。15年前に刊行したものだが、一度採択されるとずっと使われることになり、幸いにして累計20万部になる。
幼児からも、保護者からも、漢字が多くて困るとか、分かち書きがされてないので読みにくいという類いのクレームは15年間に1件もなく、好評のうちに採択園も少しずつだが増えている。
幼児が嫌がったり、親が園側から、押しつけられたと言ったりした報告は皆無である。どこの採択園でも、子供にも保護者にも大いに喜ばれているのが実状なのだ。
◆
社会実験的挑戦などと大層な言い方をしたが、15年に亘る私の実験、というよりも「実践」は、私に次のような事実を明示してくれたと言うことができるだろう。御批判を期待している。
ア、読字力という限定をするならば、漢字と仮名の難易に差はない。仮名が読み易いのは文字数が50字と少ないからに過ぎない。
イ、漢字の数は仮名よりも遙かに多い。漢字は表語文字なのでそれは当然のことだ。つまり、多くの漢字が読めるということは多くの語彙を習得することなのだ。読字力を増強することはそのまま語彙力の増強になる。
ウ、漢字を読む力つまり読字力の増強策のポイントは「早くから何回も」に尽きる。漢字には年少の頃から、繁く出合わせることが得策だ。
エ、分かち書きというのは、学校の低学年教科書にだけ登場する無意味、無益、有害の表記法であり、止めても何の損失もない。私の15年の実践で証明済みだ。
オ、現在の検定済みの低学年国語教科書の表記は、易しすぎる。国語学力の低迷は、教科書教材の過保護的優しさに起因する。
執筆/野口芳宏 イラスト/すがわらけいこ
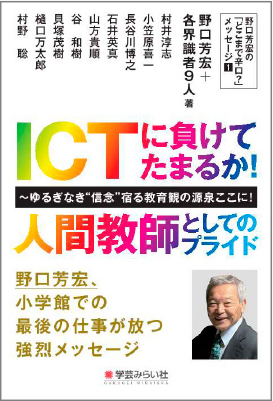
<野口芳宏先生、新刊のご案内>
この直言連載の中から9編分を厳選した野口芳宏先生の最新書籍『ICTに負けてたまるか 人間教師としてのプライド ~ゆるぎなき “信念” 宿る教育観の源泉ここに!』(学芸みらい社)は2月14日発売予定です。ぜひ、お読みください。

