菊池省三の「コミュニケーション力が育つ教室づくり」 #46 菊池省三解説付き授業レポート⑪ ~千葉県鎌ケ谷市立初富小学校5年1組<前編>

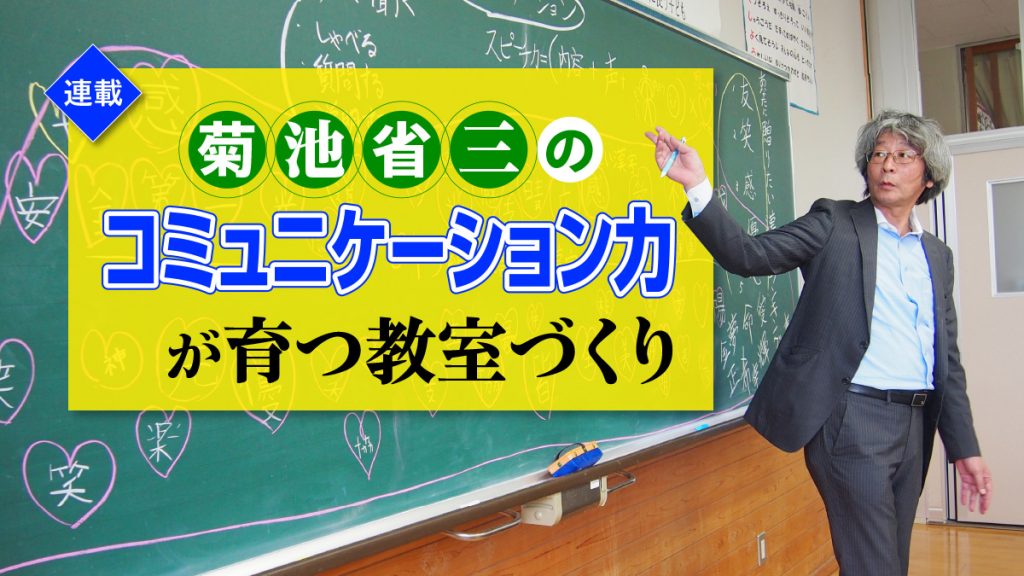
全国各地での飛び込み授業を、菊池先生ご自身の解説付きでレポートする好評シリーズ。
今回からは、鎌ケ谷市立初富小学校の5年生への授業をレポートします。菊池省三の「子供を見る目」を学びたい方にとって、必読の連載です。
目次
“世界一に挑む” と子供たちをあおる
「お久しぶりです!」
菊池先生が教室に入るなり、子供たちは大きな拍手とスタンディングオベーションで迎えた。
「今の2倍の笑顔と拍手で、もう1回迎えてもらっていいですか?」
と菊池先生が子供たちをあおると、みんな大乗り気で拍手をやり直した。
「落ち着くときは落ち着く。盛り上がるときは盛り上がる。公の場にふさわしいみんなの行動や態度、仕草、言葉の使い方ができる。すごいことですね」
菊池先生が、黒板の左端に<公の言葉>と書きながら、子供たちをほめた。
「担任の先生から『5年1組は世界一を目指している』と聞いたので……」
と言いながら、<公の言葉>の上に<世界一に挑む>と書き加えた。そして、「挑む」という字を指さしながら子供たちに尋ねた。
「読める人? 3秒間だけ、隣の人と『あんた本当に読めるか?』と言い合いましょう」
3秒後、菊池先生が最後列の子を指名した。
「教室入り口のウェルカムボードに、『聞くではなく聴く』と書いてありました。まだ授業が始まったばかりでも堂々と手を挙げる。ドキドキ感に負けずに言おうとしているあなたの気持ちの部分も、みんなは “聴く” から、拍手の準備をしているんだ。だから世界一を目指せるんだね」
「いどむ、です」
「正解です。では、挑む人はやる気の姿勢を見せましょう」
菊池先生の声かけに、子供たちがぴしっと背筋を伸ばした。
![]()
「世界一に挑む」とあおることで、授業の質を高め、明日からの学びをさらに加速させていくねらいを込めました。
いくつもの問いかけに、自分らしさあふれる答えが
菊池先生がA4判の白紙を全員に配ってから、黒板の真ん中に書いた。
<3・22>
「これは、何の数字でしょうか?」
菊池先生が尋ねると、挙手した3人が答えた。
●すごい人と真ん中の人と苦手な人の割合
●5年生最後の日
●一人ひとりの気持ちの強さ
「先生が考えていたのは、2番目に発表してくれたことです。聞いていて覚えていて言える人?」
菊池先生が聞くと、多くの子が手を挙げた。
「そう、みなさんの5年生最後の日。3月22日が修了式です。こんな風にいろいろと聞いていきますね」
菊池先生はそう説明すると、スキップしながら最前列の男子のところに行き、笑顔で尋ねた。
「どうしようもないことを聞いてもいい? 『あなたは何ですか?』と聞いたら、みんなは何と答えますか」
みんな大笑いした。
![]()
固い空気の教室で固苦しく問いかけても、子供たちは答えません。スキップをしたり、笑いながら問いかけたり、教師が自ら自由な雰囲気をつくることで、子供たちに笑顔があふれ、「何を答えても大丈夫そうだ」という柔らかい空気が生まれます。
こうした微細なパフォーマンスを常に意識することも大切です。
3秒間、隣の人と意見を交換し、縦列の子が発表した。
●自分は自分
●人間
●女の人
●動物
菊池先生が2番目の答えを言った子のところに行きながら、
「先生が考えていたのは、彼が言ったことだけど、何て言ったか……」
言い終わる前に、全員が勢いよく手を挙げた。
「人間です」
指名された子が発表すると、菊池先生が、
「そうですね。じゃあ、もう一つ聞いていい? 『あなたはどこにいますか』と聞かれたらどう答えますか?」
とさらに尋ねた。
指名された縦列の子たちが答えた。
●地球
●千葉県鎌ケ谷市初富小学校の5年1組
●教室
●日本
●惑星
さらに、菊池先生が地球の写真を見せた。
「地球には、人間以外の生き物がどれぐらいいるのでしょう。当てずっぽうでいいから、3秒間隣の人と予想し合いましょう」
●5種類
●1億
●1500
●100兆
●2000億
●1兆
●2億
●322種類
菊池先生が最後の回答の子に、
「おお、さっきの3・22とつないだんだね。そのように表現できる教室はいいね。先生にとって、新しい学びになりました」
と話しかけた。
![]()
最初に書いたことと結び付け、深読みした子の発想に驚かされ、素直な私の気持ちをみんなに話しました。
ともすれば教師は、自分が意図したこと以外の発言をした子を無視してしまうことがあります。その子らしい視点が感じられるこうした発言は大いに認め、ほめましょう。
「わかっているだけで175万種、わかっていないものも含めると300~500万種いると言われています。
地球上にはいろんな種類の生き物がいますが、人間にしかできないこと、他の生き物にはできないことはどんなことでしょうか」
菊池先生が問いかけると、子供たちの表情が真剣になった。

