不登校児童生徒数約30万人! その学びをいかに保障するか?【連続企画 多様化する選択肢 令和時代の不登校対策 #00】
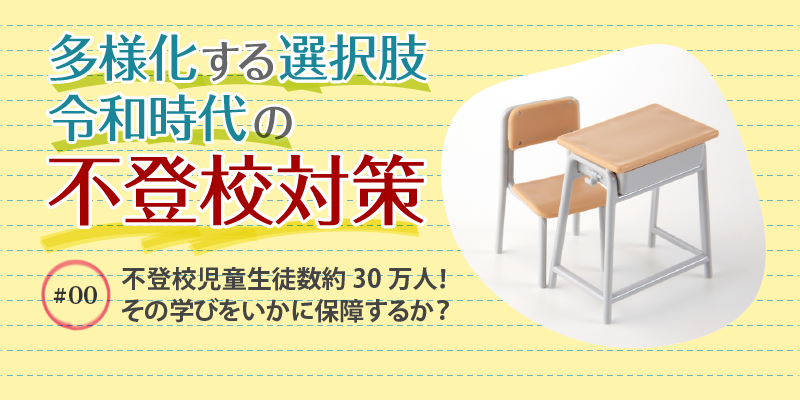
近年、増加の一途を辿る不登校児童生徒数。文部科学省が打ち出す「誰一人取り残さない学びの保障」を実現するために、学校と教員にできることは何なのか。識者の提言と各現場の事例から考えていく。
本企画の記事一覧です(週1回更新、全8回予定)
●連続企画#00 不登校児童生徒数約30万人! その学びをいかに保障するか?(本記事)
●連続企画#01 不登校対策では、子どもだけでなく保護者への支援も重要/奈良女子大学教授 伊藤美奈子
●連続企画#02 「誰一人取り残さない」学校づくりが不登校対策につながる/神奈川県横浜市立山内小学校
●連続企画#03 不安な子も自信がついた子も、みんなが心地よい学校づくりを目指す/岐阜県岐阜市立草潤中学校
●連続企画#04 生活困窮の子どもにとって学校は最後の砦。だからこそ、先生はぜひ周りを頼ってほしい/株式会社キズキ代表取締役社長 安田祐輔
●連続企画#05 不登校者数は2年で10万人増。問われる公教育の在り方/ストップいじめ!ナビ 副代表理事・事務局長 須永祐慈
●連続企画#06 学齢や状態に合わせて子どもを支援。分教室型の不登校特例校も開校/東京都調布市教育委員会
●連続企画#07 メタバースを活用して、不登校児童生徒に居場所と学びの機会を提供/北海道帯広市教育委員会
●連続企画#08 「多くのチャンネル」と「匿名性」を確保し、子どもが安心できる社会を/名古屋大学大学院教育発達科学研究科教授 内田 良
増加の一途を辿る不登校児童生徒数
文部科学省が2023年10月に発表した「令和4年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果」によると、小・中学校における不登校児童生徒数は、小学校が10万5,112人、中学校が19万3,936人の合計29万9,048人。前年度から22.1%の増加となり、過去最多の数となった。
不登校の子どもの数はこのところ10年連続で増加しており、小学生は10年前の約5倍、中学生は約2倍に増えている。文部科学省が2020年度に行った「令和2年度不登校児童生徒の実態調査」では、学校に「最初にいきづらいと感じたきっかけ」として、小学校では「先生のこと」「身体の不調」「生活リズムの乱れ」などが、中学校では「身体の不調」「勉強が分からない」「先生のこと」などが上位に挙がっており、それぞれ「きっかけが何か自分でもわからない」という児童生徒も一定の割合で見られる。まさに不登校の要因は子どもによって様々であり、一人一人に寄り添った対応が求められる問題といえる。
●(学校に)最初にいきづらいと感じたきっかけ
文部科学省「令和2年度不登校児童生徒の実態調査 結果の概要」
【小学校】
29.7%…先生のこと(先生と合わなかった、先生が怖かった、体罰があったなど)
26.5%…身体の不調(学校に行こうとするとおなかが痛くなったなど)
25.7%…生活リズムの乱れ(朝起きられなかったなど)
25.5%…きっかけが何か自分でもわからない
【中学校】
32.6%…身体の不調(学校に行こうとするとおなかが痛くなったなど)
27.6%…勉強が分からない(授業がおもしろくなかった、成績がよくなかった、テストの点がよくなかったなど)
27.5%…先生のこと(先生と合わなかった、先生が怖かった、体罰があったなど)
(中略)
22.9%…きっかけが何か自分でもわからない

