いじめ 【わかる!教育ニュース#33】
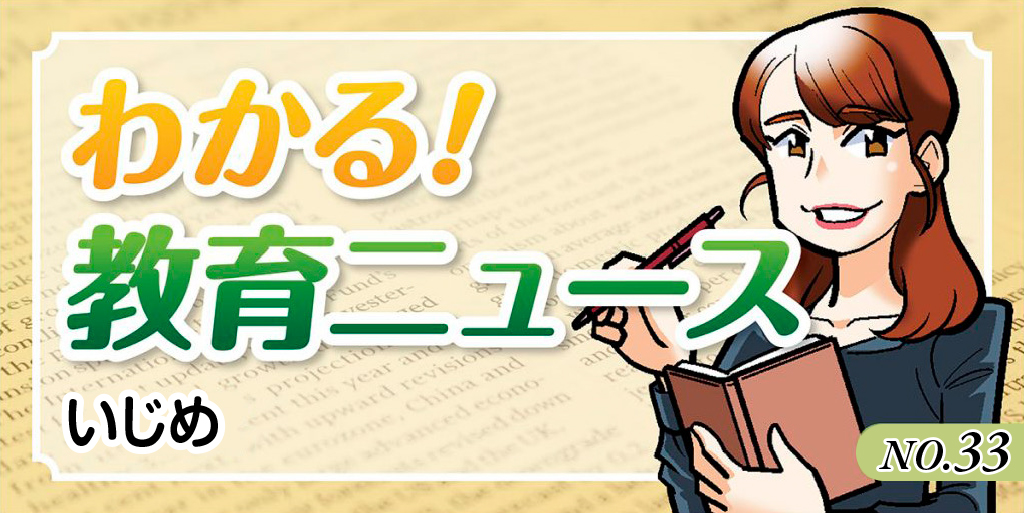
先生だったら知っておきたい、様々な教育ニュースについて解説します。連載第33回のテーマは「いじめ」です。
目次
こども家庭庁が「いじめ調査アドバイザー」制度を設ける
いじめの定義を示し、国や自治体、学校などがするべきことを定めた「いじめ防止対策推進法」ができて、10年経ちました。自殺の恐れや長期欠席など被害が深刻な「重大事態」には、学校設置者や学校などが、事実関係を調べる組織を設けることも義務付けています。と言っても、スムーズに対応できているものでしょうか。
こども家庭庁が「いじめ調査アドバイザー」という制度を設け、大学教員、弁護士、日本医師会や日本社会福祉士会の関係者など8人に委嘱しました。役割は、自治体や学校が重大事態の調査組織を立ち上げる際、委員の人選や中立で公平な調査の方法を第三者の立場で助言すること。アドバイザーが直接、調査に携わるわけではありません。
調査組織をつくろうにも、どう進めればよいのか悩む自治体もあるでしょう。一方で、組織づくりに手間取って調査にとりかかるのが遅れると、事実関係を確認するのがむずかしくなり、被害者の苦しみも増します。アドバイザー制度は、余分な時間をかけずに組織を立ち上げ、偏りのない調査ができるようにするのが狙いです。
小倉将信こども政策担当相(当時)も委嘱に当たって「調査の経験がなくて何をしたらよいか分からない、委員決定に時間がかかる、被害者側の納得が得られないといった課題が指摘されている」と問題意識を語り、アドバイザーが関わることで、調査につながる意義を説明しました。

