「ティーム・ティーチング」とは?【知っておきたい教育用語】
「ティーム・ティーチング」とは、単に複数の教師が授業や指導を担当するということに止まらず、教授(ティーチング、teaching)組織を改善するための一つの方式であると言えます。その普及の歴史を振り返るとともに、今後の課題について解説します。
執筆/茨城大学大学院教育学研究科教授・加藤崇英
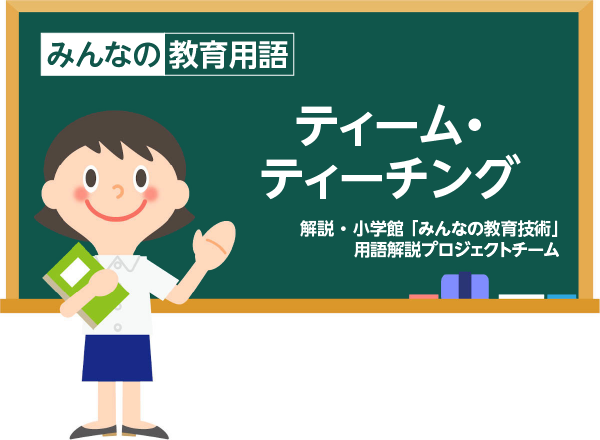
目次
ティーム・ティーチングの定義
今日、ティーム・ティーチング(team teaching)は、外来語(カタカナ言葉)として、直接このように呼ばれることが一般的ですが、頭文字をとって「TT(ティーティー)」と呼ばれるほか、日本に紹介された当初は、「協力教授」と訳されました。教師がティームを作って、協力して授業を行うことで、教育効果を高めようとする取組です。
ティーム・ティーチングの生みの親とされるアメリカのシャプリンによれば、ティーム・ティーチングとは、「授業組織の一様式で、教職員とかれらに割りあてられた生徒を含み、ふたりもしくはそれ以上の教師が、協力して、同じ生徒グループの授業全体、または、その主要部面について、責任を持つものである」としています。
学級制、学年制とティーム・ティーチング
ティーム・ティーチングは、単に複数の教師が授業や指導を担当するということに止まらず、教授(ティーチング、teaching)組織を改善するための一つの方式であると指摘できます。一般的に小学校や中学校の組織は学年と学級をベースに構成されています。中学校は教科で担当の教員が異なります(教科担任制)。小学校については、近年、高学年を中心に教科担任制を取り入れているところも多くなってきましたが、担任する学級においてすべての教科を担当する学級担任制が基本といえます。
しかし、一方でこうした学年制と学級制は、固定された授業形態や指導形式になってしまうことで、子どもの多様化や教育内容の高度化への対応が進まないことや、さらに様々な教育方法の試みを阻害し得ると指摘されてきました。よって、一人の教師と1学級という関係性に柔軟性を与え、教育効果を高めるべく、とりわけ教師がティームを構成し、複数で指導にあたるティーム・ティーチングが研究され、実践されてきました。

