そろそろ教師としての専門性を高めていきたいのですが…(後編)【教師の悩みにピンポイント・アドバイス 田村学教授の「快答乱麻!」#7】

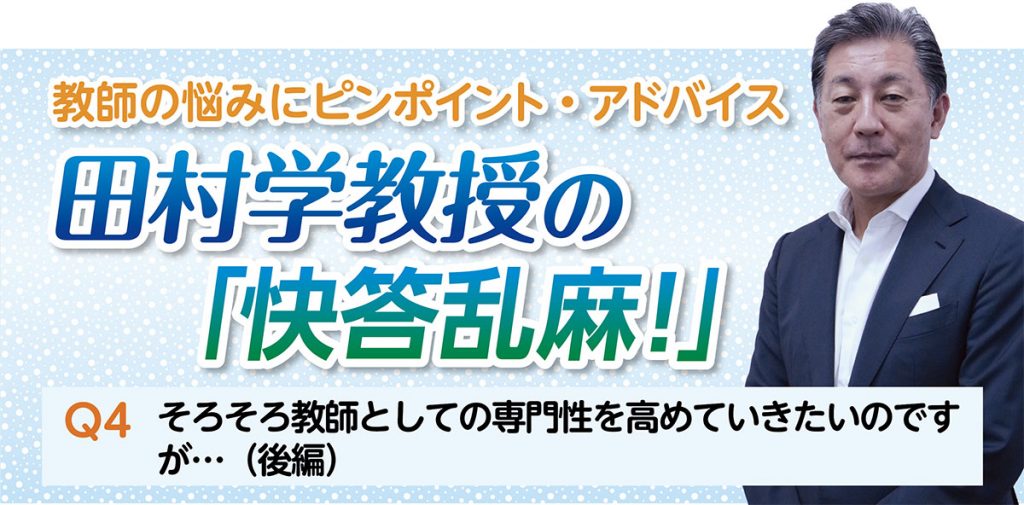
先生方のご相談について、國學院大學の田村学教授にお答えいただくこの企画。今回も前回に引き続き、若手の先生が専門をどうしようかと悩んでいるご相談に対して「快答」していただきます。
※
Q4 新採用から3年を経て授業づくりにも学級づくりにも校務にも慣れてきました。そうすると、取り組むべきこと、取り組んでみたいことがたくさん出てきて、何に力を入れて専門分野にしていけばよいか悩んでいます。どのように考えたらよいでしょうか?(小学校・20代)
「教科指導」のミクロな視点と「教育課程」全体のマクロな視点をもつ
A 前回は、教師力を高めたいという悩みに対して、教師の資質・能力とは、情熱・教育的愛情と人間力と専門性であることや、前の2つは備わっているという前提で、教師に求められる専門性とは「教科指導の専門性」と「教育課程の専門性」の2つだということを、私自身の経験を通してお話ししてきました。今回はそれに続いて、「教科指導の専門性」と「教育課程の専門性」の2つのバランスの重要性について、話をしていくことにしましょう。
まず多くの先生は、専門性を身に付けるという時には、これまでの多くの先生方と同様に、「教科指導の専門性」を磨くことから入っていくと思います。ただ「教科指導」から入っていくと、教科内容を優先するような頭になりがちで、「いかにこの知識を確実に身に付けさせるか」とか、「いかにこの~的思考力を身に付けさせるか」ということに意識が向きがちになるということだけは意識しておくことが必要でしょう。そのような考え方は教科のもつ特性でもありますから、それ自体は悪いものではないのです。しかし、子供の学びや学習のありよう自体を優先して見ていくと、そのようなミクロな視点だけになってしまってはいけないと思います。子供の学びとはもっと総合的なものであり、教育課程全体を俯瞰するとか、教科横断的な学びを考えるといったことが必要です。そのように「教科指導」のミクロな視点からと、「教育課程」全体のマクロな視点からの両方をもてると、結果的に子供の学びを深めていく上で非常に有効になるでしょう。
ご質問にある、何を専門にするかということですが、おそらく教科指導については、先生自身のそれまでの学びの経験とか、得意不得意とか、赴任した学校や地域でどんな研究が盛んかといった環境とか、そういったものに関係して選択がなされていくことだろうと思います。それは大事にした上で、そこがすべてではなく、もう少し広く教科横断とか教育課程といった視点をもって、子供がどのように学んでいるかを考えていってほしいと思うのです。それを仮に教科で選択すれば、(これは私が言うので当然のことと思われるでしょうけれど)生活科や総合的な学習の時間は、そういう視点をもてるものだと思います。そのように、極めて教科内容を基盤としている教科と同時に、子供の生活を基盤としている教科にちょっと着眼するだけで、ずいぶんと変わってくるのではないでしょうか。
ただし、「両方を突き詰めてください」と言われても困るでしょう。ですから、「自分は算数でいこう」と思っていたとしても、そこにむやみに突き進んで走りきるのではなく、「子供の学びはどうなっているかな」とか、「カリキュラムはどうなっているかな」「他の教科とどう連動しているかな」という気持ちをわきに置き続けておけると、これからの時代に期待される教師になれるのではないかと思います。

