「シンギュラリティ」とは?【知っておきたい教育用語】
情報テクノロジーの飛躍的な発達によって、2045年に到来すると予言されている「シンギュラリティ」。その意味や、将来を見据えた学習のポイントについて解説します。
執筆/信州大学教育学部助教・小倉光明
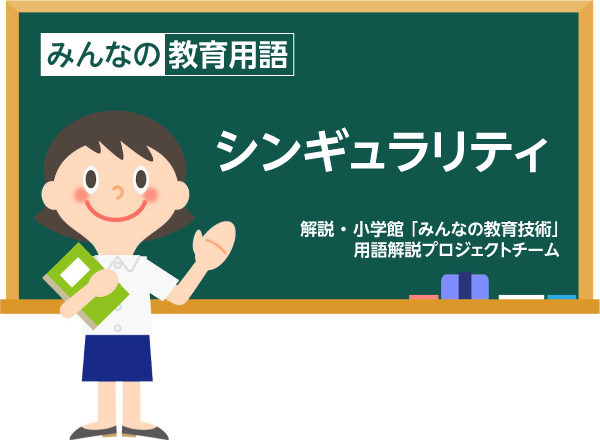
目次
「シンギュラリティ」とは?
シンギュラリティ(特異点)は2006年のレイ・カーツワイルの著書「The Singularity Is Near(邦題:ポスト・ヒューマン誕生)」で世界的に注目されるようになりました。そこでは、情報テクノロジーの指数関数的な発達によって、2045年にシンギュラリティが到来するとしています。指数関数的な発達を予言するのは、これまでの過去のテクノロジーがそのように進歩してきたという分析と、AIがAI自身をさらに改善することができるようになることを想定しているためです。
よくシンギュラリティは「AIが人類を超える」といった意味合いで表現されます。しかし、著書の中では、シンギュラリティを「人間の能力が根底から覆り変容する時」と表現しています。これは、レイ・カーツワイルがGNR(遺伝子、ナノテクノロジー、ロボット工学〈AI〉)の技術を合わせて、シンギュラリティが到来すると考察しているためです。
例えば、「ナノボット(非常に小さな機械装置)が血流の中を流れることで健康増進につながる多くの仕事をやってのける」といった表現がされており、GNRの統合的な視点で議論していることがわかります。この本の発表は2006年であり、2012年にはディープラーニングが画像認識でブレイクスルーを起こしています。それによって急速にAIへの関心が高まっている現代では、AIの側面がより強くクローズアップされているようです。
著作の内容はSFのように感じますが、レイ・カーツワイル自身が文字読み取り機(OCR)等の発明者であり、これまでにコンピュータがチェスのチャンピオンに勝つことを予言するといった先見の明が、世界的にも認められています。レイ・カーツワイルが予言した通りのシンギュラリティが起こるかどうかはわかりませんが、急速に時代が変化していることは事実です。未来のために今何を教育することが必要かを考えるヒントに、シンギュラリティはなるかもしれません。
急速な社会の変化に伴う教育の変化
現代は、シンギュラリティが予言されるように、急速で複雑かつ広範囲な変化が進んでおり、「将来の変化を予測することが難しい社会」を迎えています。そのため、OECDのキー・コンピテンシーに代表される問題解決・問題発見・創造力、論理的・批判的思考力、メタ認知・適応的学習力などの汎用能力の重要性が高まっており、2017(平成29)年度告示の学習指導要領では、各教科の「見方・考え方」が明記されました。
今学習した知識は、子どもたちが大人になるころには陳腐化しているかもしれません。それゆえ、身につけた見方・考え方を働かせつつ、時代に応じて新たな知識・情報を獲得し、自分の考えを形成して問題解決していく力を身につけていくことが重要です。そのためには、ICTの活用やプログラミングを含めた情報活用能力が必要不可欠です。常に未来を予測して今の教育を考えることが重要であると言えます。

