コロナ禍の学校閉鎖は学力低下を生むか(下) ー長いスパンで克服されていくものだー【野口芳宏「本音・実感の教育不易論」第41回】

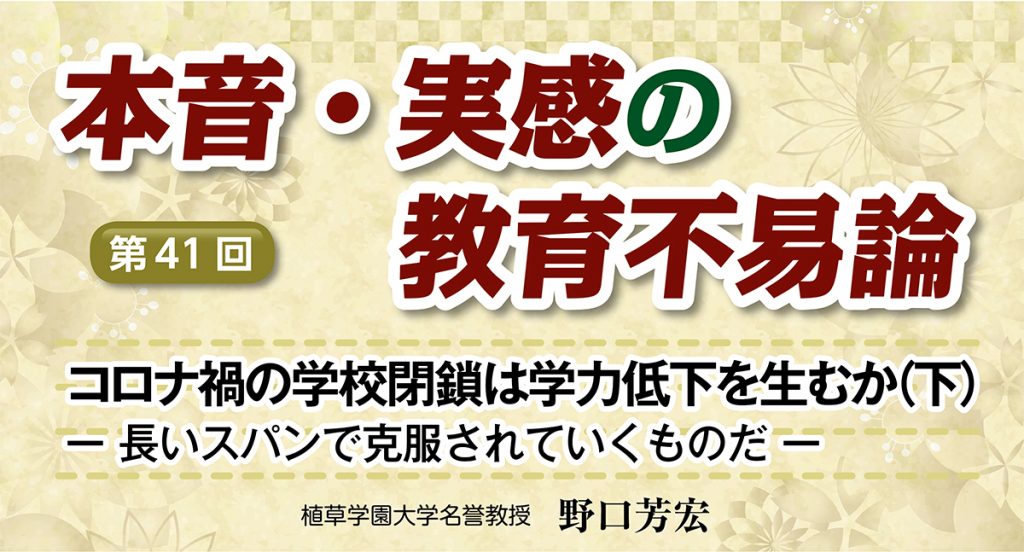
教育界の重鎮である野口芳宏先生が60年以上の実践から不変の教育論を多種のテーマで綴ります。連載の第41回は、【コロナ禍の学校閉鎖は学力低下を生むか(下) ー長いスパンで克服されていくものだー】です。

執筆
野口芳宏(のぐちよしひろ)
植草学園大学名誉教授。
1936年、千葉県生まれ。千葉大学教育学部卒。小学校教員・校長としての経歴を含め、60年余りにわたり、教育実践に携わる。96年から5年間、北海道教育大学教授(国語教育)。現在、日本教育技術学会理事・名誉会長。授業道場野口塾主宰。2009年より7年間千葉県教育委員。日本教育再生機構代表委員。2つの著作集をはじめ著書、授業・講演ビデオ、DVDなど多数。
目次
6 国民学校1年に入学
昭和16年(1941)、国民学校令によって小学校は国民学校になった。初等科6年、高等科2年、合わせて8年間が義務教育である。「皇国の道にのっとる教育」を目指して教科書も全面改訂された。但(ただ)し、高等科は戦況悪化の為「無期延期」となったから、実状の義務教育期間は6年間である。
『日本歴史大事典』の中で寺崎昌男氏は、
(前略)行学一体、師弟一如等の理念が強調されたものの、実際には軍隊式の体罰・懲罰の横行、行事偏重などがみられた。(中略)近代戦としての総力戦に即応する人間形成システムの総合的再編を象徴する学校であった。
と書いているが、その教育を受けた私の実感とはかけ離れている。
「行学一体」「師弟一如」の「理念強調」は全く思い出にないし、さりとて「体罰・懲罰の横行」や「行事偏重」も実感にない。
私は、国民学校初等科1年入学が昭和17年で、戦況は2年生から急速に悪化し、4年生の昭和20年8月15日に敗戦によって無条件降伏となり、戦争は終わる。
戦争が終わったのだから「平和」にはなったのだが、国民の生活の窮乏はむしろ戦後の2、3年の方が大きかったのではないかと思う。私は房総の田舎の農家に育ったので飢えというものの体験はないが、衣類や食生活の日常はきわめて貧しいものだった。
国民学校は、敗戦による学制改革によって昭和22年(1947)3月を以て廃され、4月からはいわゆる6・3・3制の新制小学校、中学校、高等学校に変わる。私は、国民学校初等科に1年生から5年生まで在籍し、新制小学校6年生を卒業して、新制中学校1年生に進んだ。一言で言えば、私の小学生時代は、日本の最大の混乱期だったということになる。少し、その辺りの子供事情を書いてみたい。
本誌の読者の大方は、昭和36年以降に生まれた方々で、戦時下の事情については殆ど御存知ないだろうから、ちょっと想像がつかないことどもも多かろうかと思う。

7 当時の小学生の日常
今は、太平洋戦争という呼称が正式とされているが、当初の正式名称である大東亜戦争の勃発は、昭和16年(1941)12月8日である。
開戦後の1年間、つまり私が1年生の頃までの日本は、連戦、連勝の戦況にあったが、2年生になる頃から日本の戦果は苦境に傾いていく。4月に山本五十六連合艦隊司令官撃墜死、5月にアッツ島守備隊玉砕、9月イタリア降伏、11月タラワ島守備隊玉砕。明けて昭和19年(1944)6月北九州初空襲、7月サイパン島玉砕、10月那覇大空襲、神風特別攻撃隊初戦果、11月東京大空襲(以下略)という具合である。この頃から都会の子供たちの田舎への避難が始まる。いわゆる「学童疎開」である。因みに、疎開というのは、「空襲、火災などの被害を少なくするため、集中している人口や建造物を分散すること」である。学童疎開の始まりは、都会が次々に狙われて空襲が日常化してくることを見越した対応である。
田舎の学校にも、都会からの転入児童がぼつぼつ増え、学校の裁縫室や作法室などには「集団疎開」の学童が仮住まいを始めた。私たち田舎の子供は教室で勉強もできたが、集団疎開の子供たちは教室がそのまま寝起きする生活の場であったから、どんなふうにして暮らしていたのだろうか。学校以外にお寺でも集団疎開の子供らを受け入れているところがあったが、親元を離れて暮らす寂しさや悲しさにか、校舎の陰で泣いている子供の姿を見かけることがあった。子供心にも、それは痛々しく哀れでたまらなかったことを思い出す。
そして、田舎にも、警戒警報や空襲警報が毎日出された。警報発令は避難上の至上命令で、直ちに一切の仕事を止めて一斉に子供たちは防空壕に向かって走った。
防空頭巾は、当初は座布団を二つ折りにして片側を布で縫いつけるという簡単なものであったが、次第に工夫されてやや薄手の、首から肩の部分を二つに裂いた形に改良され、毎日それを持って通学することが決まりになった。どの家も、家の近くの地下に穴を掘り、警報発令とともにそこに逃げこんで入り口を塞いだ。
学校の防空壕は地面を50㎝ほど掘り下げた縦横5mほどの素掘りで、雨が降ると水が溜まって池同然になった。
生活上の日用品は極度に不足していたから、履き物は下駄か草履で、雨が降れば全員裸足で通学し、教室に入る前には「足洗い場」で土を落として校舎に入った。上履きなどは見たこともなく、誰もが素足で教室や廊下をぺたぺたと歩いていた。それが日常だったので、誰もそれを変だともおかしいとも思わなかった。
疎開によって転入してくる子供の中には裕福な子もいたので、長靴などを持っている子もいたが、それはむしろ贅沢な「非国民」のすることと見られる風さえあった。
唐傘は、竹の骨に油紙が張られたものしかなく、「こうもり傘」と呼ばれた布製の傘などほとんど見ることもなかった。紙も油も不足していたので、ぼろぼろに破れた唐傘でも大事に使っていたし、それを笑ったり、からかったりする者もなかった。

