主体性、自主性、個性重視の功罪 ー明治生まれの父の教育想片ー【野口芳宏「本音・実感の教育不易論」第17回】

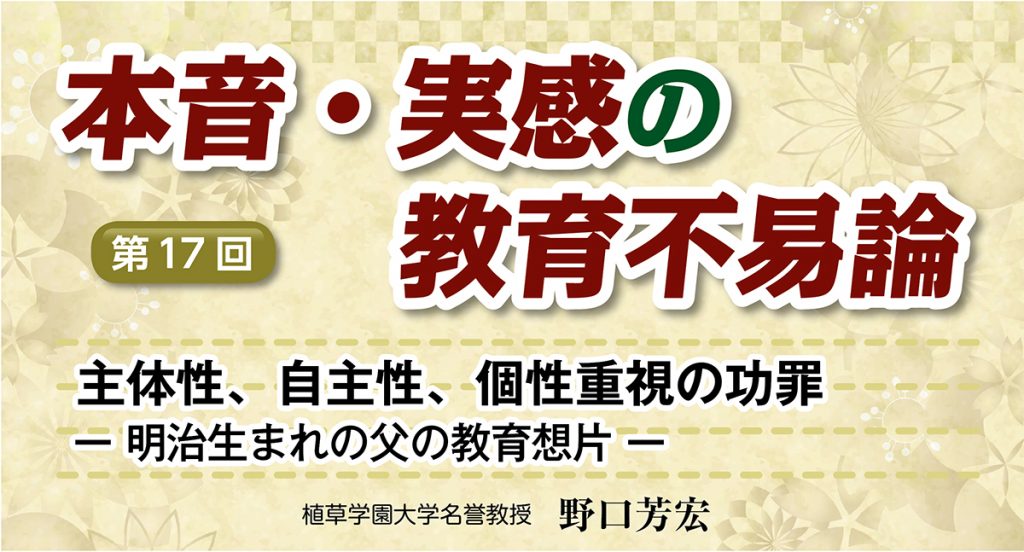
教育界の重鎮である野口芳宏先生が60年以上の実践から不変の教育論を多種のテーマで綴ります。連載の第17回目は、【主体性、自主性、個性重視の功罪 ー明治生まれの父の教育想片ー】です。

執筆
野口芳宏(のぐちよしひろ)
植草学園大学名誉教授。
1936年、千葉県生まれ。千葉大学教育学部卒。小学校教員・校長としての経歴を含め、60年余りにわたり、教育実践に携わる。96年から5年間、北海道教育大学教授(国語教育)。現在、日本教育技術学会理事・名誉会長。授業道場野口塾主宰。2009年より7年間千葉県教育委員。日本教育再生機構代表委員。2つの著作集をはじめ著書、授業・講演ビデオ、DVD等多数。
目次
1 父の愛を受けて
「出自」という言葉がある。「出どころ。うまれ」と『広辞苑』にある。「出自を明らかにする」などと使われる。人は、出自によってその人生を大きく形づくっていく。
筆者である私も例外ではない。「私事に亘って恐縮ですが──」などとよく言われるが、「私事」こそ、その人の人間形成に影響を与える最たるものとも言えるのではあるまいか。教育のありようを考える時に、自らの出自、家庭、生育歴を抜きにしては語れまい。私事に亘るが、それを通しての人間形成のありようについて改めて考えてみたい。
私の家は、代々婿養子が続いた。私の父は千葉県師範学校を出て、私の出た小学校の訓導として赴任し、縁あって一人娘の野口家に養子として迎えられた。私はその第一子として実に100年ぶりに野口家に生まれた男児である。一家の喜びは大変なものであったが、私は生来病弱で、人力車で往診をする医者を呼ぶ日々が続いたから、家では心配が絶えなかった。とりわけ責任感の強かった父の心痛は大きく、家族には極秘で、密かに名高い易者を訪ねてその要因を問うた。俗に、「寝釈迦」と尊敬されていた近在で高名な易者は、「宅地の東が大きく欠けているだろう」と言った。図星であり、父は大いに驚いた。「そういう家では長男は育たない」と寝釈迦は断言し、「宅地の改造」を促した。男の子が生まれても早逝した例もあったのを思い出した父は、小学校の教員を1年間休職した。そして、私の為に私有地を公道に寄付をして、宅地を東に拡張する大工事に挑んだ。私が4歳、父が31歳の時である。
易者の言が、果たしてどれほどの信頼性があるのか、その科学的根拠の程は私には分からない。だが、父のこの大決意と断行に対して、私は心の底から感謝している。「至誠神に通ず」などと言えば、時代錯誤とも、神がかりとも嗤われそうだが、現に私は82歳の今も健康に恵まれ、全国各地に出かけて先生方との学びを楽しんでいる。それが東宅地の拡張の功か否かは別として、そこまでして私の健康を守ろうとしてくれた父の愛に深い感動を伴って感謝している。父親という存在のありようを身を以て示してくれたものと思う。
さて、100年ぶりの男児として生まれ育った私は、最も強く父によって教育されたという実感がある。父は、大きな期待と責任感の下に私を可愛がり、大事にし、また、厳しくも育ててくれた。その父の教育のお蔭で今日の私がある、と私は確信している。
その私に対する父の教育のあり方を回想しながら、「教育の不易」というテーマを体験的に考察してみたい。いつものことながら、「本音、実感、我がハート」という発言モットーに基づく私見である。
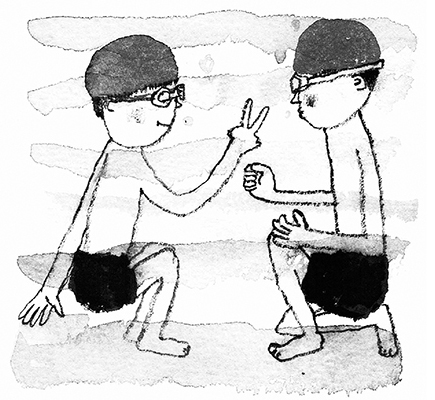
2 不機嫌を許さず
注意されたり、それを守らないと叱られたりということは、子供にとっていくらでもあることだが、それらは、子供にとっては決して嬉しいことではない。そんな時には、とかく子供は不機嫌になったり、膨れっ面をしたりしがちになるが、父はその点に関しては極めて厳格で、それを許さなかった。「何だ、その返事の仕方は!」「何だ! その顔は」と私を責めた。
自分の非を素直に認め、父の叱責を受容し、反省し、改めるという、子供としての真っ当なあり方、態度を父は強く求めた。それにもなお私が従わない時には、私の自分本位の我儘に父は容赦しなかった。時に鉄拳を振るうことさえもあった。それによって私は、絶対に父に逆らうことはしなくなった。「言葉で言って分からない時には、痛い目にあわせてでも分からせる」というところがあった。「ならぬことはならぬ」を父は貫いた。
叱られたりすれば食欲などなくなる。そんな時「食べたくない」などと私が言えば、「泣きながらでも食え」と父は言った。自分本位の不機嫌、個人的な不快を以て、他の人にまでそれを及ぼすことを許さなかった。「お天気屋は駄目だ」とよく言った。そう言う父は、ほとんど不機嫌という表情を見せなかった。叱る時に怖いのはむろんだが、それが済めば元の平常心に戻った。優しく、明るい父が日常であった。
そのように育てられることによって、私は従順で素直な子供にと成長した。それは大人になっても変わることはない。だから臍を曲げるとか、不機嫌な顔をするということは私の日常にはほとんどない。そのことによって、私自身は、おおむね快活であり、素直であり、楽しい日々を過ごせている。また、多くの人に愛される。結局は、私自身が幸せなのである。そのように育ててくれた父に心の底から有難かったと思う。

