「孝」の教育の復活、復興を ー日本人の自信と誇りを取り戻す為にー【野口芳宏「本音・実感の教育不易論」第13回】

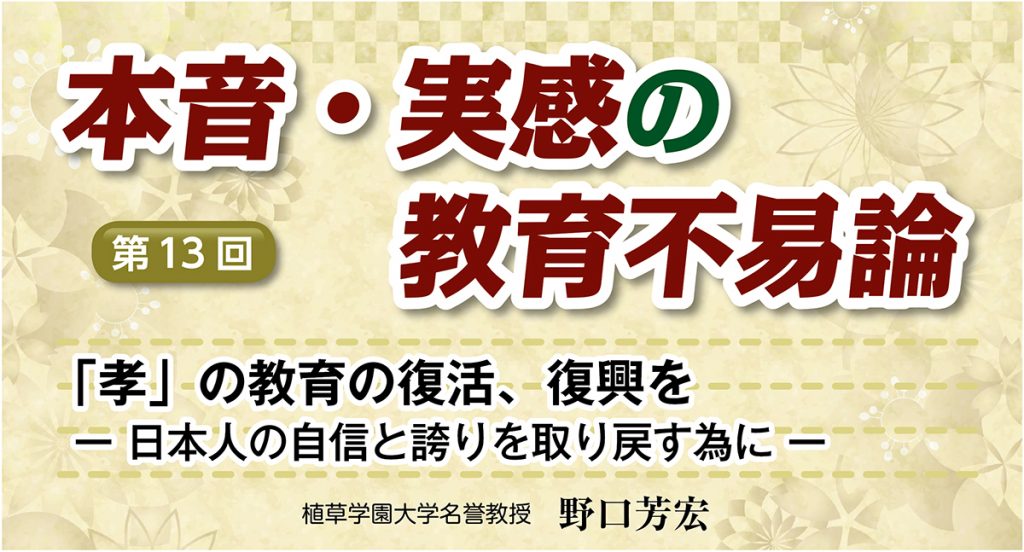
教育界の重鎮である野口芳宏先生が60年以上の実践から不変の教育論を多種のテーマで綴ります。連載の第13回目は、【「孝」の教育の復活、復興を ー日本人の自信と誇りを取り戻す為にー】です。

執筆
野口芳宏(のぐちよしひろ)
植草学園大学名誉教授。
1936年、千葉県生まれ。千葉大学教育学部卒。小学校教員・校長としての経歴を含め、60年余りにわたり、教育実践に携わる。96年から5年間、北海道教育大学教授(国語教育)。現在、日本教育技術学会理事・名誉会長。授業道場野口塾主宰。2009年より7年間千葉県教育委員。日本教育再生機構代表委員。2つの著作集をはじめ著書、授業・講演ビデオ、DVD等多数。
目次
1 今日のおとずれ何と聞くらむ
平成7年3月20日、オウム真理教による地下鉄サリン事件が発生した。「日本犯罪史において最悪の凶悪事件」とされている。主犯の麻原彰晃以下13名の死刑が23年間の歳月をかけて確定した。
この件について詳しく触れるつもりはない。私が最も心を痛め、関心を強くするのは、このような子どもを産み、育てた親の悲嘆、懊悩の深さである。
犯人らの苦しみや悲しみは当然本人が負わねばならぬことであり、その罪過を思えば同情の余地はない。だが、その親の苦悩について思いを致す時、犯人らは何という親不孝なことをしでかしたものだろうと思わざるを得ない。もはや定かな記憶ではないが、麻原の主謀が明白になった時、その親は夜逃げ同然にそれまでの住居から姿を消したそうである。とてもそのまま同じ居所に留まることはできなかったことだろう。
日本では昔からこういう事態を「世間に顔向けができない」という言葉で言い表してきた。子どもを犯罪者に育てようなどと思う親はあるまい。「良い子に」「良い大人に」しようと育ててきたに違いないのである。だから、死刑囚13名は、親の愛と期待を裏切って、親に大恥をかかせた大親不孝者である。「親の顔に泥を塗る」無礼この上ない行為である。
吉田松陰は、安政の大獄によって刑死するが、その処刑される時の辞世として知られる和歌がある。
「親思ふ心にまさる親心今日のおとずれ何と聞くらむ」
子どもが親を思う心よりもずっと深く大きいのが、子を思う親の心である。私の刑死の知らせを知ったらどんなに親は悲しむことになるだろうか。何とも申し訳ないことだ──との歌意である。
もしも、仮に──と思うのだ。麻原に、あるいは高橋克也に「親に心配をかけてはいけない」という思いが少しでもあったならば、あんな馬鹿げた凶悪な犯罪には及ばなかったのではないか──と。もしも、「親ほど有難い恩人はない。老後の親には少しでも安楽な生活をして貰いたい」という思いがあったならば、あのような大惨事を引き起こすような大罪を犯すことはなかったのではないか、──と。
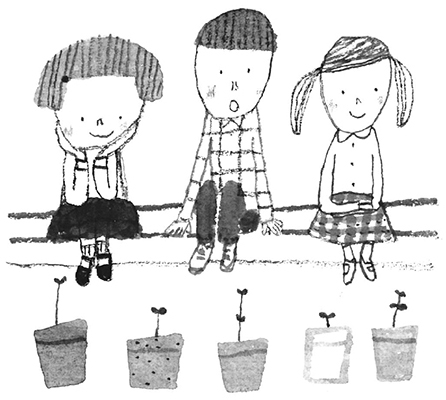
2 孝者百行之本也
この慣用句は『白虎通』に「孝、道之美、百行之本也」とあるものに依る、と『広辞苑』にある。その意味は「孝行はもろもろの善行の基である」ということだ。簡潔だが、その意味するところは大きく重い。この言葉の真実を深く思う。
また思う。「我カ臣民克ク忠ニ克ク孝ニ億兆心ヲ一ニシテ世世厥ノ美ヲ濟セルハ此レ我カ國體ノ精華ニシテ敎育ノ淵源亦實ニ此ニ存ス」という「教育ニ関スル勅語」の一節である。今風に言えば、「我々日本国民は、忠孝の二つの道を十分に体得、実践しつつ、みんなで心を一つにして長く今日に至るまで見事な成果をあげてきた。これこそが日本という国の真価、核心と申すべき国柄である。教育という営みを為す根本は、この誇るべき日本の伝統を守り育てていくことにあるのだ」とでもなろうか。
ここには、「忠・孝」の二つの徳目こそが、日本人の、日本国民の、最も中核の徳であるとの認識が見てとれる。「忠」とは、「真心。誠。忠誠。臣下としての本分を尽くすこと」である。一糸乱れぬ秩序はここから生まれてくるのだ。「孝」は、「親、祖先に敬愛と孝を尽くすこと」である。
今さら、なぜ教育勅語のように古めかしい文書を引き出してくるのか、という思いを抱く向きもあろう。だが、教育勅語という文書については大きな誤解がなされたままであり、どこかでその正しい理解を取り戻さなくてはならないと私は考えている。
「本音・実感の教育不易論」のテーマの下に若干の蛇足を許されたい。
ア、教育勅語は明治23年から昭和23年までの60年間、日本国民の共有理念だった。
イ、戦後3年間、温存された。まっ先に消されてもよかった筈だが、GHQもそのよさ、価値を否定できなかったのか。
ウ、戦前は英国をはじめ各国語に訳されて広く教典として尊ばれていた。
エ、日本国民の教育の原点、原理を簡潔、明快に示した熟議、熟考の古典。
オ、「之ヲ古今ニ通シテ謬ラス之ヲ中外ニ施シテ悖ラス」という、胸を張り自信に満ちた不変不動の国家的宣言。
上は、筆者の解釈、理解、所感であるが、この機会にぜひとも原典に当たってその真価を探ってみて欲しい。「教育勅語」という言葉そのものを知らない世代も増えてきている。また、名前ぐらいは耳に残っていても、直接自分の眼でそれを読んだ人は、ほとんどいないといってもよい現実がある。それにもかかわらず、教育勅語については「誤った国策の象徴」という誤解に基づく印象を抱いている教師も多い。本文を自分の眼で読むことなく悪い印象を持っているというのは、「そのように教えられた」のであり、最も警戒すべき理解の仕方である。

