田村学著『「ゴール→導入→展開」で考える「単元づくり・授業づくり」』刊行のお知らせ 第2回

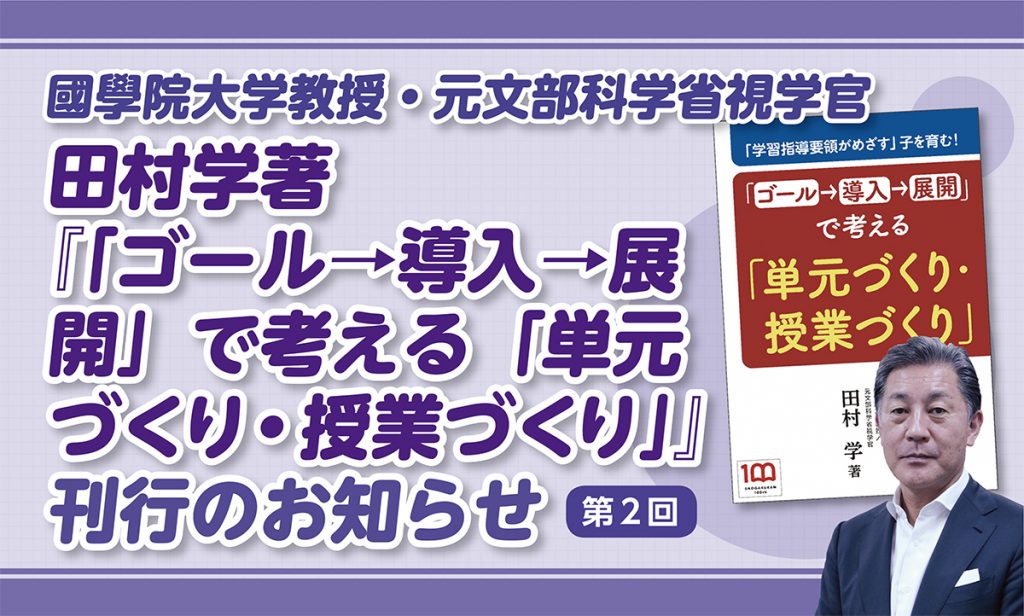
2022年12月1日に刊行したばかりの國學院大學・田村学教授の著書、『「ゴール→導入→展開」で考える「単元づくり・授業づくり」』(小学館)。前回は、この書籍の概要について説明しましたので、今回は主に書籍の全体構成やその意図について説明していきます。この書籍は大きく5章で構成をしていますので、その章ごとに説明をしていくことにしましょう。
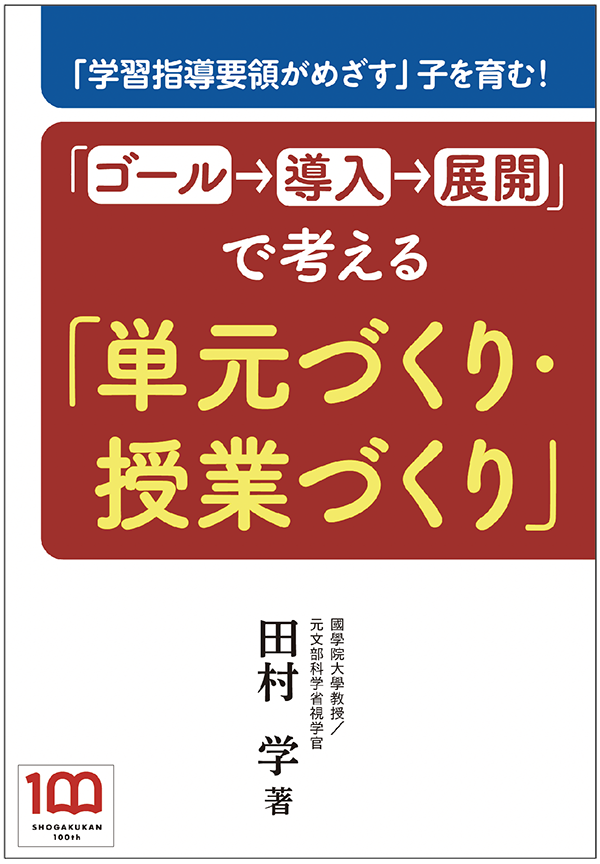
「学習指導要領がめざす」子を育む!
『「ゴール→導入→展開」で考える「単元づくり・授業づくり」』
田村 学 著
ISBN 978-4-09-840226-7
目次
「単元づくり・授業づくり」を考えるための大前提から具体的な方法まで
まず第1章は、「これからの学校や学校教育に求められているものとは?」です。「単元づくり・授業づくり」について具体的に考えていくことが、この書籍の主目的ですが、その前に読んで考えていただきたいのが、これからの社会において求められている学校や学校教育のあり方です。それはまさに、学習指導要領が現行のものに改訂された背景でもあり、これを知ることで学習指導要領が求めるものをより深く理解できるはずです。
前回も触れましたが、究極的には先生が担任する子供たちと自分自身の個性や実態に合った「単元づくり・授業づくり」ができるようになっていくことが理想だと思います。そのためには、「なぜそのような教育が必要なのか?」ということを理解することが必須でしょう。この章を読んで理解することが、先生の「単元づくり・授業づくり」は、より自由で豊かなものになるのだと思います。
第2章は、「学習指導要領が求める資質・能力とはどのようなものか?」です。これは、言うまでもなく学習指導要領が育成を求めているものです。経験が浅いうちはどうしても、目の前の各教科等の指導内容(端的に言えば教科書の内容)を、どう教えるかに目がいきがちです。しかし、その内容を指導することを通して、どんな力を育むかということこそが学校教育の目標なわけです。そこで、学習指導要領が求める三つの資質・能力をより分かりやすく解説しているのがこの章です。これをしっかり理解することで、次の章での「単元づくり・授業づくり」の実践もより確かなものになっていくことでしょう。
第3章は、「『単元づくり・授業づくり』はどのように行えばよいのか?」です。いよいよ、具体的な「単元づくり・授業づくり」の方法について紹介をしているのが、この章です。学習指導要領は、「単元や題材など内容や時間のまとまりを見通しながら」授業改善を図り、資質・能力を育むことを求めています。そこで、単元や授業をどのようにデザインしていけば、めざす資質・能力を育むことができるのか、より具体的な手順を紹介し、実践事例を通してさらに深く理解を図れるようにしています。この章をしっかり読むことで、ただ教科書をなぞるのではなく、子供たちの実態に合わせて自分なりに単元や授業をデザインしていく方法が見えてくることでしょう。

