「ウェルビーイング」とは?【知っておきたい教育用語】
「心身ともに健康で幸福な状態」を示す、ウェルビーイング(Well-being)。なぜ今注目を集めているのか、その背景を含めて考えていきましょう。
執筆/文京学院大学外国語学部教授・小泉博明
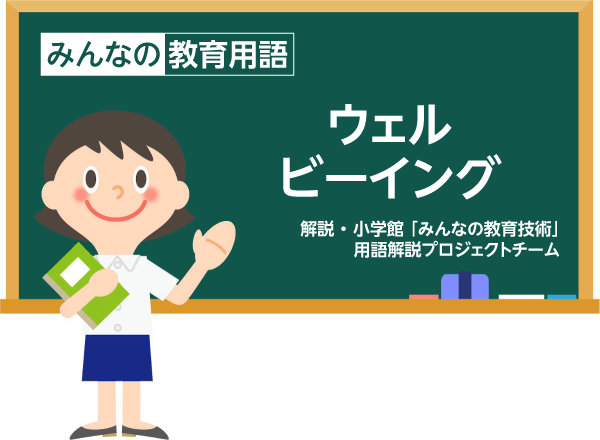
目次
「ウェルビーイング」とは
ウェルビーイング(Well-being)とは、「良好な状態」「心身ともに健康で、持続的に幸福な状態」という意味です。学校においては、子どもたちのウェルビーイングの実現をめざし、学習者が主体となる教育の転換が問われています。また、SDGsにおいてもウェルビーイングが重要です。
「令和の日本型学校教育(答申)」におけるウェルビーイング
「『令和の日本型学校教育』の構築を目指して~全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現~」(答申)において、ウェルビーイングは、次のように言及されています。
経済協力開発機構(OECD)では子供たちが2030年以降も活躍するために必要な資質・能力について検討を行い、令和元(2019)年5月に“ Learning Compass 2030 ”を発表しているが、この中で子供たちが ウェルビーイング(Well-being)を実現していくために自ら主体的に目標を設定し、振り返りながら、責任ある行動がとれる力を身に付けることの重要性が指摘されている。
「『令和の日本型学校教育』の構築を目指して~全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現~」(答申)
この「OECD ラーニング・コンパス(学びの羅針盤) 2030」“Learning Compass 2030”では、「教育の未来に向けての望ましい未来像を描いた、進化し続ける学習の枠組み」の中で「教育の幅広い目標を支えるとともに、私たちの望む未来(Future We Want)、つまり個人のウェルビーイングと集団のウェルビーイングに向けた方向性」を示しています。
また、OECDは、「PISA2015年調査国際結果報告書」においても、ウェルビーイングを「生徒が幸福で充実した人生を送るために必要な、心理的、認知的、社会的、身体的な動き(functioning)と潜在的能力(capabilities)である」と定義しています。教育再生会議でも「一人一人の多様な幸せと社会全体の幸せ(ウェルビーイング)の実現を目指し、学習者主体の教育の転換」と提言しています。

