リレー連載「一枚画像道徳」のススメ #13 函館港まつりに込められた想い|工藤美希先生(北海道公立中学校)

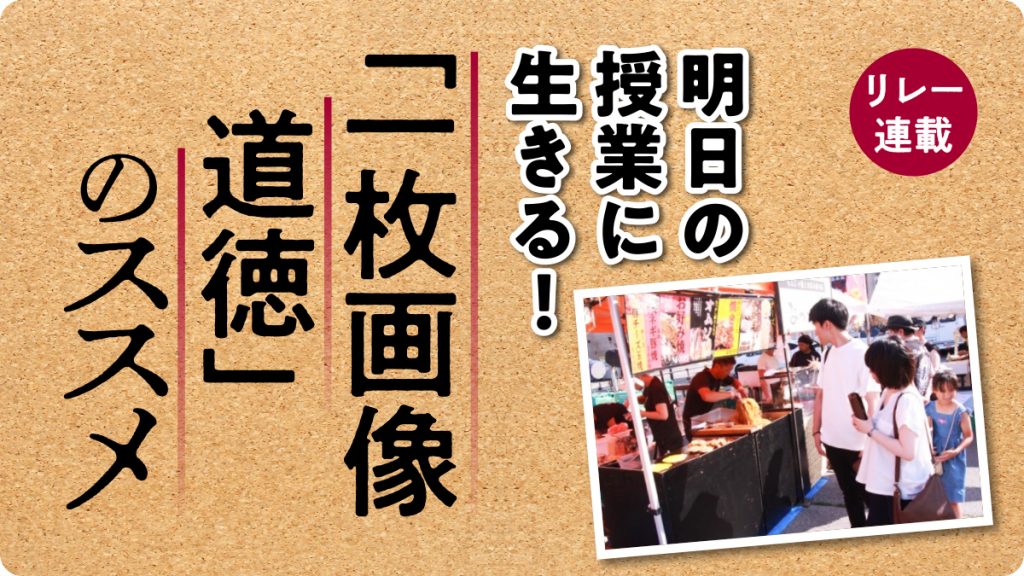
子供たちに1枚の画像を提示することから始まる15分程度の道徳授業をつくり、そのユニットをカリキュラム・マネジメントのハブとして機能させ、教科横断的な学びを促す……。そうした「一枚画像道徳」実践について、具体的な展開例を示しつつ提案する毎週公開のリレー連載。第13回は工藤美希先生のご執筆でお届けします。
執筆/北海道函館市立臼尻中学校教諭・工藤美希
編集委員/北海道函館市立万年橋小学校教諭・藤原友和
目次
1.はじめに
こんにちは。函館市で中学校教諭をやっております。昨年度に引き続き、恩師である藤原先生の道徳の企画※1に携わることができて、とても嬉しく思います。
藤原先生との出会いは、私が教育実習生のとき……教師としてのステップアップをするために、様々なことに挑戦できる環境にしてくださり、本当に感謝の気持ちでいっぱいです!
今回は、前回同様、地域学習をして、自分の住んでいる街をもっと好きになってほしい、誇りを持ってほしいという気持ちから、地域教材を探しました。
また、先日、オリジナル地域教材を使った道徳授業を受けた生徒たちが、授業で紹介した地域の偉人、坂田孫六の遺徳碑※2を、宿泊研修中の自主研修の時間を使って探していたことを知りました。
残念ながらそのときには見つからなかったそうですが、授業が生徒の心に響いていたことをとても嬉しく思いました。
もう、これは地域道徳にしよう。また少しでも生徒の心に残ればと思い、今回は「函館港まつり」に目を向けてみました。
3年ぶりに地元で一番大きな祭りが開催されたこともあり、祭りの歴史に迫ったところ、私も知らなかった深い物語がありました。
では、短い内容ですが、皆さまの心に響きますように……。
2.「一枚画像道徳」の実践例
対象:中学2年生
主題名:地域の伝統の大切さ
内容項目:C-(16) 郷土の伝統と文化の尊重、郷土を愛する態度

発問1 この祭りの写真には、ある想いが込められています。それはどんなことだと思いますか?
●その地域の平和を願っている
●人との交流を深める
●人々が元気になってほしい
●大漁祈願
●大きな火事があって、街を元気にするため
「皆さんからこんな素敵な想いが見つかるなんて嬉しいです。皆さん、とても心がきれいですね。それでは実際にはどんな想いが込められていたのでしょうか。これからお祭りの歴史をお話しします。」
説明
『函館市史』※3によると以下のように説明されています。
●港まつりを開催するきっかけは、1934年3月に突如、函館を襲った函館大火。
●市民は意気消沈したが、約1年半かけて日本全国、海外から寄せられた義援金を基にして、復興を目指していた。
●大火復興1周年を意義あるものにするために、当時の海運業組合長・谷 徳太郎が、祭りを提唱した。
●函館市は開港77年目にあたる1935年7月1日を開港記念日として、制定。
●谷はこれを契機ととらえ、大きな被害を受けた函館の復興祈願を目的として、「第1回 函館港まつり」を開催した。
「新型コロナウイルス感染症により、港まつりが2度中止になったのは、昭和18年からの3年間、戦時中のため一時休止されたとき以来だそうです。
令和4年度の港まつりはコロナに負けない強い気持ちをもって過ごしていこう、伝統を守ってまた函館市を盛り上げようと、実行委員が開催したのかもしれません。今年は開港163年であり、伝統のあるお祭りであることがわかりますね。
谷さんは大火からの復興に向け、とても強い想いで、市民とともに祭りをつくり上げました。皆さんはどんな想いで地元のお祭りに参加していましたか?」
発問2 皆さんは地元のお祭りに参加するとき、どんな気持ちで参加していましたか?
●楽しむため
●ただおいしい食べ物を探していた
●よさこいを披露するのが嫌だ
●お金を使いすぎないようにしよう
「考えてみると、自分だけが楽しければいいやとか思っていたかも……」
「祭りに込められていた想いは初めて聞いた……」
「嫌々踊りを披露していた…」
などの発言があり、生徒たちは地元のお祭り、地域のお祭りに強い想いが込められていたことに驚いていました。
「皆さんが住んでいる地元のお祭りにも、じつは、大漁を願って地域を元気にしよう、という想いが込められています。長い間守られてきた想いですね。これから読む教科書のお話も同じような内容ですが、読んだ後にどのような気持ちになるかな? では読んでみましょう。」と、教科書教材※4につなげていきました。
教科書教材の内容は、以下のようなものです。
「参加者のマナーの悪さが原因で、地元のお祭りが中止になり、残念に思っていた中学2年生の主人公。
ある日先輩に誘われ、近隣の他地域の祭りに妹を連れて行くことになる……。妹の世話が面倒だと感じつつもしぶしぶ行ってみたが、なかなか先輩の姿は見つからない。
やっと見つけた先輩は、出店のお手伝いをしていた──。
気が付けばそのお祭りでは、大人だけでなく子供たちも出店の手伝いをしている。街のみんなで小さな子供たちの世話もしている。
そんな姿を見ているうち、主人公はその先輩から、「俺らの祭りじゃけ」と言われ、その言葉が心に引っかかる──。
面倒だと文句を言い、自分さえ楽しめればいいとしか考えていなかった主人公は………?」
この教材を読んだ上で、生徒たちとは次のように話し合います。
「よさこいをいやいや披露していたかもしれないけれど、地域の人から見れば、この子たちが祭りを支えてくれている。と思っていたかもしれませんね。」
「ただ参加していたと言っていましたが、皆さんは踊りを披露することで、祭りを支えていたのです。とても素晴らしいことですよ。」
授業後の生徒たちの感想には、次のようなものがありました。
「自分たちがこれから伝統を守るために、歴史を伝えていきたい。」
「私たちだけではなく、住んでいる人も伝統について学ぶこと。そして、つないでいくことが大事。」
「参加するだけではなく、裏方のことも理解して参加をする。」
この感想を読むと、どんな祭りにも歴史があり、それを受け継いできた人々がいたこと、改めて伝統を守る大切さ等について、深く考える機会になったのではないかと思います。

