【困難のタイプ別】学校における合理的配慮とは?
平成28年に「障害者差別解消法」が施行され「障害者に対して不当な差別的扱いを行うこと」が禁止されるとともに、国・地方公共団体(公立学校を含む)において、「合理的配慮の提供の義務が課せられるようになりました。
執筆/熊本県公立小学校教諭・一法師文明
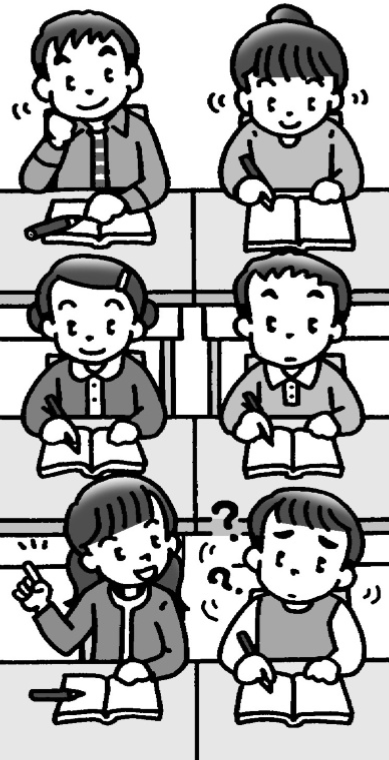
目次
教育分野における「合理的配慮」とは
障害のある子供が、ほかの子供と平等に「教育を受ける権利」を享受・行使することを確保するために、以下の3点に留意する必要があります。
- 学校の設置者および学校が必要かつ適切な変更・調整を行うこと。
- 障害のある子供に対し、その状況に応じて、学校教育を受ける場合、個別に必要とされるもの。
- 学校の設置者および学校に対して、体制面、財政面において、均衡を失した負担または過度の負担を課さないもの。
学校における合理的配慮の例
「読み」に困難さ

- ふりがなをつける。
- タブレット端末(音声読み上げソフトを活用する。
- 拡大印刷を活用する。
「視覚」に困難さ

- 黒板の文字が見やすいように座席を教室前方に置く。
- 拡大教科書を利用する。
「聴覚」に困難さ

- FM補聴システムを活用する。
- 教室前方へ座席を配置する。
- 口元を見やすくして話す。
「集中力」に困難さ

- 黒板の周りに不要な掲示をしない。
- 1時間の授業の流れを示し見通しを持てるようにする。
- 多様な課題を準備し、柔軟に選択できるようにする。
「指示の理解」に困難さ

- 指示をひとつずつ伝える。
- 写真や絵カードなど視覚的に支援する。
- 次の活動を個別に説明しておく。
「移動」に困難さ

- スロープやエレベーターを設置する。
- 体育等の内容を調整する。
- 教室の場所を検討する。

