「エージェンシー」とは?【知っておきたい教育用語】
急速に変化する世界で解決すべき新たな課題が増え、しかもその変化は先行きが不透明で、予測が難しいと言われています。感染症の世界的な流行や温暖化による大きな災害などもその一つです。そのような社会を生き抜く、あるいはそのような状況の中にあって持続可能な社会の創り手となる子どもたちに身につけてほしい力の一つとして注目されているのが「エージェンシー」です。
執筆/ 創価大学大学院教職研究科教授・渡辺秀貴
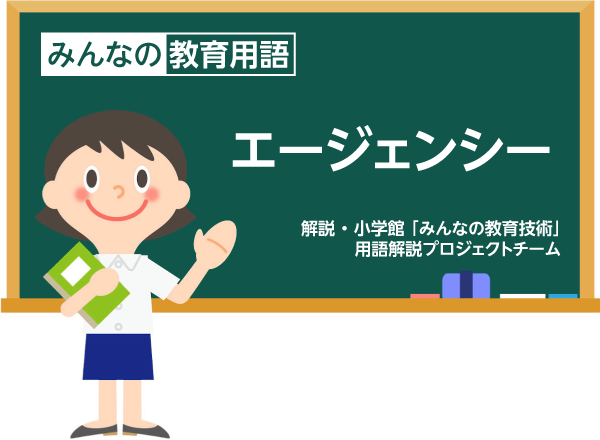
目次
「エージェンシー」とは?
これからの社会を生きる子どもたちに育成したい力について、OECD(経済協力開発機構)を中心として国際的な検討が活発に行われています。OECDは、「教育とスキルの未来2030プロジェクト」を進め、2019年5月に、「OECDラーニング・コンパス(学びの羅針盤)」を発表しました。
「エージェンシー」はその中心的な概念として、「変化を起こすために、自分で目標を設定し、振り返り、責任をもって行動する能力(the capacity to set a goal, reflect and act responsibly to effect change)」と定義されています。
なぜ、エージェンシーが注目されているか
予測が困難な状況を乗り越えていくためには、「結果の予測(目標設定)」や「目標実現に向けた計画立案」「自分が使える能力や機会を評価・振り返り、自身のモニタリング」「逆境の克服」などの多様な能力が欠かせません。エージェンシーはこれらの「よりよい未来の創造に向けた変革を呼び起こす力」を表しています。
これまで国の答申や学習指導要領でも、子どもが自ら課題を発見し、考え、主体的に判断して行動し、よりよく問題解決する資質・能力を身につける教育の重要性が示されてきました。これらの資質・能力の育成の先には、持続可能な社会の創り手としての子ども像があり、その実現への原動力となるのがエージェンシーです。
教師をはじめとする大人からの指示をこなすだけではこれらの力を身に付けられませんし、当然、この力を発揮することはできません。将来の社会のあり方について自分ごととして考え、どのように実現していきたいか、自分で目標を設定し、そのために必要な変化の実現に向けて行動することが、近い将来の社会に欠かせないことなのです。
また、エージェンシーの意味を理解する上で、「責任(responsibility)」の意識が強調されていることを捉えておくことが大切です。子ども自らの目標設定やその実現は自分たちの欲求の実現にとどまらず、自分たちが所属する社会に責任を負うことが求められています。自らの目標や実現のための行動が、社会にどう受け止められるかを考えたり、振り返ったりする能力もあわせて育成される必要があります。

