子供に任せ、トライ&エラーで力を伸ばす【楽しい学校をつくる特別活動~研究発表会のあり方②】
第2回目の今回は、特別活動での子供に任せるポイントを紹介します。単行本『楽しい学校をつくる特別活動~すべての教師に伝えたいこと~』(小社刊)の発刊を記念して、執筆者の1人である尚絅大学平野修教授(前熊本市立帯山西小学校校長)に、特別活動や自主研究発表会のあり方等についてうかがいました(取材は2022年2月)。インタビューを2回に分けてお届けします。
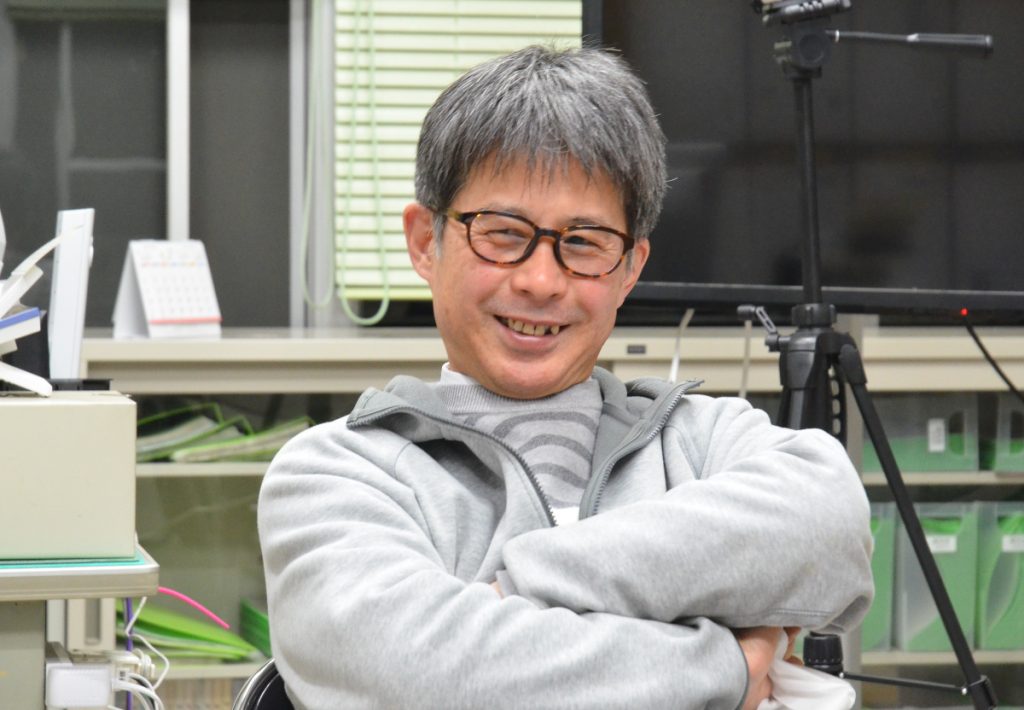
※本記事は、2回連載の第2回目です。
目次
特別活動に一番大事なことは、子供に任せる姿勢
――特別活動を実施していくうえで、効果が見えにくいという状況があると思いますが、そのときはどのようにされますか。
平野 エビデンスと言うと数字的なものばかり言われていますが、そればかりではないと思います。特に特別活動のように数字として表しにくいものを無理して数値にだけにエビデンスを求めることは危険だとも感じています。例えば、写真やビデオを使って子供の表情の変化から変容を求めたり、子供へのインタビューや感想などから変容を図ったりすることも十分に効果を図るエビデンスとして有効だと感じています。
本校(熊本市立帯山西小学校)では、大分大学の長谷川祐介先生にお願いして、本校の研究に即した調査項目を作成していただき、共同で特別活動の実践における効果というものも探っていきました。様々な、角度から効果を図ることが大切な気がします。
――特別活動を実施するうえで、平野校長先生がもっとも心がけていることを教えてください。
平野 それは子供に任せることです。子供に任せるとは、ほうっておくというのではなく、先生とかかわりながら、一緒に作っていくということです。先生方は、指導者としての立場からきちんとしたものを子供たちに作らせようとします。そうなると、どうしても指導が強くなり、子供たちはさせられた感が強くなり、先生の言う通りにしておけばいいと感じてしまいます。結果、受動的になり学びにつながりません。表面的な見栄えや格好にこだわるのではなく、失敗したら失敗したで、次に何ができるか、トライアンドエラーで考えさせていくことが大切なのです。1つの活動を見栄えで成功させるのではなく、それを通して、どういう力を子供たちに付けていくのかというスタンスで見てほしいのです。
子供たちがやりたいようにやりたいことをやって、結果、どうだったのかを振り返る。うまくいったところはどこで、うまくいかなかったところはどこなのか。どうすればよかったのかを考え、次につなげていき、自分たちて活動を作り上げていくことを大事にしてほしいのです。
そのためには、先生たちには、どういう子供たちを育てるのか、どういうふうな子供たちにしたいのかということを、いつも念頭に置いていてほしいと思います。活動をするのが目的ではなくて、その活動を通して、どういう力を子供たちに付けるかというところが重要です。特別活動は非認知的な力を付けていくので、短期的に結果を求めるのは難しいのです。子供たちの変容を、長期的に見ることが重要です。
「うちの学校の子供たちは言われたことをするけれど、自分たちで考えないんだよね」という先生たちを見受けますが、そういうふうにしているのは、先生たちなのです。
本校も最初は、「子供たちはまじめで、言われたことはするけど、自分たちでやってくれない」という先生たちの声がものすごく多かったのです。しかし、今は、先生たちの子供に対する評価は全く違います。子供たちは自分たちで自主的に活動をやっていますし、それを先生たちは楽しんでいます。先生たちが楽しむという姿勢が大事です。特別活動は楽しまないといけません。

