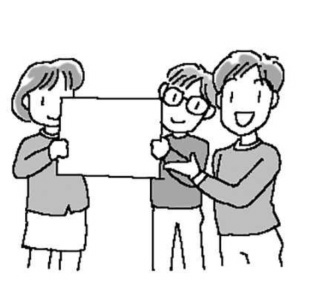交流・共同学習で深める特別支援教育
障害のある子供たちと、障害のない子供たちとの交流および共同学習は、子供たちの経験を深め、社会性を養い、豊かな人間性を育むとともに、お互いを尊重し合う大切さを学ぶ大きな意義のある機会です。『小学校学習指導要領 総則編』の中にも、障害のある子供と障害のない子供が交流する機会を積極的に設けるよう示されています。
執筆/福岡県公立小学校教諭・伊澤直美

目次
交流および共同学習とは
どのようなよさにつながるの?
障害のある子供にとって
様々な人々と助け合って生きていく力となり、積極的な社会参加につながる。
障害のない子供にとって
障害のある人に自然に言葉をかけて手助けをしたり、積極的に支援を行ったりする行動や、人々の多様なあり方を理解し、障害のある人とともに支え合う意識の醸成につながる。
参考サイト:『交流及び共同学習ガイド』(文部科学省)
交流
相互の触れ合いを通じて豊かな人間性を育むことを目的とする。
共同学習
教科等のねらいの達成を目的とする。
交流および共同学習を行う場面
特別支援学級の一人ひとりの子供の実態や目標に応じて、どのような交流および共同学習を行うことができるか検討します。
それぞれの子供にとって、どのようなよさにつながるのかを明確にすることが大切です。
学校行事や全校集会での交流
- 運動会、学習発表会、遠足、社会科見学、宿泊体験学習、修学旅行等
※並び順や組み合わせに配慮。
※学年の仲間の1人であることを意識できるようにする。

委員会活動やクラブ活動での交流
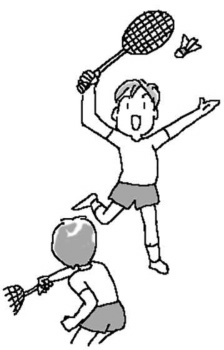
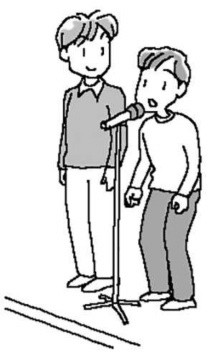
各教科や道徳科、総合的な学習の時間での交流
- 音楽、体育、図画工作、家庭科等

給食での交流
- 交流学級における給食(毎日/週に○日)
- 特別支援学級における給食を交流学級から数名ずつ交代で行う。

清掃活動での交流
- 交流学級の清掃を一緒に行う。
- 特別支援学級の清掃を交代で一緒に行う。
休み時間での交流
- 集団遊び(おにごっこ、ドッジボール等)を一緒に行う。

朝の会や帰りの会での交流
- 1日の予定や連絡を聞く。
- 係からのお知らせやイベントを行う。
- スピーチを行う