少人数学級の経験を先達に学ぶ!
2021年3月、いわゆる義務教育標準法の改正により、少人数学級を推進していくことが決まりました。小学校の学級編成の標準を5年間かけて現行の40人(小学1年生は35人)から35人に引き下げられます。今回は、少人数学級を実現した先達の話を聞き、これから少人数学級を実施することになる学校管理職や教師の道標として、その歩みを追体験してみることにします。
今から20年ほど前、全国に先駆けて、愛知県犬山市の小中学校で少人数学級の実現を目指した教育行政マンがいました。のちに校長になってから行った少人数学級による学校づくりは全国から注目を浴びました。現在、教育評論家の加地健さんにお話をうかがいました。

目次
立ちはだかる学級編成標準の壁
加地さんは、少人数学級に基づく学校教育が理想だと考えていたひとりでした。しかし、40人学級につき担任1名を配置するという学級編成標準の壁があり、それを実現することができませんでした。
ところが、当時、中央教育審議会委員の小川正人・東大教授(肩書当時)が、現行法の枠内でも、学習集団と生活集団を分離して指導することが可能だと主張していました。そこで、2000年に小川教授を招聘して犬山市教育委員会主催のシンポジウムを開催しました。
すると、少人数学級が無理としても、少人数授業が可能だとするその提言に出席者であった石田芳弘市長(当時)が賛同しました。
ただし、そうするためには、授業を担う非常勤講師を新たに採用しなければなりません。市長が乗り気になったおかげで、その予算がつき、少人数授業の実施を希望する小中学校に非常勤講師を割り当てました。
教師が学び合いの授業をできない!?
当時の犬山市は、「学びの学校づくり」を目標にした教育改革を行っていました。少人数学級を実現することは、犬山市の教育改革の目玉でした。犬山市教育委員会の学校教育部長だった加地さんは、愛知県教育委員会と長らく折衝しました。ようやく2002年になって、県教委は市の経費負担を条件に少人数学級の実施を認めました。
少人数学級のよさはすぐに表れました。教師は授業中にすべての子の実態や変容を把握でき、充実した授業を展開できたのです。子供が何を考えているか、学習の理解度を確認することができました。 また、子供にとっては、授業中に何度も当たるので、発言する機会が増えました。わからないところは教師に丁寧に教えてもらえ、授業に参加できたという満足感を持つことができました。教師は教える喜び、子供は学ぶ喜びを味わえるようになっていきました。
これらが少人数学級の光とすれば、影も見えてきました。先行した少人数授業では、それにふさわしい学び合いの授業という指導法を開発していましたから、少人数学級においても、その指導法を適用することができました。この学び合いの授業とは、子供の自主的な助け合いを重視する授業のことです。
しかし、教師は40人学級の授業感覚を引きずり、少人数学級に合わせた授業が思うようにできないという指導力不足の壁に直面しました。専門家を呼んで研修を強化し、学び合いの授業を浸透させていきました。
犬山の教育は評判を呼びましだ。苅谷剛彦・東大教授(当時)から、「犬山市の教育改革の実態を調査したい」という申し出があり、市内の全14小中学校を対象にした調査が始められました。
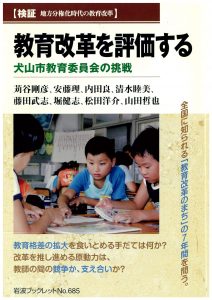
苅谷剛彦・他/著『教育改革を評価する 犬山市教育委員会の挑戦』(岩波書店)

