小1生活「あきまつりをしよう!」指導アイデア
執筆/大分県教育庁大分教育事務所・野々下睦代
編集委員/文部科学省教科調査官・渋谷一典、文部科学省教科調査官/愛知淑徳大学准教授・加藤智、大分県教育庁義務教育課指導主事・後藤竜太
目次
期待する子供の姿
知識及び技能の基礎
身近な秋の自然を使って遊ぶ活動を通して、自然の不思議さや遊びを創り出す面白さに気付く。
思考力、判断力、表現力等の基礎
身近な秋の自然を使って遊ぶ活動を通して、種の特徴を見付けたり、比べたりしながら、身近な自然を利用して自分たちの遊びを工夫することができる。
学びに向かう力、人間性等
身近な秋の自然を使って遊ぶ活動を通して、みんなで楽しく遊びたいという願いをもって友達や園児などに意欲的に関わろうとする。
単元の流れ(10時間)
学習の流れ
たねのけんきゅうをしよう!(2時間+日常の活動)
・アサガオの種を基に身の回りにある種について話し合う。
・オナモミやドングリ、果物の種など、集めた種を紹介し合い、諸感覚を生かしたり、虫眼鏡を使ったりして観察する。

【評価規準等】
知 種がもつ色や形、大きさなどの面白さや不思議さに気付いている。
※評価規準等の知 =知識・技能、 思=思考・判断・表現、 態=主体的に学習に取り組む態度の観点を示しています。

みつけたたねをつかってあそぼう!(4時間+図画工作科との関連)
・投げたり、転がしたりなど試しながら、遊びを工夫する。
・十分に楽しんだ遊びを友達と紹介し合って遊ぶ。
・互いの遊びを楽しみながら、改善点に気付く。
・みんなで楽しく遊ぶための改善や工夫を加える。

【評価規準等】
思 さまざまな色や形をもつ種の特徴を見分け、どのような遊びができるか見通しながら、遊びを創造している。
態 友達の工夫や自分との違いに気付き、みんなと協力して遊びを楽しくしようとしている。
あきまつりをしよう!(4時間)
・友達や園児を招待して楽しく遊ぶための準備をする。
・秋祭りに園児などを招待し、一緒に遊びを楽しむ。
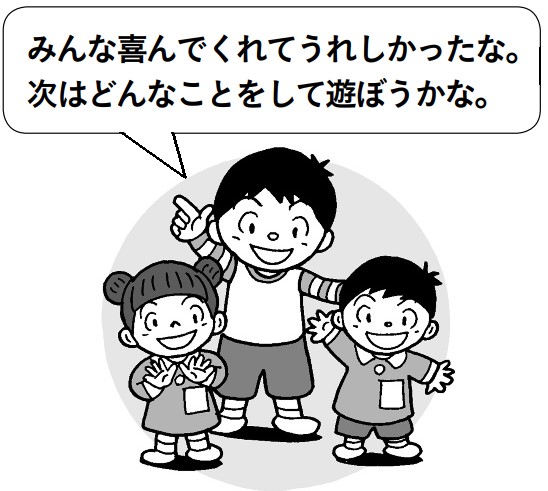
【評価規準等】
知 遊びの約束やルールを工夫して、遊びを創り出す面白さに気付いている。
態 みんなで遊ぶと生活が楽しくなることを実感し、これからの生活を豊かにしようとしている。
活動のポイント1 気付きを共有し、比べたり、関連付けたりする
「種はかたくて丸いもの」というイメージをもっていた子供に、ススキや松ぼっくりを「これも種だよ」と紹介すると、自身がもつイメージとの違いから、種への関心が膨らみます。
登下校中や家庭でも「これも種?」「あれも種?」と集め出し、その色や形、大きさの違いを比べ、伝え合うようになるでしょう。たくさんの種を見付け、集める活動によって、秋という季節の概念が形成されていきます。
気付きを共有する工夫の例
〇集めた種を袋に入れて掲示した 「たねずかん」に、気付いたことを書き込めるようにする。
○種に関する絵本や図鑑を置くコーナーを設ける。
○種の色や形、大きさ、感触の違いなどについて気付いたことを掲示しておき、遊びの際に参考にできるようにしておく。

活動のポイント2 「次は、どうする?」のふり返りで、遊びを発展的に繰り返す
イラスト/高橋正輝
『教育技術 小一小二』2020年10月号より






