プロ教師は『声の高低』で子供との距離感を自在にする
教師が使いこなすべき”6つの声“②
教師は『話す仕事』、意図的に声を使い分けるのがプロの教師です。――と語るのは、小学校教諭・熱海康太先生。各界の「話のプロ」の技術を授業や学級経営に活かす「教師が使いこなすべき6つの声」とは? その教育的効果と効果的な使い方について教えていただきました。話を聞かない(聞けない)子供たちにも伝わる「声」を手に入れる極意を、「教師が使いこなすべき”6つの声”」全3回の連載でお届けします。今回は、難易度は高いが身に付けると最強の武器にもなる「高い声・低い声」です。
執筆/私立小学校教諭・熱海康太
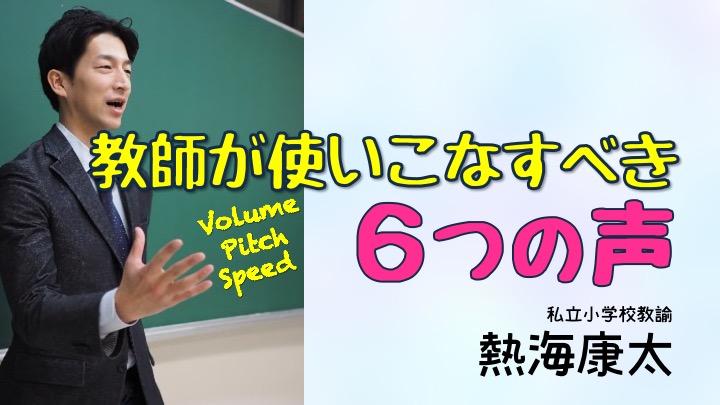
目次
「高い声」と「低い声」
教師は「話す仕事」です。
話すためには声が必要です。
多くの先生が基本的には教室全体にクリアに聞こえる「大きい声」で話し、たまにアクセントで「小さい声」で子供たちを惹きつけます。
ここまでは、ある程度、経験のある先生なら自然に行っていることかもしれませんが、そこに「高い声」「低い声」というバリエーションを入れることで、言葉はさらに子供に届きやすくなります。
テレビコマーシャルに出てくる有名予備校の先生や、落語家さんなど「伝えることのプロフェッショナル」の話し方をよく聴くと、音の高低を効果的に駆使していることが分かります。
「高い声」「低い声」には、どのような教育的効果や留意すべきことがあるのでしょうか。
それらを意識することで、「高い声」「低い声」を使いこなし、「伝えることのプロフェッショナル」を目指していただければと思います。
音域の広さは教師の「ストロングポイント」になる!
第1回でも説明したように、大きい声、小さい声を使い分けることは、既に多くの先生がしています。
これは、そもそも日常の生活でもTPOに応じて、「声を大きくしないと聞こえない」とか「ここまで静かだと、よっぽど小さな声で話さないと迷惑になってしまう」など自然に使い分けられることが多いからです。
しかし、この先で紹介する、「高い声」「低い声」については、意識していない人が多いのではないでしょうか。多くの先生方が様々な場面で話しているのを聴いていても、同じような音域であることがほとんどです。
ただ、トップクラスの先生の授業を観たり、音声を聴いたりすれば明らかですが、子供たちを惹きつける話し方をする教師は、声の高さの幅が広いです。

先に述べたように、有名予備校の先生や落語家さんを想像するとさらに分かりやすいと思いますが、話の内容を立体的に表情豊かに表現するには、声の高低を巧みに駆使することが必須となります。
そして、多くの先生方があまり意識していないということの裏を返せば、その技術を習得することは、あなたのストロングポイントになり得るということです。
役を演じ、インパクトを与える「高い声」
高い声を使う有名な方を挙げるとすると、皆さんなら誰を想像するでしょうか。私は、株式会社ジャパネットたかた創業者・高田明さんが思い浮かびました。
高田さんは、商品を紹介する時に、肝になる説明の部分では、とても高い声を使っています。
高田さんは、すごくしゃべりが流暢であったり、活舌が良かったりという印象はありませんが、一度聞いたら忘れることのできない語り口が特徴です。その要因は、高い声によるインパクトの強さなのではないかと考えています。
当然、高田さんも普段からあのしゃべり方ではないと思います。強いイメージを与えるために「役者」になっているのでしょう。
この「役者」になるということは教師にも求められることです(「教師は五者たれ」⦅学者、役者、易者、芸者、医者⦆という言葉があります。諸説あるそうです)。
明るく元気に振る舞ったり、キーワードを印象付けるために大げさに伝えたりと、「役者」になる時に高い声は役に立ちます。
子供に親近感を持たせる「高い声」
また、高い声とは子供の声である、ということも重要な事実です。
男子は小学生であればまだ声変わりが始まっていない子が多く、高い声で話す子がほとんどです。また、女子も声変わりをしますが、低中学年では、より高い声の子が多いです。
高い声で話すということは、自分を子供に寄せるという意味です。
例えば、子供たちと遊んでいる時には、「同じ目線」を大切にしたいのであれば、低い声よりも高い声を出した方が子供たちは親近感を覚えるでしょう。
声の出し方に限らずですが、このように大人のほうから子供に寄り添うということは重要です。
そして、実際に寄り添うことは言うほど簡単ではなく、誰にでもできるわけではありません。このように声を寄せるなど、地道な取り組みの積み重ねが重要なのです。
深刻さを軽減したいときの「高い声」
さらには、高い声には「深刻になりすぎない」という効果もあります。私はこの効果を、様々な場面で使っています。
低学年では子供たちに「大好きだよ」と伝えることがありますが、これを低い声で伝えると、少し怖いかもしれません。
また高学年では「もう分かっているよ!」と思われることでも、繰り返し伝えていかなくてはならないことについては、あえて深刻さを出さない高い声を使う場合が多いです。
ただ、高い声を不快に思う人も少なくありません。終始高い声を使うことは避けた方が無難です。
ここぞという場面で効果を意識しながら使うことで、豊かな個性を表現できるものになるのです。

