色カードで意思表示しやすくする|樋口綾香のGIGAスクールICT活用術②

Instagramでは1万人超えのフォロワーに支持され、多くの女性教師のロールモデルにもなっている樋口綾香先生による人気連載! 今回は、ICT活用のしかけの一つ、どの授業でも簡単にできる「色」を使った意思表示についてお伝えします。
執筆/大阪府公立小学校教諭・樋口綾香
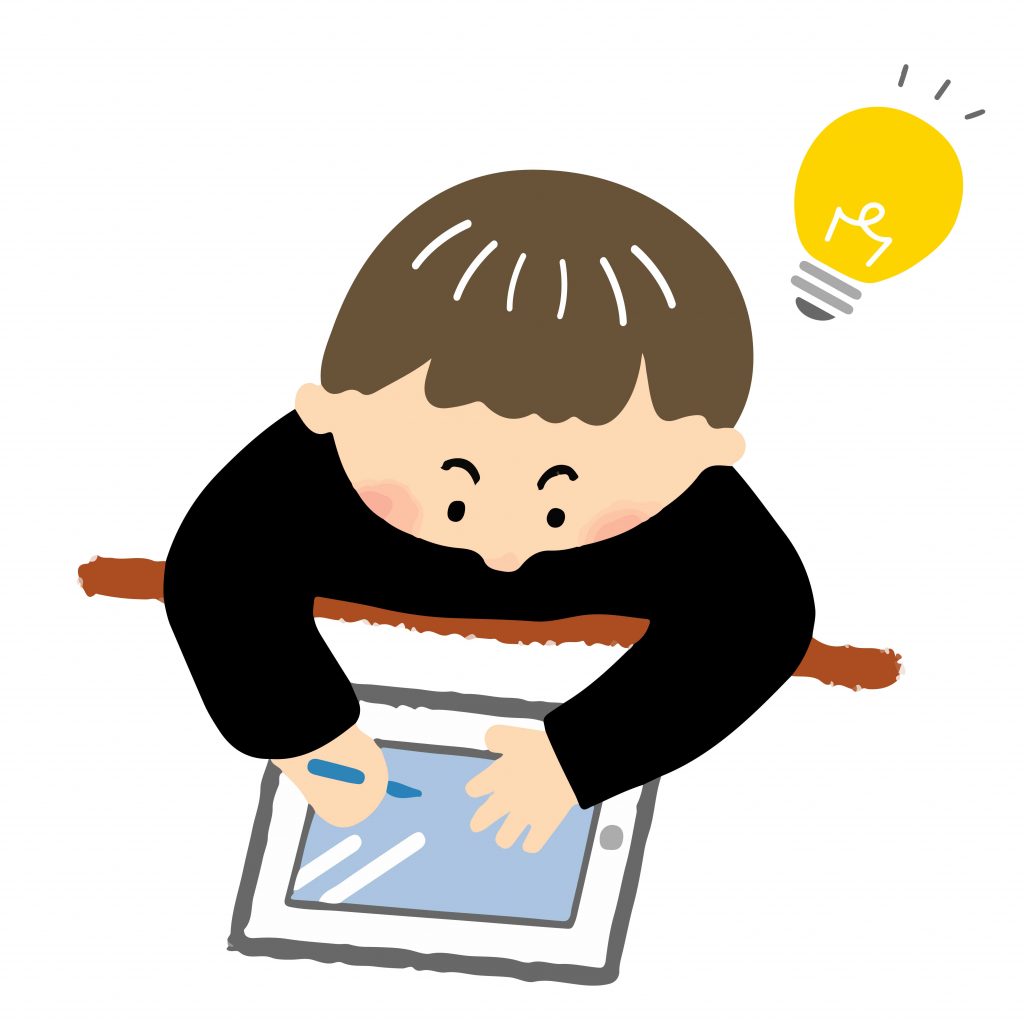
【関連記事】GIGAスクールのICT活用①~国語:季節の言葉~
使用タブレット:iPad
使用アプリ:ロイロノート
目次
意図的にしかけを散りばめる
国語の読みの授業では、導入で初発の感想を書かせることがよくあります。
初発の感想をもつことや、交流することは、これからの授業の方向性を児童と共通理解しながら進めていく上で大変重要です。
しかし、すべての単元計画が児童の感想で決まるというわけではありません。指導目標や、授業者の意図も大切な要素です。
児童にどんな力をつけたいかを十分に考えた上で、児童の思考が自然に流れるように、導入の授業に意図的にしかけを散りばめていきます。
そのしかけの一つに、「色カードで意思表示」というものがあります。
【関連記事】
子供たちに伝わる板書の書き方を徹底解説している特集。様々な事例がたくさん!→ 樋口綾香&樋口万太郎夫妻が解説! 国語・算数 伝わる板書のルール
『初雪のふる日』の導入で
光村図書の4年生の教科書に『初雪のふる日』(安房直子)という作品があります。
ファンタジー作品ですが、同じ4年生で学習する温かでさわやかな作品 『白いぼうし』(あまんきみこ)とは違い、背筋がゾッと寒くなるような、登場人物が恐ろしい体験をするお話です。
単元の計画として、読者が感じる「不思議さ」や「怖さ」の根源を、児童が読み味わう授業をしたいと考えました。そして、自分が理解し、感じたことをレポートにして発表するという単元計画を立てました。
この単元計画に沿って授業をしたいと考えたとき、まずは児童がこの作品を「不思議だな」「怖いな」と感じていなければいけません。あるいは、「自分はおもしろいと感じたけれど、他の子は『不思議』や『怖い』と思っている子が多いのだな」と知ることが重要です。
そこで色カードを使いました。
【関連記事】
綾香先生が国語の教材分析についてまとめたこちらのシリーズも必読です!
国語の教材分析① ~教材分析で大切にしたいこと~
国語の教材分析② ~分析の観点「題名」~
国語の教材分析③ ~教師と教材との出合い~
国語の教材分析④ ~分析の観点「冒頭」~
国語の教材分析⑤ ~分析の観点「事件と山場」~
国語の教材分析⑥ ~分析の観点「主題」~

