小2生活「大きくなあれ わたしの野さい」指導アイデア
執筆/神奈川県公立小学校教諭・篠原紘子
編集委員/文部科学省教科調査官・渋谷一典、文部科学省教科調査官/愛知淑徳大学准教授・加藤智、神奈川県公立小学校校長・二宮昭夫
目次
期待する子供の姿
知識及び技能の基礎
野菜を継続的に栽培する活動を通して、植物が生命をもっていることや成長していることに気付くことができる。
思考力、判断力、表現力等の基礎
野菜を継続的に栽培する活動を通して、植物の変化や成長の様子に関心をもって働きかけることができる。
学びに向かう力、人間性等
野菜を継続的に栽培する活動を通して、生き物に親しみをもち、大切にすることができる。

単元の流れ(9時間)
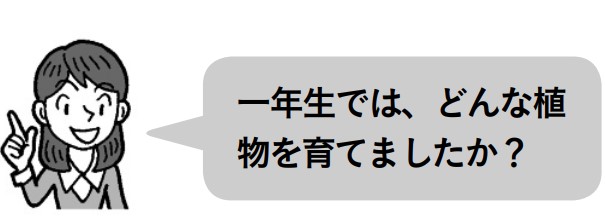
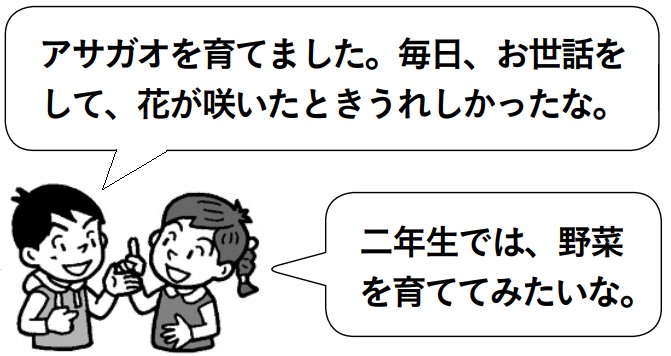
野さいをそだてよう(3時間)
・ 自分の栽培する野菜を決める。(1時間)
育ててみたい野菜を決めましょう。
ミニトマトを育てて、お母さんに食べてもらいたいな。
八百屋さんが、今から育てるなら夏野菜がいいって言ってたよ。 夏野菜には何があるかな。
・野菜の苗を植えたり、種をまいたりする。(2時間)
ふかふかで、栄養たっぷりの土に植えるね。「オクラちゃん」おいしく育ってね。
野菜によって、種の形や大きさ、葉っぱの形や手ざわりが違うんだね。
評価規準等
(思)野菜の特徴などを意識しながら、自分で育てる野菜を決めている。
(知)=知識・技能
(思)=思考・判断・表現
(態)=主体的に学習に取り組む態度
野さいのせわをつづけよう(2時間・常時活動)
・水やりや雑草取り、施肥など、継続的に世話をする。(常時活動)
・野菜の様子をもとに、必要な世話について交流する。(2時間)
野菜の様子やお世話について話し合いましょう。
キュウリくんからつるが出てきたよ。支柱が必要かな。
トマトの「わき芽」を取ったほうがよく育つって、野菜名人が教えてくれたよ。
評価規準等
(思)野菜の様子に応じて関わり方を見直しながら、観察したり、世話をしたりしている。
(知)=知識・技能
(思)=思考・判断・表現
(態)=主体的に学習に取り組む態度
野さいをしゅうかくしよう(1時間・常時活動)
・野菜を収穫する。(常時活動)
・収穫して気付いたことを表現する。(1時間)
一本の苗から、たくさんのピーマンが採れたよ。「ピーくん」すごい!
採れたオクラをスープに入れて家族で食べたら、おいしいって言われてうれしかった。
評価規準等
(知)野菜は生命をもっていることや成長していること、上手に世話ができるようになった自分に気付いている。
(知)=知識・技能
(思)=思考・判断・表現
(態)=主体的に学習に取り組む態度
野さいのほうこく会を開こう(3時間)
・これまでの活動をふり返り、報告会の計画を立てる。
(2時間)
野菜づくりをふり返りましょう。
毎日、話しかけながらお世話をしたから、おいしいナスができたんだ。
お世話になった野菜名人に発表を聞いてもらいたいな。
・友達やお世話について協力してくれた人に報告会をする。(1時間)
最初は、細い茎だったけど、お世話をすると太くなったよ。すごいね。
野菜名人の方が教えてくれたおかげで、たくさんのトマトが収穫できました。今度は、冬野菜をつくりたいです。
評価規準等
(思)育ててきた野菜の成長や心を寄せて世話をしてきたことなどをふり返り、表現している。
(態)野菜に親しみをもったり、自分の関わりが増したことを実感したりしている。
(知)=知識・技能
(思)=思考・判断・表現
(態)=主体的に学習に取り組む態度
活動のポイント1
栽培活動への意欲が高まる環境を工夫しよう
栽培活動を継続的に行うなかで、子供たちの意欲をさらに高めるためには、さまざまな工夫が必要です。
出合わせ方の工夫
よりよい成長を願う気持ちをもてるようにしましょう。
・自分の鉢で野菜を育てる。
・野菜に名前を付ける。
・野菜に名札を立てる。 など
活動時間の工夫
野菜の変化を交流できる時間や場を日常に設けましょう。
・朝の会や帰りの会の「野菜タイム」
・休み時間の「お世話タイム」など
※デジカメ等を活用すると効果的です。
野菜名人への相談
「野菜名人」として協力を依頼し、多様な人と関わりながら活動できるようにしましょう。
・地域の農家の方や野菜を栽培している方
・野菜づくりを体験している三年生
・学校の職員
・保護者 など

教室環境の工夫
栽培活動に関する情報コーナーなどを工夫しましょう。
・全員の野菜の記録を掲示する。
・植物の栽培に関する図書コーナーを設置する。
・人に聞いた栽培方法を紹介するコーナーを設置する。
活動のポイント2
子供の思いや願いを生かして、気付きの質を高める工夫をしよう
生活科は、子供が身近な環境と直接関わる活動や体験のなかで生まれる気付きを大切にします。植物を継続的に栽培する活動のなかで生まれた気付きの質が高まるよう、「見付ける」「比べる」「たとえる」「試す」「見通す」「工夫する」などの多様な学習活動を取り入れましょう。
見付ける
イラスト/高橋正輝、横井智美
『教育技術 小一小二』2020年4/5月号より






