国語の教材分析② ~分析の観点「題名」~

Instagramでは1万人超えのフォロワーに支持され、多くの女性教師のロールモデルにもなっている樋口綾香先生による人気連載! 今回は、国語の教材分析において大切な、題名分析についてのお話です。
執筆/大阪府公立小学校教諭・樋口綾香
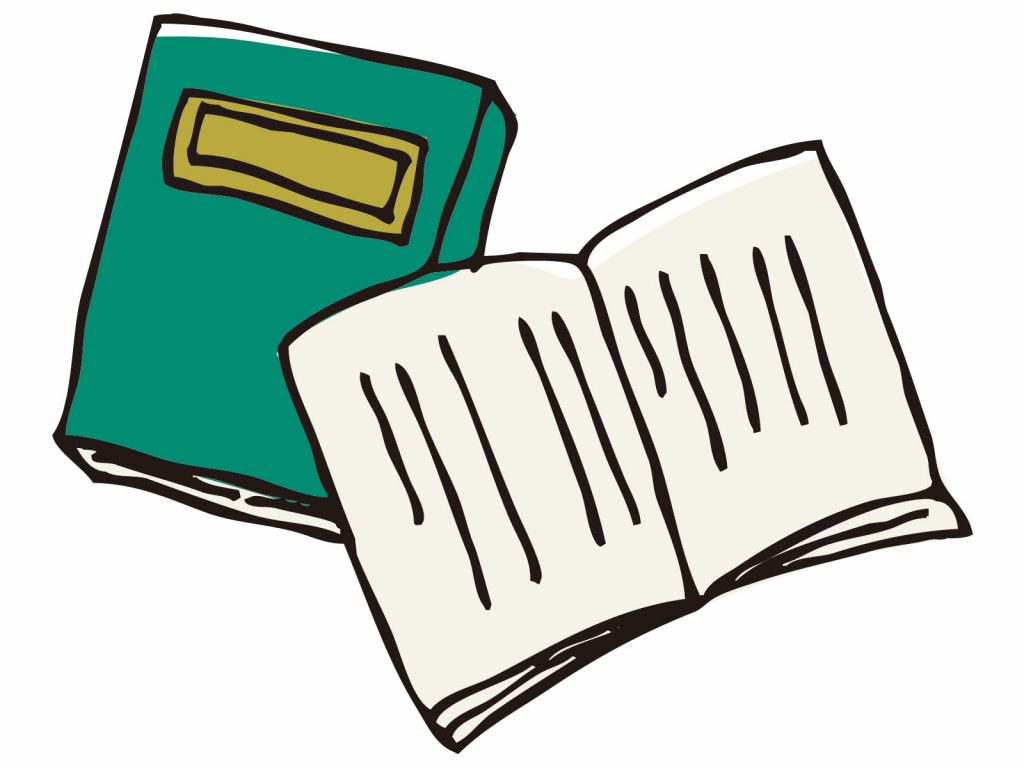
【関連記事】国語の教材分析① ~教材分析で大切にしたいこと~
目次
分析の観点を知るために
大学で学んだはずの国語科教育法。うっすらと「白いぼうし」の指導案を書いた記憶…。大学の先生は、教材を分析するための観点を、きっとたくさん教えてくださったのだと思います。しかし、教師になって1年目。私の記憶にはちっともその内容が残っていませんでした…。
私は、住田先生との学習会で、少しずつ分析の観点の知識を得ていきましたが、今自分で学ぶ中でよく読むのが『国語教育指導用語辞典(第四版)』(著:田近 洵一・井上 尚美/教育出版)です。この本には、国語の教材を分析するための視点や、国語の学習活動にかかわる言葉などの定義、指導内容や指導方法が170の項目を立てて記述されています。
すべてを覚えることは難しいですが、困ったときに何度も読んでいます。国語の教材分析に困っている方は、一度手にとって読んでみてください。(現在は第五版が発行されています)。
【関連記事】
子供たちに伝わる板書の書き方を徹底解説している特集。様々な事例がたくさん!→ 樋口綾香&樋口万太郎夫妻が解説! 国語・算数 伝わる板書のルール
分析の観点その1「題名」
物語文や説明文に出会ったとき、いちばん初めに目にするのが「題名」です。題名は、教材分析をするために、とても大切な観点になります。
光村図書の教科書から、1年生の物語文教材の題名で考えてみましょう。
『はなのみち』
『おおきなかぶ』
『やくそく』
『くじらぐも』
『たぬきの糸車』
『ずうっと、ずっと、大すきだよ』
題名を読み深めていきます。
①『はなのみち』
この題名は、くまさんが落とした花の種が、春になって花を咲かせた道のことです。「はなのみち」は「場所」と捉えることができます。つまり、この物語は、この「はなのみち」という場所が大切な物語ということです。どうして「はなのみち」はできたのか、なぜ「はなのみち」が題名なのか、考えてみるのはどうでしょうか。
②『おおきなかぶ』
おじいさんが大切に育てたかぶが大きくなりすぎて、どれだけ引っ張っても抜けません。そんな「おおきなかぶ」は「キーアイテム」として捉えられます。キーアイテムは、人物が変わったり、物語が大きく展開するきっかけになるもののことです。「おおきなかぶ」に着目して読むと、かぶの大きさと、ねずみの小ささが対比的に描かれていることに気づいたり、大きなかぶがその小さなねずみの協力によって抜けることにユーモアを感じたりすることができます。
③『やくそく』
3匹の青虫たちが、1本の大きな木の上で出会い、はじめて海を目にします。青虫たちは海を知りません。ちょうになったらみんなで見に行くことを約束します。「やくそく」は、「キーコンセプト」と捉えることができます。この物語の中で、「やくそく」がどのような役割を果たすのか、「やくそく」によって3匹の青虫たちはどのような気持ちになり、「やくそく」が果たされるまで、どのように過ごしたのかなど、「やくそく」に焦点化することで、多面的に読みを深めることができます。
④『くじらぐも』
1年生の子どもたちが運動場で体操をしていると、真っ白い雲のくじらが現れます。くじらぐもは、子どもたちと先生を乗せて、素敵な空の旅へ連れて行ってくれます。「くじらぐも」は「人物」と捉えられます。よく題名になるのは、中心人物ですが、この「くじらぐも」は対人物が題名になっています。どうして対人物が題名になのか、問いをもちながら読むと、教材を深く読むきっかけになるでしょう。
⑤『たぬきの糸車』
いたずらもののたぬきが、おかみさんが糸を紡いでいる様子を見て、おかみさんがいない間に糸車を回します。子どもたちは、たぬきが糸車を回すことを「いたずら」と考えたり、「恩返し」と考えたりします。「たぬきの糸車」は「キーアイテム」と捉えることができますが、「たぬきの」となっていることがポイントです。本来、糸車はおかみさんのものです。なぜ、「たぬきの」糸車なのかを考えると、作品のおもしろさに気づくきっかけになるでしょう。
⑥『ずうっと、ずっと、大すきだよ』
小さいころからいっしょだった男の子と犬のエルフは、いっしょに大きくなっていきます。男の子は何度も「エルフ、ずうっと、大すきだよ。」と伝えます。「ずうっと、ずっと、大すきだよ」は、男の子の「台詞」と捉えることができます。この物語の中で、男の子がエルフに「大すきだよ」と言う台詞は3回あります。この3回の台詞は、似ていますが、少しずつ違っています。どのような違いがあるのでしょうか。なぜ違いが生まれたのでしょうか。題名には、最後の台詞である「ずうっと、ずっと、大すきだよ」が使われています。それは、なぜなのでしょうか。台詞を切り口に教材を深めることができます。
【関連記事】
綾香先生が単元全体の板書とノート例を教えてくれるシリーズ!
単元丸ごと!板書&ノート① ~小一国語「やくそく」~
単元丸ごと!板書&ノート② ~小二国語「お話のさくしゃになろう」~
単元丸ごと!板書&ノート③ ~小四国語「プラタナスの木」~
単元丸ごと!板書&ノート④ ~小五国語「大造じいさんとガン」~

