小5外国語:「思考・判断・表現」の見取り方を教科書編集委員が解説
- 特集
- 評価と見とり方特集

小学校外国語科検定教科書の編集委員でもある元神奈川県公立小学校の長沼久美子先生による好評連載! 今回は、外国語の授業における「思考・判断・表現」について、子どもの様子からどこをどう見取って評価すればいいのかを教えていただきます。
執筆/元神奈川県公立小学校教諭・長沼久美子
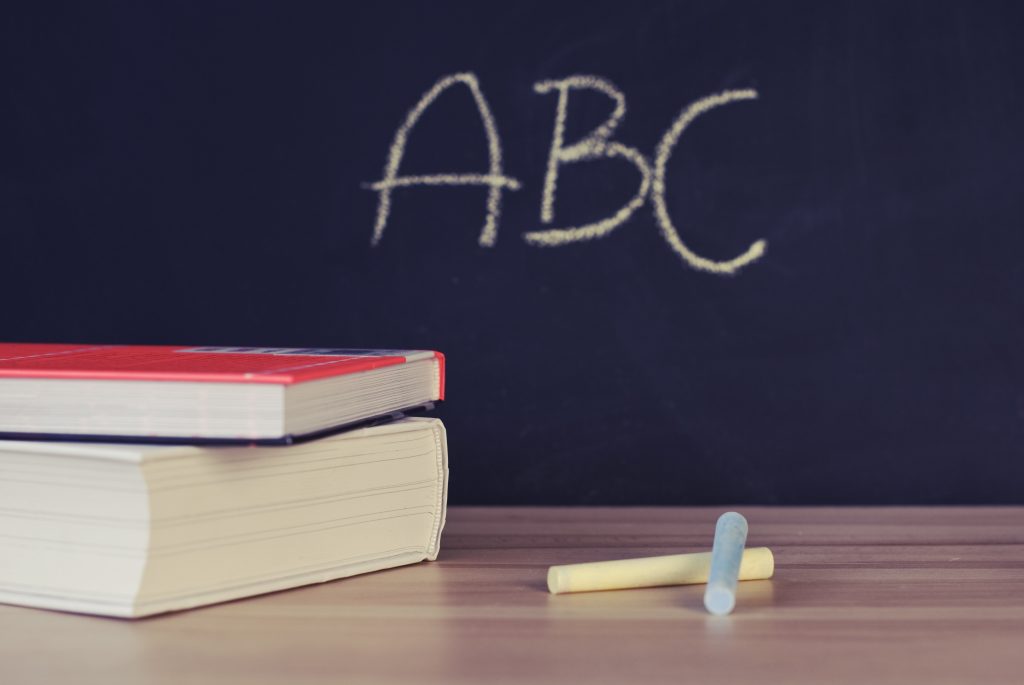
目次
Q1 「身近な人紹介カードを作ろう。」という活動では、どのように思考力・判断力・表現力の育成を意識するといいのでしょうか。
(東京書籍『New Horizon Elementary5』P.42・43)
A. 「どのように紹介しようかな?」と子供が考える時間を、十分にとってあげましょう。
この活動では、まず、誰のことを紹介するか決めます。次に、紹介カードを作ります。最後に、ペアでやりとりをしたり、発表形式で紹介したりします。
その活動の中では、次のようなことを思考・判断する必要が生じます。
- 誰のことを紹介しようかな。
- どんな語彙を使ってみようかな。どんな文章にしようかな。
- どんな質問をしようかな。どんな返事や相槌をしようかな。(ペアでのやりとり、発表)
具体的には、次のように考えています。
○○さんについて発表しよう。そうだ、〇〇さんは、□□が上手だからそのことを言おう。その場合、△△という言葉(単語)を使ってみよう
おそらく、それらの思考・判断の過程をすべて見取ることはできません。しかし、文章の作成の様子や、やりとりでの様子、発表での様子、振り返りカードなどから、子どもの思考・表現の様子を見取ることができます。
定型文を与えてそっくりそのまま言わせるような活動になってしまうと、子どもは、思考・判断をする場を失います。
どのように紹介しようかな?
と、考える時間を十分にとってあげたい活動です。
Q2 使った言葉を書き写す活動があります。「書くこと」での思考・判断とは、どのようなことなのでしょうか。
(学校図書『Junior TOTAL English1』P.64)
A. アルファベットを書くとき、どの文字を書いたらよいか、どこにその文字を書いたらよいか等の思考・判断をしています。何も考えずに書いているわけではありません。
文字を書くとき、何も考えずに書くことはありません。アルファベットを書き始めて数年の子どもは、
何の文字を書いたらよいかな。どこにその文字を書いたらよいかな。大きさはこれでよいのかな
等、いろいろと考えて書いています。
気を付けるポイントが複数あるので、すべてを網羅することができなかった時、間違って書いている状況になります。それを避けるために、子どもなりに考えながら一生懸命に書くのです。
「straight」の前に 「Go」 と書き写す時の例を示します。
「Go」はたったの2文字ですが、「G」と「o」を離して書くか、スペースを開けるのか等、いろいろな書き方が考えられます。
また、続く「straight」との単語間を離さずにくっつけてしまったり、間を空けすぎてしまったりしないように、自分がちょうどよいと思う表記を考えながら書いていきます。
4線がある場合は、
どこに書くのだったかな。たしか、ここだったな。
と、確認したり、思い出したりしながら書いています。
このように、文字を書くときも「思考・判断」をしているのですが、それを見取ることは、なかなか難しいと思います。
そこで、子どもがそれまで書いてきたものと比べながら確認することをお勧めします。
例えば、単語と単語の間を詰めて書いていた子どもが、ある日突然、隙間を開けるようになったとします。自ら気付いたのか、他者に指摘されたことがきっかけになったのかは分かりませんが、その子どもは、間を空けることを納得して受け入れ、書いているのです。その姿から、思考・表現を見取ることができます。

