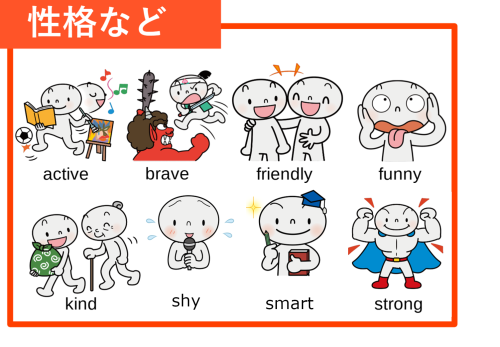小6算数「拡大図と縮図」指導アイデア
執筆/神奈川公立小学校主幹教諭・黒木正人
編集委員/文部科学省教科調査官・笠井健一、島根県立大学教授・齊藤一弥
目次
本時のねらいと評価規準
本時の位置 7/8 縮図の活用
ねらい
直接測ることができない長さを、図形を見いだすことにより縮図を描いて求める方法を考える。

評価規準
身の回りの測定しにくいものを測定する際に、縮図の考えを使い、能率的な方法やいつでも使える方法を考えている。
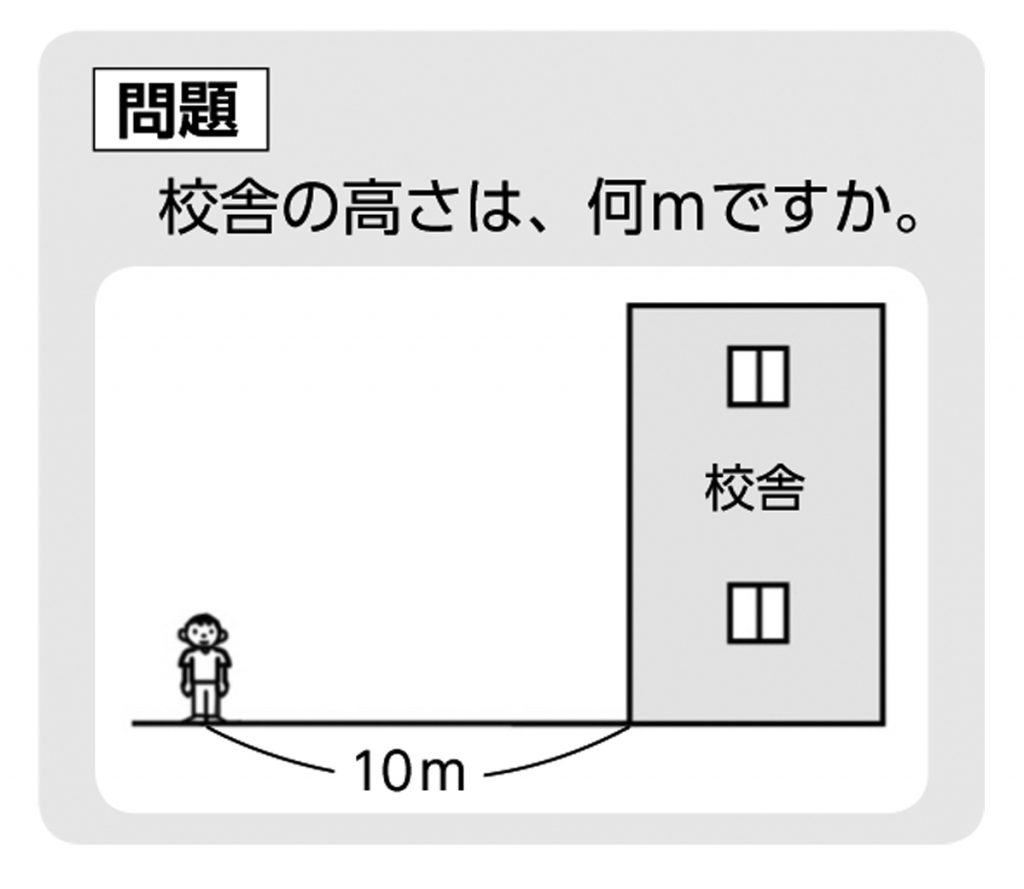
どうやったら、求められるかな。
巻き尺は使えない。
直接、測れない。
直接測れないときは、どうしたらいいかな。
縮図を描いたら、高さがわかりそう。
前回、縮尺がわかれば、縮図から、実際の長さを求めることができました。
縮図にするにも、他の場所の長さや角度がわからないとできない。
何がわかったら、できそうなのかな。
本時の学習のねらい
直接測ることのできない校舎の高さを、縮図を描いて求める方法を考えよう。
見通し
校舎と人を結ぶと、図形ができそうだな。
前時には、直角三角形を使って縮図にできたから、今回も使えないかな。
自力解決
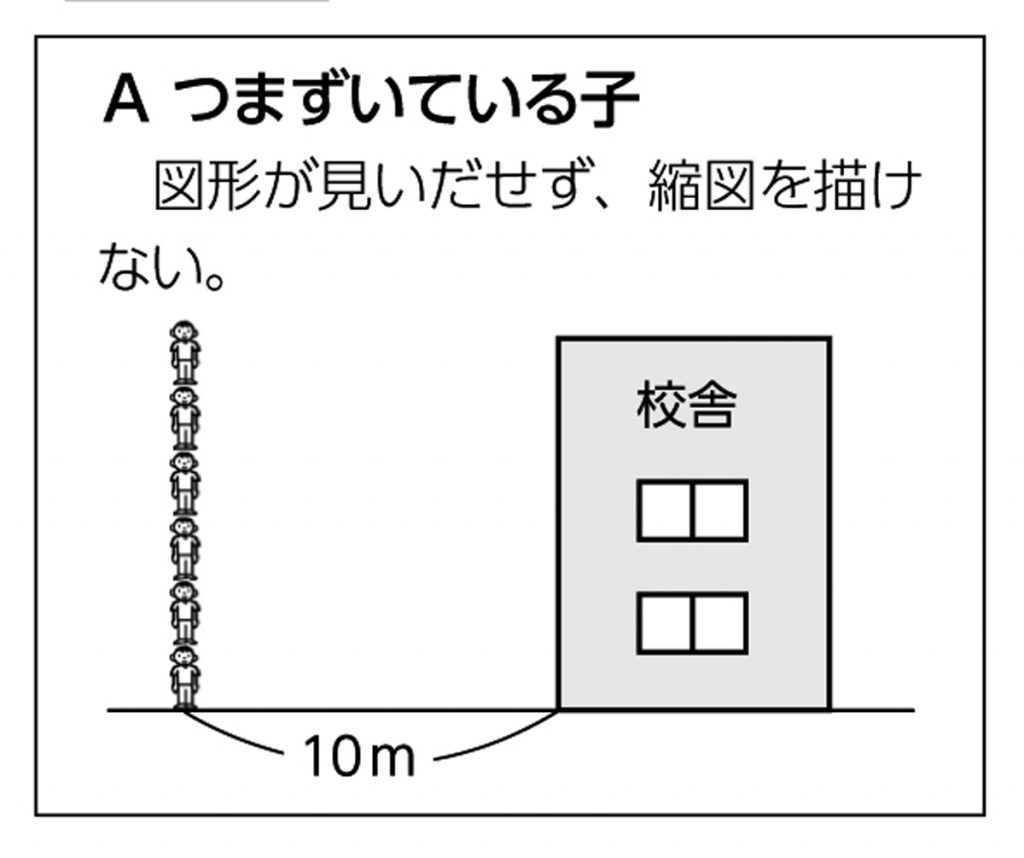
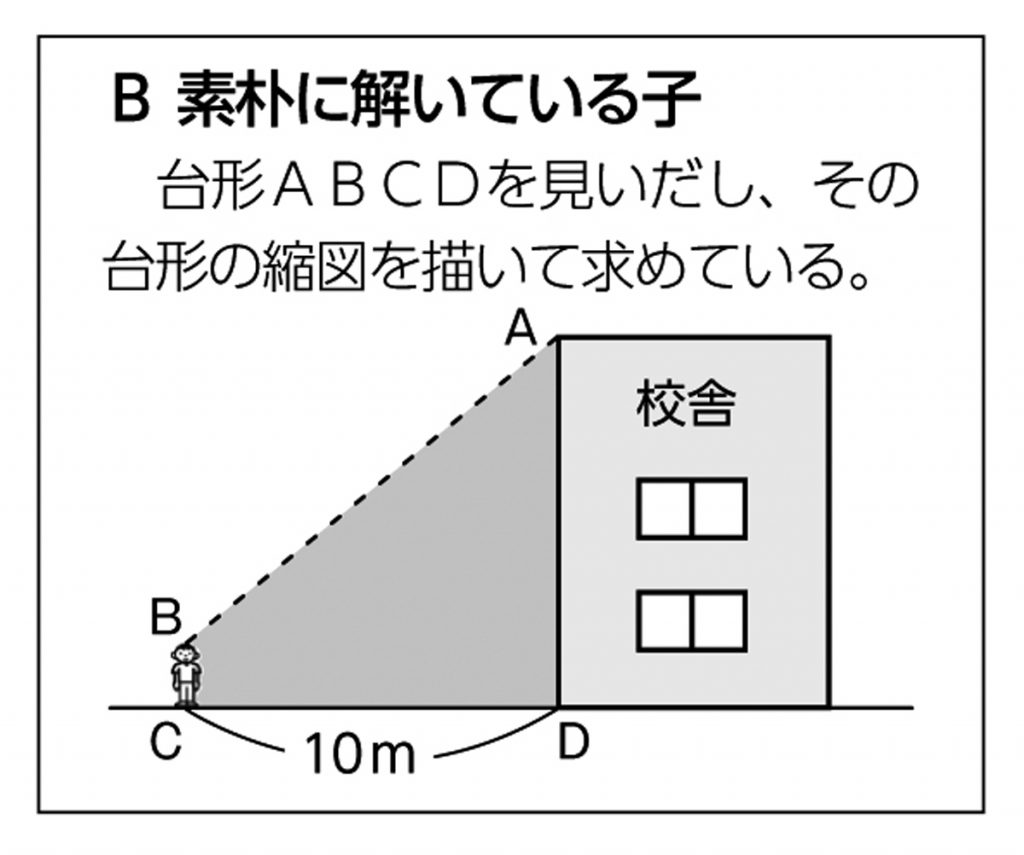
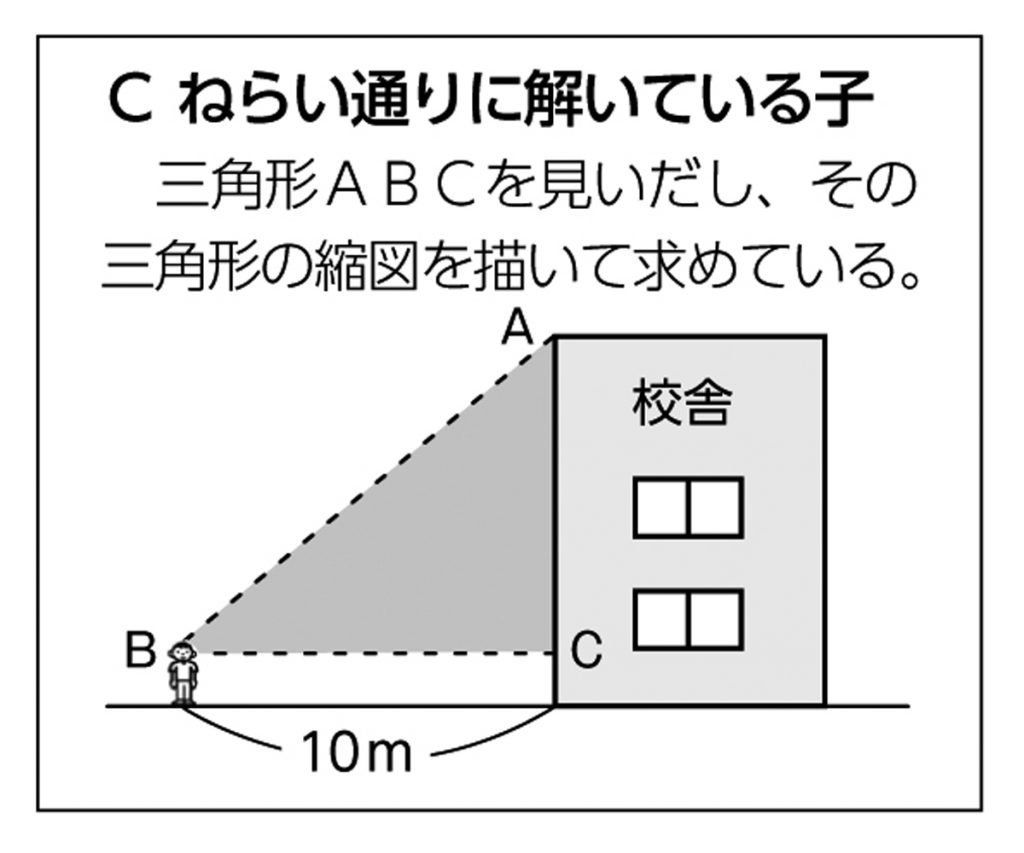
学び合いの計画
イラスト/斉木のりこ
『教育技術 小五小六』 2019年9月号より