教師も管理職も「支える力」と「押し返す力」の両立を|千葉県船橋市の元校長・渡邉尚久氏講演レポート
教育実践研究会「強い風がやむと 雨は降り始める」主催のセミナーにて行われた、渡邉尚久氏の講演レポートです。氏は長年、千葉県の公立学校で管理職や教育行政に関わってきました。
この講演では「支える力と押し返す力」をキーワードに、教師や管理職のリーダーシップについて語っていただきました。自分を知り、その弱さを見つめることで、自分に合ったリーダーシップが発揮できると言います。管理職の方だけでなく、先生方にとっても有意義なお話です。
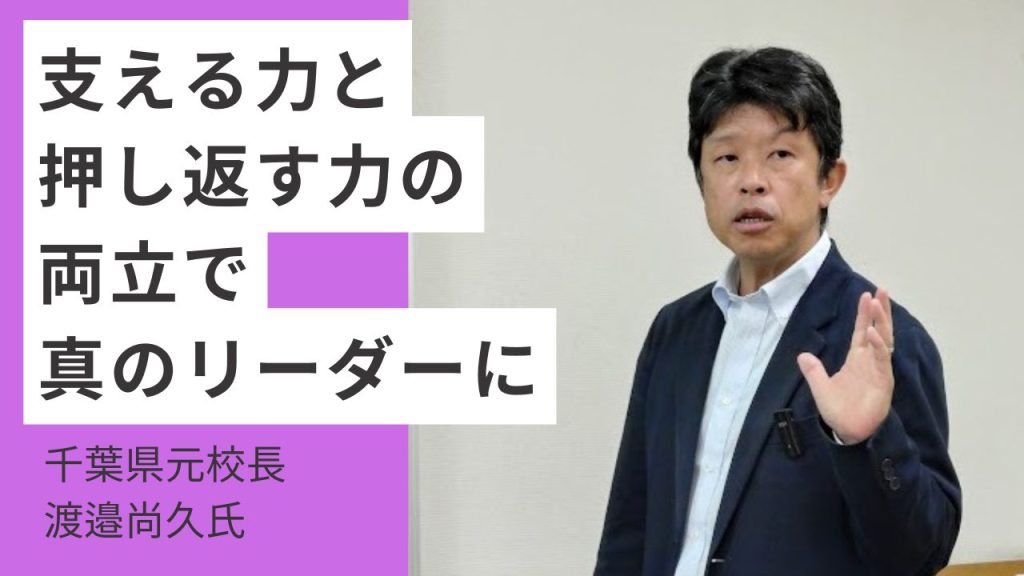
前編はこちら:
職員同士が笑い合う職員室ほど強いチームはない|千葉県船橋市の元校長・渡邉尚久氏講演レポート
目次
「仕えるリーダー」という生き方
サーバントリーダーシップとは
私はこれまで、学校の現場で長く教員を務め、管理職としても働いてまいりました。そのなかで常に心に置いてきたのは、「仕えるリーダーでありたい」ということでした。
リーダーと聞くと、上に立ち、指示を出す人というイメージを持たれがちです。しかし本来のリーダーとは、人に仕える人のことです。英語で「サーバントリーダーシップ」と言いますが、これは「人の幸せを支えるためにリーダーとしての力を使う」という意味です。
人を守るための「権限」
権限というものは、人を動かすための道具ではなく、人を守るために使うものです。職員の幸せのために、自分の権限をどう活かせるか。校長という立場にあっても、私は常に「人の下にいるようにして上に立つ」ことを意識してきました。
私が教頭や校長として仕事をしていた頃、よくこう言われました。「渡邉先生は部下思いですね」と。でも、私は「部下」という言葉が好きではありません。職員はチームの仲間であり、教員としての同志です。校長の役割は「守ること」だと思っています。
教員の中には、仕事を抱え込み、疲れ果ててしまう方もいます。そんなとき、私はよく「今日は無理しないで、明日ゆっくりやろう」と声をかけました。管理職というのは、職員の「盾」になる存在です。学校というのは、誰かが前に出て守るからこそ、全体が安心して動ける組織なのです。
リーダーに求められる「当事者意識」と「自己認識力」
「自分が源泉」という考え方
教育現場で最も大切なのは、「当事者意識」と「自分が源泉」という考え方だと私は思っています。たとえば、「この学校はうまくいかない」「あの保護者は困った人だ」と他者を主語にして語る先生がいます。しかし、そう言った瞬間、自分の手の中から“変える力”が失われます。
「自分が源泉」とは、どんな状況にも自分の関わりがあると考えることです。自分が何をどう働きかけているかによって、現実は変わる。つまり、自分の影響力を信じるということです。たとえば、授業が荒れてしまったとき、「子どもが悪い」「親のせいだ」と言ってしまえば終わりです。でも「自分の指導の中に何か改善できる点はないか」と考えれば、そこに成長のチャンスが生まれます。
自分の癖に気づく「自己認識力」
スタンフォード大学の研究によると、優れたリーダーに共通する資質の第一位は「自己認識力」だと言われています。自己認識力とは、「自分の強み・弱み・癖・傾向を理解していること」です。これが欠けていると、人はいつの間にか他人のせいにしてしまいます。
ある先生が「保護者の対応が大変で、今年は苦情が多い」とこぼしたことがありました。私はその先生にこう言いました。「相手が変わったのではなく、自分が変わったんだ」と思ってみてはどうでしょう。自分の接し方や発言の癖に気づくだけで、関係は大きく変わるのです。

