シンプルに始める!教頭による教員育成改革【GKC|がんばれ教頭クラブ】

管理職による一方的で古いやり方の指導がSNS等で批判され、多くの若手教員が情熱や意欲を失っています。教頭・副校長には学校の質を守る責務がありますが、今求められるのは信頼と寄り添いによる支援、つまり心理的安全性のある環境です。若手教員が「この人にならついていきたい!」と思えるような関係性の構築が、教育現場の再生の鍵となります。
執筆/元山形県公立学校教頭・山田隆弘(ようだたかひろ)
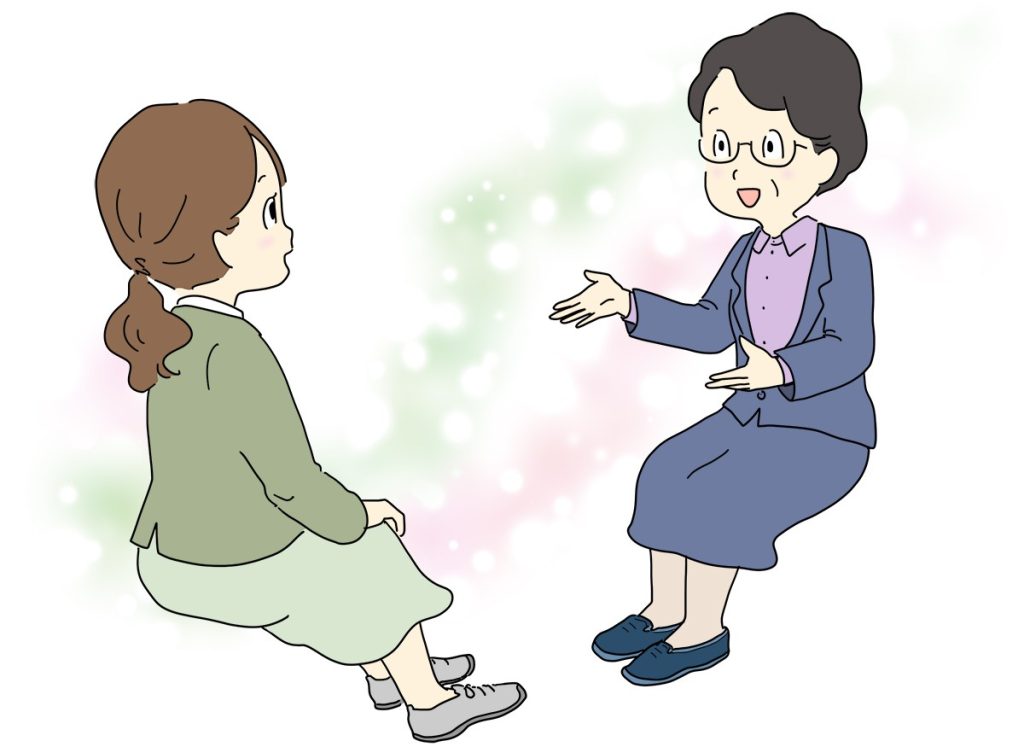
目次
1 すべての支援の土台は絶対的な信頼
管理職(指導教員)からの助言が口うるさい小言ではなく、期待のメッセージとして伝わるには、若手教員との間に揺るぎない安心感(信頼)が必要です。この土台がない限り、どんな指導も「圧」になり、意欲を削いでしまいます。
(1)まずは人として心を開く姿勢
管理職は完璧である必要はありません。人間味を見せることで、若手との心の距離を縮めていきたいです。形式的な指示出しだけでは、人は心を開きません。廊下での挨拶や休憩時間での短い雑談といった非公式な関わりこそが、心理的バリアを下げる最初のステップとなります。心を開く姿勢とは、管理職側からの自己開示を意味します。
①失敗談の共有とその乗り越えのプロセスを伝える
指導者(管理職)の若手時代の失敗とどう乗り越えたかということを具体的に話していきます。管理職もかつてはつまずいた一人の教員だったという共感が、「この人になら正直に話せる」という安心感を生みます。単なる武勇伝ではなく、「あのとき、どう考え、何を試行錯誤したか」という苦労のプロセスを具体的に共有することが大切です。これにより、若手教員は失敗を恐れず、改善の道筋をイメージできるようになります。
②判断基準を公開し透明性を確保する
なぜそういう指導をするのかを明確に伝えたいです。その判断が私情ではなく、児童生徒の安全と成長という最も大切な基準に基づいていることを示すことで、信用が得られ、指導の正当性が担保されます。また、学校運営の透明性が高まることで、若手教員は単なる指示の受け手ではなく、チームの一員として学校経営に参画している意識を持つことができます。
(2)「あなたの成長が最優先」を態度で示す
口先だけでなく、行動で「あなたを大切に思っている」というメッセージを伝えます。言葉よりも行動で示された一貫性こそが、信頼の証となります。
①育成時間を聖域化し質的に保証する
若手教員との面談や授業参観の時間は、最優先します。急な会議や雑務でこの時間を絶対につぶさないと決めることで、「忙しくても自分を見てくれている」という信頼が生まれます。継続的な対話の時間がある保証が、日々の実践への安心感につながります。さらに、単に時間を確保するだけでなく、面談や指導時間のテーマを事前に共有し、若手教員が何を話したいか、何に困っているかを把握しておくことで、対話の質を高めることができます。
②即時フィードバックをし不安を払拭する
授業を見た後、その日のうちに、たとえ一言でも声をかけたいです。「忙しいから後で」では不安を増大させます。とくに、最初に良かった点や努力が認められる点を具体的に伝えることが、不安を打ち消す最大の安心材料になります。即時性が、「きちんと見ていた」という動かしがたい証となり、信頼を築きます。もし改善点について話す場合でも、まずはポジティブな事実から入り、建設的な提案として伝える配慮が必要です。
2 指導と気負わず伴走者(コーチ役)になる
信頼関係ができたら、次は、指導したり、教えたりすることを控えて、個に寄り添う支援(個別最適化)を始めます。指導者が一方的に話すのではなく、教員自身に気づかせることが、自律的な成長を促し、教育の質を向上させます。
(1)評価ではなく事実を伝える
授業参観では、主観的な良い・悪いを伝えないようにします。客観的な事実だけを冷静に記録し、共有することに徹します。指導者の主観が入ると、教員は反射的に防衛的になり、成長のための内省が阻害されていきます。事実に基づく記録は、対話のための共通言語となり、冷静な自己分析を可能にします。
①客観的な事実のみを記録する事例
- 教員が話した時間(授業者発話量)と、児童生徒が発言した回数(児童発話量)の割合
- 作業時間なのに手が止まった児童の人数や時間帯
- 特定の児童への声かけ回数の偏り
など、データや事実だけを冷静に記録します。これにより、「板書が雑だっ!」といった主観的な評価ではなく、「10分のうち、板書に費やした時間が3分あり、その間、後方の児童の手が止まっていた」という客観的な事実に基づいた議論が可能になります。
②共有し、事実からプロの技術論へ
この記録を若手教員に示し、「これが客観的なあなたの授業です」と伝えます。指導が感情論ではなく、事実に基づいたプロの技術論として受け入れられるようになります。
(2)指示ではなく質問で考えさせる
問題点が見えても、すぐに解決策を指示しないようにします。質問で内省を促し、自分で考える力を養わせていきます。これは、教員自身に気づきと発見を与えるコーチングのアプローチです。
①内省を促す質問例(過去と現状の分析)
【過去と現状の分析を深める質問例】
「なぜこの方法を選びましたか? その意図は?」
「あのとき、発言できなかった児童はどんな気持ちだったと思いますか?」
「あなたの授業の目標を達成するために、最も効果的だったと感じる瞬間はどこですか?」
【前向きな行動につながる質問例】
「次回、同じ単元を行うとしたら、どの部分にたった一つだけ変化を加えますか?」
「その変化を加えることで、児童の反応はどのように変わると期待しますか?」
「その解決策を実践するために、わたしがサポートできることは何ですか?」
②じっくり耳を傾け、経験を役立つ知識に変える
管理職が話す時間を減らし、教員の話をじっくり聞くことに徹します。質問に答える過程で、教員自身が課題と解決策に気づくことが、真の成長につながります。この対話の積み重ねが、経験をさまざまな場面で使える指導のワザ(教授スキル)へと変えていきます。

