低学年の質問指導「問いに親しむ」指導のコツ|問いを生み出す「質問力」の育て方〈第2回〉
生成AIが普及していくこれからの時代では、「何を問うか」という力がますます重要になってきます。しかし、そもそも「問いの立て方」を十分に学ぶ機会がなかった私たちにとって、「問うことを教えること」は容易なことではありません。神戸大学附属小学校教諭の友永達也先生が、子どもの「問いを生み出す力」を育むための指導理論を解説する本企画、第2回は主に低学年の子どもを対象に、「問いに親しんでもらう」にはどうしたらよいか、具体的な実践アイデアを交えながら紹介いただきます。
執筆/神戸大学附属小学校教諭・友永達也
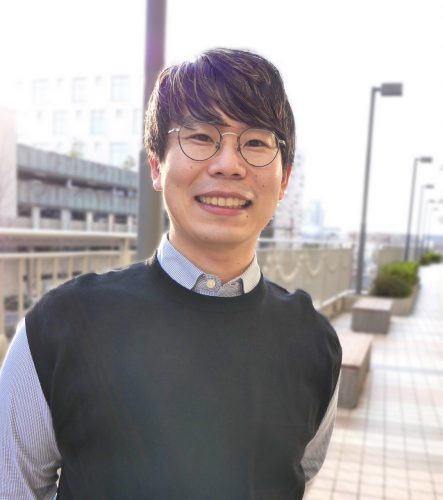
執筆/友永達也(ともなが たつや)
神戸大学附属小学校教諭。専門科目は国語科。とくに話すこと・聞くことの指導に関心があり、現在、学習者が問う力を高めるカリキュラムの開発や、メタ認知に基づく判断を生かしたコミュニケーション教育、小学生を対象とした聞き書きプロジェクト等に取り組んでいる。また、国語科を中心として、問題解決的な単元デザインや、それを支えるノート指導にも日々取り組む。 全国大学国語教育学会、日本国語教育学会、日本教育方法学会、国語教育実践理論研究会(KZR)に所属するとともに、尼崎市の国語科授業サークルのアドバイザーを務めるなど複数の国語科研究会の運営にも携わる。
単著に『対話を深め・問う力が育つ 質問力アクティビティ40』(東洋館出版社・2025年)、『1回10分!トークタイムできく力を育てる ストラテジック・リスニング』(明治図書・2020年)が、分担執筆に『対話的に学び「きく」力が育つ国語の授業』(明治図書・2018年)、『「感性的思考」と「論理的思考」を生かした「ことばを磨き考え合う」授業づくり』(明治図書・2020年)等がある。
第1回:問いを生み出す「質問力」の育て方〈第1回〉コミュニケーションに不可欠な3種類の問いとは?
教室のコミュニケーションを豊かにするためには、お互いに質問し合って考えを広げたり深めたりすることが必要不可欠です。多様な社会を生き抜くこの「質問力」は、どのようにすれば身に付けられるのでしょうか。本記事では、問いを生み出す力をどうすれば子どもたちに育むことができるのかという指導理論について、具体的な実践アイデアも交えながら紹介していきます。
よりたくさんの指導アイデア、より詳しい理論的な説明が知りたい方は、執筆者が2025年に刊行した『対話を深め・問う力が育つ 質問力アクティビティ40』(東洋館出版)をぜひ手に取っていただけると幸いです。
目次
低学年の子どもたちの特徴
低学年は、「友達に伝えたい!」「考えを聞いてほしい!」というコミュニケーションへの意欲にあふれた子どもが多いです。我先にと自分の話をしようとする、そんな学年です。月曜日の朝、教室に入ると、「先生! 昨日ね! 私ね! ○○へお出かけしたんだよ!」とあいさつも忘れて週末の活動報告を受ける経験は、低学年を担当したことがある教師なら一度はあるのではないでしょうか。
もちろん、意欲的な子どもばかりではありません。とくに2年生ごろになると、自分の考えを伝えるのに戸惑っている子、呼びかけへの反応が遅い子も気になり始めます。こういった子どもたちとは、とくに一対一の関係づくりと、教師の粘り強い声かけが必要です。どんなことに戸惑っているのか、どこまでだったら伝えられそうなのか、丁寧に聞き出します。そして勇気を出して伝えられたときには、すかさずほめ、がんばれたことを一緒に喜んであげましょう。そういった日々のかかわりがとくに必要なのが、この低学年の時期といえます。
そんな低学年の子どもたちですから、問うことに関する実態としては、問うことよりも答えることのほうに意識が向きがちです。「○○してみるのはどう?」と、たとえ子どもが問いかけていたとしても、相手の返答はお構いなしという状態によく出くわします。相手の返答を聞いてすらいないときもあります。コミュニケーションの目的達成を目指した問いかけというよりは、その場で感じたり思ったりしたことを、問いという形で無意識に発言しているようなイメージです。
ちなみにこのような子どもの姿は、幼児期である5歳児(年長クラス)でも見かけます。その意味では、質問力指導は幼小接続も意識して取り組むとよいでしょう。「なぜなぜ期」と呼ばれ、興味があることは何でも質問してくる幼児期から、一貫して質問力を育てることができれば、日本における子どもたちの質問力の様子もずいぶん変わってくると考えています。
低学年の質問力指導は「問いに親しむ」ことを大切に
とくに低学年では、「質問する」ということを子どもたちに意識させることが重要です。普段は無意識に相手に質問をしている子どもたちに、相手に質問をするという行為と向き合わせるのです。
そしてそのうえで「質問をするといいことがある」「質問をするのが楽しい」という思いをもたせてあげましょう。これから一生をかけて培っていく質問力の土台を、この時期にしっかりと育てたいのです。そのため低学年の子どもたちには質問力指導の出発点として、「問いに親しむ」ことを大切にした指導が重要になってきます。
ここで注意しておきたいのは、子どもが質問することを嫌ってしまうような指導をしないということです。それは問いに親しむ指導とは正反対の指導になってしまいます。
例えば全体説明の後にわからないことを質問してきた子どもに「さっき言ったでしょ!」と大人が言ってしまうと、子どもは質問することに委縮してしまいます。そもそも質問することは「自分はわかっていない」ということを表明するリスキーな行為でもありますから、放っておけばだんだん質問しなくなってしまうものなのです。だからこそ質問をしてくれた子どもには最大限の温かさを示さなければなりません。
「さっき言ったでしょ!」と言いたい気持ちをぐっとこらえて(そう言いたくなる気持ちはよくわかります)、「さっきも言ったんだけど、○○さんが質問してくれたおかげで、聞いているみんなももっとしっかり理解できたと思うよ。どうもありがとう」と言えるかどうか。ここは低学年の質問力指導の大きな分かれ目です。
低学年向け実践アイデア「おたずね20」
ここで、低学年の子どもたちが問いに親しめるようになる指導を一つご紹介します。その名も「おたずね20」です。推理ゲームの一つとして様々な名前でも呼ばれていますが、端的に言えば質問を通して相手の頭の中にあるワードを言い当てるゲームです。ルールと実施の手順は以下の通りです。
➀出題者は教室の前に出る
➁出題者は頭の中に一つのワードを思い浮かべる
➂そのワードを先生に伝える(後で出題者が勝手に答えを変えることを防ぎます)
➃回答者(出題者以外の全員)は「はい」か「いいえ」で答えられる質問をする
➄回答者は20回以内に出題者の頭の中のワードを言い当てる
➅言い当てるときは「答えは○○ですか」と質問する
➆言い当てるチャンスは3回とする
例えば出題者が「りんご」を頭の中に思い浮かべたとします。「それは食べ物ですか」という質問には「はい」、「それは辛いものですか」という質問には「いいえ」で答えなければなりません。そうして20個の質問を通して、回答者は言い当てるワードを確定していきます。質問で言い当てるというゲーム性に、子どももワクワクして取り組みます。質問したい子どもが勢いよく手を上げます。この時点ですでに質問することに親しむという目的は達成されているでしょう。
さらに、この活動のよいところは、知らず知らずのうちに子どもの聞く力を高めてくれることです。20回しか質問できないのですから、同じような質問はご法度です。過去にどんな質問がされたのか、どのような回答があったのかしっかりと聞き分けておく必要があります。
加えて「それは食べ物ですか」「はい」のやり取りの後に、「それは怖いですか」という質問は不適切な質問だということがわかる子どもも出てきます。「怖い食べ物」はあまり想像がつかないので、20回のうちの1回を費やして質問をするのは得策と言えないからです。これは質問の質にも自然と意識が向いている姿でしょう。すかさず価値づけたいですね。

もし活動の中で、質問が覚えられなかったり、不適切な質問が多かったりした場合は、教師が黒板に出てきた質問をメモして見えるようにしておくと、子どもたちがゲームを楽しんだり、質問を考えたりすることをサポートできます。
このように「おたずね20」は、楽しみながら質問に親しめるだけでなく、質問の質にも意識が向くという意味で、どの学年にもおすすめの活動ですが、低学年の質問指導の導入としてぴったりです。また、隙間時間に手軽に実施できるので、時間を見付けて定期的に取り組めば、子どもたちはこの活動をとっても楽しみにしてくれるようになるはずです。

