小3「初めての書写の授業」を、どうデザインする?
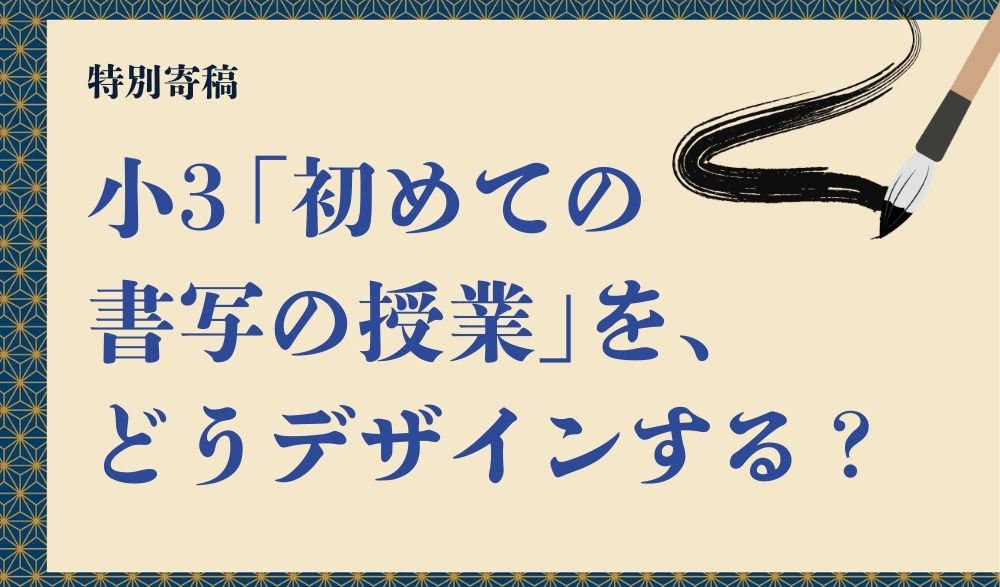
「心を落ち着け、自分と向き合い、相手に思いを伝える営みとしての書道は、日本文化の象徴と言える筆・墨・硯といった道具を大切にする心も育てる」と、筆者の𠮷田拓海先生は言います。3年生が初めて毛筆を手にする授業をより充実させる単元デザイン(3時間)を、動画付きで提案する特別寄稿です。
執筆/京都府立洛水高等学校 芸術科(書道)・𠮷田拓海
目次
はじめに
3年生になると、子どもたちは初めて毛筆を手にします。鉛筆やペンで慣れ親しんできた「書く」という行為が、ここから少し違った表情を見せるようになります。墨の香り、筆のやわらかな毛の感触、半紙ににじむ黒の濃淡はどれも、これまでの学習では味わえなかった体験です。では「子どもたちにとって、書くこととは何か」。この問いに、はっきり答えられる教師はどれほどいるでしょうか。
きれいに書く、整えて書く、筆順を守ることももちろん大切なことです。しかし、それだけでは書写の時間は「字を練習するだけの時間」になってしまいます。
近年はタブレットや音声入力などが当たり前になり、子どもたちの生活から「手で書くこと」が少しずつ遠ざかっています。だからこそ今、筆や墨を使って一文字をゆっくり書くことには、これまで以上に深い意味があります。手で書くという行為は、ただ情報を記すだけではなく、心を落ち着け、自分と向き合い、相手に思いを伝える営みなのです。
また、筆・墨・硯といった用具は「面倒な道具」ではなく、日本文化の象徴ともいえる存在です。きちんと扱い、手入れをすること自体が「ものを大切にする心」を育てます。
さらに、書写は「国語科の学び」として正しく丁寧に書く力を育てる一方、高等学校の芸術科書道では「表現」や「鑑賞」をめざします。両者は別物でありながら、土台にある「文字と誠実に向き合う姿勢」は同じです。
授業デザインの基本方針
- 体験を重視する
結果の美しさよりも、まず「やってみた」という体験に価値を置く。線が太すぎてもにじんでも、それを発見として共有することが学びとなる。- 道具の扱いを学びに変える
筆を洗う、硯に水を落とす、片付けをする。これらを「準備や後片付け」ではなく「学習の一部」として位置づける。- 個人差に配慮する
筆圧、集中の持続、道具の慣れは一人ひとり異なる。「できなかった部分」ではなく「できた工夫」に光を当てる。- 心の成長を位置づける
墨を磨る静かな時間、筆を動かすゆっくりした時間は、子どもの心を落ち着ける。書写を「字を練習する時間」から「心を整える時間」へ広げる。
第1時 導入(文字への関心を高める活動)
【授業のねらい】
- 毛筆に使う道具と出会い、正しい扱い方を知る。
- 筆に親しみ、鉛筆との違いに気づく。
【授業の流れと発問例】
- 道具を紹介する
教師の発問例:「これは何に使うと思いますか?」
教師の発問例:「硯は墨をためるお皿ではなく、墨を育てる場所です。どう違うと思いますか?」
→ ねらい:道具を「ただの道具」とせず、意味を含んだ存在として理解させる。- 机上に配置する
教師の発問例:「道具をどの順番で並べたら書きやすいと思いますか?」
教師の発問例:「机を整えると、どんな気持ちになりますか?」
→ ねらい:配置の仕方を自ら考えることで、作業の主体性を高める。- 水で筆を試す
教師の発問例:「鉛筆で書くときと、筆で書いた線はどう違いますか?」
教師の発問例:「筆を強く押さえると線はどうなりそうですか?」
→ ねらい:墨を使う前に、筆独特の「太さ」「にじみ」に気づかせる。- 振り返り
教師の発問例:「今日の学習で新しく気づいたことは何ですか?」
→ ねらい:気づきを言葉にさせることで、次時につながる期待感を醸成する。
第2時 道具の使い方・墨を磨る方法(実演)・初めての筆運び
【授業のねらい】
- 筆・墨・硯の扱い方を知る。
- 墨を磨る方法を知り、基本の横画・縦画を書いてみる。
教師の発問例:「前回、水で筆を動かしたときに、どんな線になりましたか?」
教師の発問例:「今日は墨を使います。水とどう違うでしょうか?」
【墨を磨る方法の実演(教師が提示)】
実際の小学校教育の場では、45分で固形墨を全員が磨ってから書くのは難しく、普段は墨液を使うのが一般的です。しかし最初に「固形墨の磨り方」を示し、時間のあるときに実際にやらせることにはとても価値があります。墨を磨る音や香り、濃さの変化を感じることが「心を整える学び」になるからです。
教師の発問例:「墨を磨ると、どんな音やにおいがすると思いますか?」
教師の発問例:「色の濃さはどのように変わるでしょうか?」
教師の発問例:「墨液と自分で磨った墨、どういう違いがあると思いますか?」
コラム1:墨と筆に息づく歴史と文化
墨は千年以上にわたり、日本人の生活や文化を支えてきました。奈良時代にはすでに国産墨が作られ、江戸時代には伊勢や大和で高品質の墨が生産されました。煤の粒の細かさや原料によって墨色は変わり、同じ「黒」にも奥行きと幅があります。また、墨色は水によっても変化します。硬水と軟水で墨の伸びや発色が異なることが知られており、自然環境と表現が深く結びついているのです。硯も単なる容器ではなく、「固形墨で墨を磨る場所」として文化的な意味をもちます。石質によって墨の下り方や色合いが変わり、文字の表情そのものを左右します。筆もまた、歴史と文化を背負った道具です。奈良の正倉院には唐の筆が残されており、日本では馬毛・羊毛などを用いた多様な筆が発展しました。
毛質によって線の表情が変わり、近年小学校で使われる馬の筆は「書くときには扱いやすいがきちんと洗わなければ特に割れやすい」という特徴を持っています。こうした歴史や背景を少しでも伝えることで、子どもたちにとって「墨を磨る」「筆を洗う」といった活動が、単なる準備や片付けではなく、日本文化を受け継ぐ営みであることを実感できるようになります
墨の磨り方と墨液の使い分け
高校の芸術科書道の授業で「固形墨を磨ったことがあるか」と聞くと、ほとんどの生徒が小学校、中学校では「ない」と答えます。経験者も多くは誤った方法で磨り、固形墨にヒビが入ったり割れてしまったりする原因をつくっています。よく見られるのは、硯の海に水をため、陸で磨っては海に戻す方法です。このやり方は墨に水が過剰に含まれ、乾燥後にひび割れを起こします。効率的で墨に負担をかけない正しい磨り方をぜひ参考にしてください。
【効率的で墨に負担をかけない正しい磨り方】
1. 陸に500円玉ほどの水をたらす。
2. 墨で「N」や「の」の字を描くように磨る。

3. 濃くなるまで磨り進める。
4. 磨った部分に墨の角で線を引き、溝ができるくらいが目安(下写真参照)。

5. 必要に応じて水を少しずつ足して量を調整する。
↓以上の磨り方を、動画でも解説しています。
【磨った墨のメリット】
- にじみやかすれが美しい。
- 墨色の濃淡を調整できる。
- 筆に優しい。
- コストが良い。
【磨った墨のデメリット】
- 墨色が安定しにくい。
- 防腐剤がなく腐りやすい。
- 準備に時間がかかる。
【墨液のメリット】
- 常に同じ墨色が得られる。
- 黒々とした表現に向く。
- 保存しやすい。
【墨液のデメリット】
- 筆を傷めやすい。
- 濃淡の調整が難しい。
- 表現が単調になりやすい。
授業では墨液を使うのが現実的ですが、固形墨の価値を示すことは不可欠です。特別な時間に磨った墨を使うだけでも、子どもたちは「書に向き合う心」を学びます。

筆の洗い方と用具の扱い
授業で使った筆を観察すると、大筆が割れて広がっていることがあります。原因の多くは「正しく洗えていないこと」です。
【筆を傷める要因】
- 使用後に洗わず乾燥させる。
- 墨が固まっても放置する。
【墨液の性質】
- 学校でよく使われるのは樹脂系墨液。安価で保存性が高いが、お湯に溶けにくく汚れが残りやすい。
【正しい洗い方】
- 使用後はすぐ水で洗い、根元まで墨を残さない。
- 固まった場合はぬるま湯でやさしくほぐす。
- 洗ったら形を整え、乾燥させる。
【筆の材質への配慮】
- 学校の習字セットの筆は馬毛が多く、割れやすい。
- だからこそ「洗う・乾かす」を徹底することが必須。
教師がこの指導を繰り返し行うことで、筆を大切に扱う習慣が子どもに根づいていきます。
コラム2:筆は「命を宿す道具」
筆は単なる文房具ではなく、古来「命を宿す道具」と考えられてきました。筆の毛は動物の恵みから生まれ、羊毛は柔らかく、馬毛は弾力があり、イタチ毛は鋭い線を引けるなど、それぞれに性格があります。これらを組み合わせて一本の筆が作られ、人の手によって磨き上げられた筆は、一種の「生き物」として尊ばれてきました。戦国時代の武士が武具とともに筆を持ち歩いた記録や、学者が亡くなる際に愛用の筆を棺に納めた例などからも、筆が「人の心を託すもの」と見なされてきたことがわかります。
子どもたちに「筆も命ある素材から生まれている」と伝えることで、単なる消耗品ではなく、大切に扱うべき道具だという意識を育むことができます。筆の根元に墨を詰まらせない、洗ったあとに形を整える、といった細やかな指導も、文化を大切にする心を育てる学びへとつながります
第3時 まとめと作品づくり
【授業のねらい】
- 自分の墨(または墨液)を使い、名前や一文字を清書する。
- 書いた字や体験を振り返り、学級全体で共有する。
【授業の流れと発問例】
- 墨を擦る
教師の発問例:「今日は5分間で磨ってみましょう。音や香りにどんな気づきがありますか?」
→ ねらい:短時間でも「自分の墨」を用意する体験を持たせる。- 作品づくり
教師の発問例:「自分の名前や大切にしたい一文字、どちらを書いてみたいですか?」
教師の発問例:「1枚に心をこめて書くには、どんな気持ちで臨めばよいでしょうか?」
→ ねらい:題材選びに主体性を持たせ、清書を「自分の作品」として位置づける。
→ 留意点:初回は「清書1枚」で十分。量よりも集中して取り組む姿勢を評価する。- 振り返り
教師の発問例:「墨を擦ってから書いてみると、どんな感じがしましたか?」
教師の発問例:「今日の学習で工夫したことや挑戦したことは何ですか?」
→ ねらい:プロセスに価値を見いだし、次の学習につなげる。- 鑑賞活動
教師の発問例:「同じ文字でも、友だちの字と見比べてどんな違いがありますか?」
教師の発問例:「一人ひとりの作品から学べることは何でしょうか?」
→ ねらい:多様な表現に気づき、互いの努力を認め合う場をつくる。
→ 留意点:順位付けを避け、努力点や工夫点に光を当てる。- 教師の工夫例
【1. 準備・片付けを学びに変える】
「筆を洗って干すまでが授業です」と伝える。
下敷きや文鎮は自分で配置させる。
新聞紙で机を養生させ、子ども自身が環境を整える体験を持たせる。
→ 意図:用具を「準備されるもの」ではなく「自分で整えるもの」と意識させ、学びの主体性を育てる。
【2. 学級経営の工夫】
忘れ物が多い子には「貸し出しボックス」を用意し、責めるのではなく工夫で補う。
道具を扱う係をつくり、授業開始前の準備や終了後の確認を習慣化する。
→ 意図:ルールを通じて集団で活動する力を育てる。
【3. 評価の工夫】
「清書の完成度」だけでなく「工夫点」「挑戦点」を評価する。
ルーブリック例:
① 道具を整えて使おうとしたか
② 線や字の形を工夫しようとしたか
③ 書いた後に自分の字を振り返ったか
おわりに
歴史的展望
古代から筆と墨は、日本人にとって「書くこと」と「祈ること」を結びつける道具でした。
平安時代の仮名文学では、墨色の濃淡が感情を映し出す表現に用いられ、江戸時代には寺子屋教育を通じて庶民の生活に深く根づきました。そして現代、デジタル化が進む社会にあっても、毛筆は「心を込めて書く」という体験を提供します。書写を通じて伝統を子どもたちに伝えることは、未来への文化継承そのものです。
未来における「書くこと」の意味を問う
21世紀に入り、教育現場にも急速にICT化の波が押し寄せてきました。タブレット端末が1人1台配備され、子どもたちはキーボードやタッチペンを使って思考を可視化し、表現を広げることができるようになりました。こうした変化は歓迎すべきものですが、その一方で、「手で文字を書く」という行為の意味が、あらためて問い直される時代にもなったと言えるでしょう。
書写教育が担う“未来をつくる力”
書写は、どんなにデジタル化が進もうとも、人と人とが「心を通わせるための基盤」であり続けます。そしてその価値は、子どもたちが社会に出てからも失われることはありません。
- 筆跡からにじみ出る心のこもったメッセージ
- 一筆一筆に思いを込めて仕上げる卒業証書
- 心を落ち着かせて整える書道の時間
これらはすべて、「未来の社会で必要とされる人間力」を育てる営みです。
書写の授業は、ただ字を練習する時間ではありません。筆や墨に出会い、静かな時間を過ごしながら、自分の名前や一文字を書き記すことそのものが、子どもにとって特別な学びです。普段は墨液を使う現実の授業の中でも、固形墨の磨り方を教え、ときには体験させることで、書写は“準備”から“心を整える学び”へと変わります。
教師の発問を通じて「なぜ?」と問いかける授業こそが、子どもたちにとっての新しい気づきと学びを生み出します。小3での最初の体験が、その後の書写教育・書道教育、さらに日常生活における「文字を大切にする心」へとつながっていきます。本授業デザインが小学校で子どもたちと向き合う先生方の一助となることを願っています。

<著者プロフィール>
よしだ・たくみ。京都府立高校にて芸術(書道)を指導。
大学時代に著名な先生の影響を受け、イベントに参加、企画・運営し、学び続けている。
単行本『Withコロナ時代のクラスを「つなげる」ネタ73』(黎明書房)に執筆協力。

