自然って面白い! 子どもの探究心が芽生える理科授業【理科の壺】

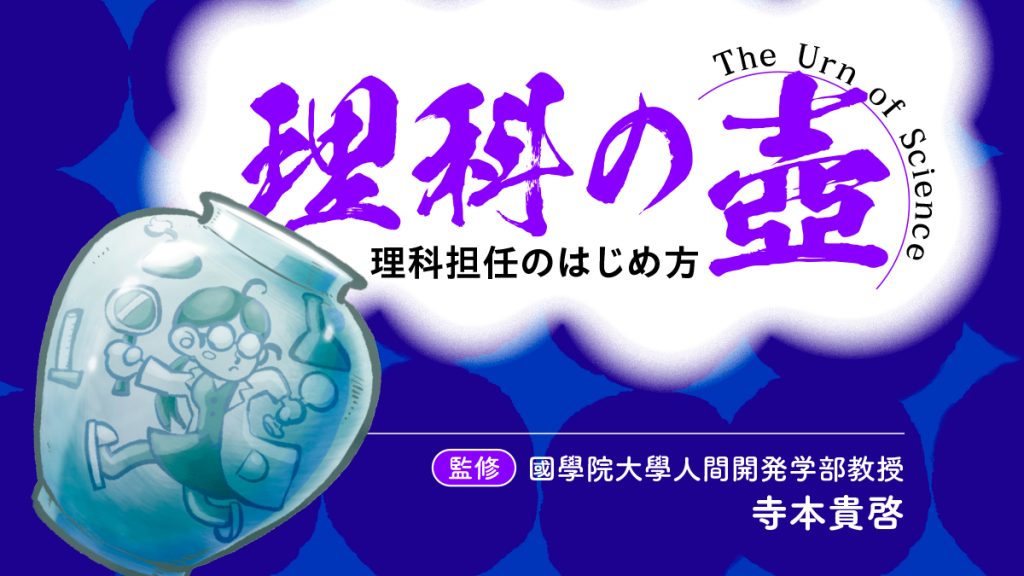
理科は、子ども自身が自然に親しみ、自発的に関わっていくことが大切です。そこで教師に求めらるのは、子どもたちが自ら自然に興味をもてるようになる“環境づくり”や“声かけ”です。今回は、自然、すなわち「身の回りの世界」への子どもたちの興味・関心を刺激する理科の授業を紹介します。“当たり前”だと思っていた身の回りの世界が少し変わって見えることから、自分たちを取り巻く自然への関心が高まり、探究心が芽生えるのではないでしょうか。優秀な先生たちの、ツボをおさえた指導法や指導アイデア。今回はどのような“ツボ”が見られるでしょうか?
執筆/滋賀大学教育学部附属小学校主幹教諭・山際真知子
連載監修/國學院大學人間開発学部教授・寺本貴啓
子どもたちが自然と理科の世界を楽しみ始める授業を紹介します
教科書の問題に「昆虫の~」「植物は~」「動物は~」と書いてありませんか?
例えば植物の場合、「ヒマワリは、どのように成長するのだろうか」などと、ある特定の種類に限定されていません。なので、「植物は〜」と一般化できるように学ぶには、ホウセンカもマリーゴールドも取り上げなくてはいけない⋯⋯と、授業づくりが少し大変に感じられるかもしれません。
でも、あるポイントを押さえれば、子どもたちは、自ら身近な動植物をいくつか比べてみたり、観察・実験したりすることを通して、理科の世界に興味や関心をもち始めます。
そんな「理科の世界=身の回りの世界」を子どもたちが楽しみ始める理科授業を2つ紹介します。
【昆虫編】着眼点は足! 足の形の違いで何が分かる?
第3学年『昆虫の体のつくり』では、「頭、胸、体の3つの部分に分かれていて、胸には6本の足があるものを『昆虫』という」と学習します。
私はよく子どもたちと虫を捕まえてきて、それが「昆虫」なのかを一緒に調べます。体が3つの部分に分かれているかは見分けにくいので、たいてい足に注目して分類します。そして、見付けてきた昆虫や、図鑑に載っている昆虫の写真を並べて、足に焦点を置いた問いかけをします。
どの昆虫も足の数は同じだけれど、似ているところや違うところはどこかな?
すると、
「どれも曲がるところがある」
「長さが違う」
「バッタのいちばん後ろの足は太くて長い」
など、足の形の共通点や差異点に気づきます。
ほんとうだね。
なんでバッタのいちばん後ろの足は太いのかな?
と、さらに問いかけると、
「だってバッタはジャンプするから」
「バッタはすっごく飛ぶんだよ」
「チョウは、花とかに止まるだけだから短くていいんだよ」
と、自分の知っていることと、目の前のバッタの足の形とを結びつけて話し出します。
足に焦点化して比べることで、足の形の似ているところや違いに気づくことができます。さらに、その違いがなぜかを考えることで、「足のつくりの特徴」と「過ごし方」を結びつけて考えられるようになります。

